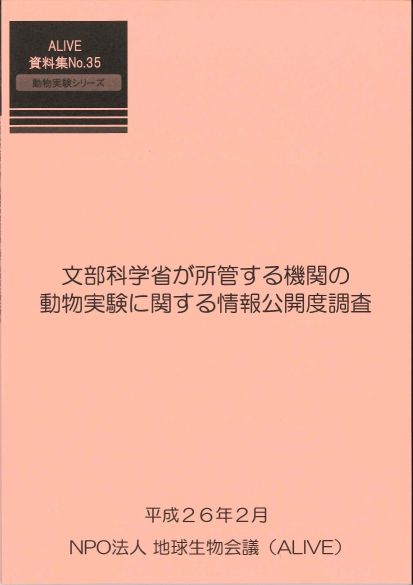文部科学省の動物実験基本指針(2006)では、
「研究機関等の長は、研究機関等における動物実験等に関する情報(例:機関内規程、動物実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等)を、毎年1回程度、インターネットの利用、年報の配付その他の適切な方法により公表すること。」
とされています。
本資料集は、文部科学省が所管する全国の国公私立大学その他の動物実験を行っている381機関(国立大学74機関、公立大学50機関、私立大学245機関、独立行政法人・大学共同利用機関法人7機関、高等専門学校5機関)を対象にした調査結果で、各機関が公開する情報を、15項目にわたり表とグラフにまとめ、統計、分析したものです。
また、各機関の情報公開度を点数化した一覧表付きで、機関ごとの優劣が一目瞭然にわかるようになっています。
情報公開を含めた文部科学省の基本指針の遵守状況については、2011年に文部科学省が行ったアンケート調査がありますが、文部科学省の調査は、対象機関の答えをそのまま集計したもので、実際に情報公開がされているかどうかを確認したものではありません。今回のALIVE調査は、インターネット検索により、各機関のホームページを実際に1つずつ見て確認した結果を集計したものです。検索で情報公開のページが見つからない機関にはFAXやE-mail、郵送で照会を行い、ページの有無を確認しています。
基本指針ではインターネットの他に年報の配布等による公開も認められていますが、今回の調査ではあくまでインターネット(ホームページ)での情報公開を対象としました。
また、文部科学省の調査は情報公開を「している」か「していない」かだけを調べたものですが、ALIVE調査は情報公開の中身にまで踏み込んで詳しく統計しています。
今回の調査で、主に以下のようなことが分かりました。
● 文部科学省の基本指針制定から7年経っても、指針で定められた情報公開を行っていない、または行っていないと疑われる機関が全体で1/5、特に私立大学では1/4にのぼる。
● 各機関の情報公開度を点数化した結果、全機関平均は15点満点中3.4点と低い値であり、全体で3割の機関が1点以下、半数以上の機関が3点以下であった。
● 国立の機関と公私立の機関で情報公開度の落差が激しい。(2倍程度)
● 一般市民の関心事項(①何のために、②どんな実験を、③どれだけの動物を使って、④どれほどの苦痛を与えているか)がほとんど反映されていない。
このような試みは全国初の試みです。
ご近所の施設等へ情報公開の促進を訴える活動の材料にしていただければ幸いです。
<目次>
1. 文部科学省の動物実験基本指針 ・・・01
2. 動物実験を実施している研究機関 ・・・02
3. 調査期間 ・・・03
4. 調査方法と対象機関 ・・・03
5. 何らかの情報公開を行っている機関の割合 ・・・04
6. 項目別の情報公開度 ・・・05
7. 各機関の情報公開度を点数化 ・・・07
8. 各項目の解説 ・・・09
9. 文部科学省が所管する全国381機関の情報公開度比較表 ・・・24
10. 文部科学省が所管する全国381機関の点数・偏差値一覧 ・・・60
11. 情報公開に見られた自主管理の取り組み事例 ・・・66
12. まとめ ・・・67
13. 提言 ・・・68
14. 最後に一般市民の皆様へ ・・・69
参考資料
1.「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」全文 ・・・70
2.「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」 ・・・73
(平成18年6月1日施行)より情報公開に関する部分の抜粋
3.「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」 ・・・73
(平成18年6月1日施行)より情報公開に関する部分の抜粋
4.「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」 ・・・74
(最終改正:平成25年環境省告示第84号)より情報公開に関する部分の抜粋




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求