これに関して、ALIVEでは、以下のような条件付賛成の意見を出しました。
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」改定案に関する意見
<該当個所>
「適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に 危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせる
おそれがない場合は、この限りではない。
1.警察犬、狩猟犬等をその目的のために使役する場合
2.人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い 払いに使役する場合」
<意見内容>
家庭犬を獣害対策に活用することは、犬の能力を発揮させることにより、 野生動物をみだりに駆除しなくてもよくなることが期待でき、賛成です。
今後、農作物被害防除の労力やコストの削減のためにも、各自治体・ 地域での取り組みが広がっていくことが予想されますが、その場合、
放し飼いに伴うリスクを最小限に抑えるために、以下のような措置を 基準で定めておく必要があると考えます。
1.および2.の場合には、以下の措置を行うこと。
1)登録及び狂犬病予防注射に関する義務が守られていること。
2)必要に応じて感染症等の予防措置を行うこと。
3)迷い犬としないために個体識別措置を行うこと。
4)野良犬を増やさないために不妊去勢措置を施すこと。
5)訓練においては、犬の個性や習性を尊重し、過酷なものとならないようにすること。
<理由>
1)狂犬病予防の観点から、登録と予防注射の義務を確認する必要があります。
2)近年、各地で犬由来と考えられるカイセンなどの皮膚病がタヌキなどの野生動物に感染していることが報告されています。一方、山野に犬を放した場合に、犬がダニなどの寄生虫に感染する場合もあります。寄生虫や病原菌などが野生動物と飼育動物の間で交差感染しないように、十分に注意を払うべきです。
3)毎年、狩猟シーズンが終わる頃になると、逸走したかあるいは遺棄された猟犬が各地の保健所や動物愛護センターなどに収容されます。猟犬や追い払い犬が追跡に夢中になって遠く離れ帰ってこれなくなる場合もありえます。放し飼いの犬の場合は、首輪に鑑札および飼い主の連絡先入りの迷子札、マイクロチップの装着を義務付けるべきです。
4)行政の施設に持ち込まれる犬の大半は子犬です。放し飼いにより望まれない子犬が産まれないように、不妊去勢手術を施すことも必要です。
5)犬の訓練においては、犬が自ら喜んで行うようその犬の適性を活用する方法をとり、暴力や懲罰等の過酷なしつけを決して行わないことが重要です。過酷な訓練は咬傷事故などを誘発するおそれがあります。
地球生物会議 ALIVE




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求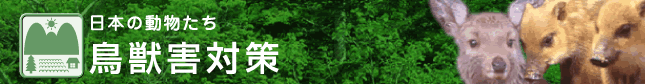
 日本の農耕社会では、昔から犬は農地に近づく野生鳥獣を追い払う役目を担っていたと考えられます。かつては、犬は放し飼いが当たり前でしたが、戦後、狂犬病対策のために、犬のつなぎ飼いが義務付けられました。放し飼いにしていると保健所に捕獲されてしまい、厚生労働省の統計によると、1971年に捕獲された犬の頭数は723,973頭にも及びます。
日本の農耕社会では、昔から犬は農地に近づく野生鳥獣を追い払う役目を担っていたと考えられます。かつては、犬は放し飼いが当たり前でしたが、戦後、狂犬病対策のために、犬のつなぎ飼いが義務付けられました。放し飼いにしていると保健所に捕獲されてしまい、厚生労働省の統計によると、1971年に捕獲された犬の頭数は723,973頭にも及びます。