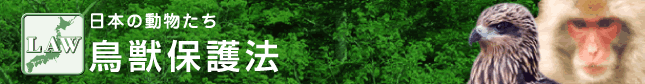ðN12ɬ§µ½u¹bíQh~Á[@vÍA±ÌQQPúÉ{s³êé\èÅA»êÉ槿A@¥ÅèßçêÄ¢é_Ñ
YåbÉæéuî{wjvÉ¢ÄApubNRgª¡ú©çnÜèܵ½B
úÀF2008N117ú`PRPúií¸©QTÔj
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=Pcm1010&BID=550000726&OBJCD=100550&GROUP=
ALIVEÅÍAȺÌÓ©ðñoµÜµ½B
½¬20i2008jN123ú
¹bÉæé_Ñ
YÆÉWéíQÌh~̽ßÌ{ôðÀ{·é½ßÌî{IÈwjÉ¢ÄÌÓ©
n
¶¨ïc@ALIVE@ã\@ìãÓ³q
YÓP.7`P.8
ê@íQh~{ôÌÀ{ÉÖ·éî{IÈ
R@À{̧̮õ
Ó©ER
@(1)íQÎôh~¦cïÌiÉ¢Ä
@@EíQh~væðôè·éɽÁÄÍAíQÎôh~Îô¦cïðÝuµÄA¢ðKvÆ·é±Æð¾LµÄ¾³¢BNªAÇÌæ¤È豫ðoÄvæð§Äµ½Ì©ð¾ç©ÉµÄ¨Kvª èÜ·B
@@EíQh~Îô¦cïÍAs¬ºA_ÑÆcÌAÂFïAs¹{§Ìyw±@ÖÌÖW@ÖÅ\¬·éÉÆÇÜç¸AÏÉIÉnæZ¯ÌQÁð£·àÌƵľ³¢BnæÐïɨ¢ÄÍAæ»ÒªÄèȱÆðµÄ¢éÆvíêéÆZ¯Ìðâ¦ÍªiÝܹñBnæ®éÝÌæègÝð·é½ßÉÍAZ¯QÁªsÂÅ·B
@(2)¹bíQÎôÀ{àÌ\¬É¢Ä
@@EíQÎôÀ{àõÉÍA춹b̶ÔyÑ»nÌnÉÚµ¢m¯Æo±ðL·éÒðK¸ÜßéàÌƵľ³¢BEõªàõÉÈéêÍÐèÔÆÈèAì¹b̶ÔɳðÅAȨ©ÂnsÄàÈÒÅÍAƤĢÎôÉøÊÍ]ßܹñB
@(3)ÎÛ¹bßlõÉ¢Ä
@C@eÂÉæéßlÌ]ÒÉ¢ÄÍAeÂÆðLµAßRNÔÉA±µÄoÂo±ª éÒƵľ³¢BëÂo^ðA±µÄsÁÄ¢ÄàÀÛÉoµĢȢÒà½A2007N12ÉN±Á½·è§ÌÂeÉæéElÆÌæ¤ÈÒðrÅ«édgÝÆ·é½ßÉÍAÈÆàA±µÄoÂo±ª é±ÆððÉ·éKvª èÜ·B
@@íÈÉæéßlÉ]·éàõɨ¢ÄàA¯lÉíÈÆðLµAÅáÅàRNÈãÌÀ{o±ðKvÆ·é׫ŷBÀÕÅsKØÈíÈÌËÝÍlgÌâöëßlðø«N±µAZ¯Ì{èâ½ðó¯é±ÆÉÈèÜ·B
YÓP.9
ê@íQh~{ôÌÀ{ÉÖ·éî{IÈ
S@¹bÌßl
Ó©ER
@iPjs¬ºEõâ_ÑÆcÌÌEõÉæéßļÌ\zuÁÉCmVVÉ¢ÄÍ íȪøÊIÅ évÆ èÜ·ªAcLmO}̶§nÅÍöëßlâ¬lª½µÄ¢é±ÆªâèÆÈÁĢܷBíÈÉ¢ÄÍAöëßlE¬lh~ðð¯éû@ÌLÚâAöëßlÌñ`±ð¾L·é±ÆªKvÅ·B
YÓP.11
ê@íQh~{ôÌÀ{ÉÖ·éî{IÈ
T@Nüh~òÌÝuÉæéíQh~
Ó©ER
iPjøÊIÈiüh~òÌÝu
@uiüh~òÌÝuãÌǪs\ªÅ év±ÆªwE³êĢܷªAm©É]©ç½åÈïpÆJÍð¶Èªçøʪ¾çêȢƢ¤á»ðó¯Ä«Üµ½B èAdCòÌúdh~ôâAÎÛ¹bÌK«An`âCóAGß̽lÈðÉKµ½øÊIÈòÌÝuÆÇÌû@ðA«ß±Ü}j
AƵĢKvª èÜ·B
iQjÇ¢¥¢®Ìi
@@jzUÉ¢ÄÍuÇ¢¥¢v̼ÉuÇ¢ã°vðÁ¦Ä¾³¢B_nÉ
¢½TðRÆÇ¢¥ÁÄàAܽ×Ú·é_nÉÚ®µÄµÜ¤¨»êª èÜ·BTÌ{̶§n⶧Â\Ènæð¾ç©ÉµÄA»±ÉuÇ¢ã°évÆ¢¤ÚIðèßéKvª èÜ·B
@@ܽA¢ÉæéÇ¢¥¢E Ç¢ã°ÉÍ¢øʪ é±ÆªmçêĢܷªA¶¢a\h@ânû©¡ÌÌ¢ÉÖ·éðáÆÌÖWð¾LµÈ¢ÆZ¯Éëððµ±ÆÉÈèÜ·B³çÉAÇ¢¥¢É¢ÄÍLøÈPû@ÌJªKvÅ èA»Ìyà í¹Äißé±Æð¾LµÄ¾³¢B
YÓP.12
ê@íQh~{ôÌÀ{ÉÖ·éî{IÈ
U@ßl¹bÌK³È
Ó©ER
@ßlÂÌÌpÉ¢ÄÍAnæÂÌQÌâĄ̊»êÌÈ¢ë¹bÅ éCmVVAVJÉÀè·é±Æð¾LµÄ¾³¢BN}ÍnæIÉâĄ̊»êª éíÅ èAÛIÉà»Ì¹pªâÅÌvöÌêÂƳêĢܷBF_̤æøªì¶ÌN}̧Ââ§Aðø«N±µÄ¢é±ÆA¿Éæø³êéF_ÌÌæðÚIƵÄÓ}IÉíÈŬl³êéÈÇAßlÂÌÌpÉæÁÄâŪë³êé½ßAN}ÉÖµÄÍpðÖ~·é׫ŷBܽAjzUÉ¢ÄÍAÚIðUÁÄßlµAÀ±pÉ÷nÌ·é±Æª½Ñ½ÑsíêĨèA»ÌxfBAÅå«ñ¶çêéÈÇAÐïIá»ðó¯Ä¢Ü·Bú{Í®¨À±É@K§Ì¶ÝµÈ¢BêÌæiÅ èAì¶jzUÌpªÄÑubN}[Pbgð`¬µÈ¢æ¤ÉAßlÌiKÅÌpÖ~ð¾L·é׫ŷB
YÓP.13
ê@íQh~{ôÌÀ{ÉÖ·éî{IÈ
V@Anûö¤cÌÌAgyѦÍ
Ó©ER
@s¹{§É¨¢ÄAs¬ºvæð¦c·éÛÍAK¸_ÑåÆ«åÆ̯¦cðs¤±àÌƵľ³¢B]A¹bÌßlÆíQh̪ÙÈéꪽA»ê¼êªÆ©ÉÎôðÆé½ßÉIÈÛìǪ¢ïŵ½BÖWÌAgÍå¢ÉißÄ¢½¾«AíQhA¶§nÇAÂ̲®ÌRÂðÜÆß½¹bÌIÛìÇðÀ»µÄ¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
YÓP.16
ê@íQh~{ôÌÀ{ÉÖ·éî{IÈ
10 Áè¹bÛìÇvæÌì¬ÍÏX
Ó©ER
@s¬ºvæðLæIÉôè·éÉ ½èAs¹{§xÅÌÁèvæªÈ¢êÉÍA¬â©ÉÁèvæªôè³êéæ¤ÉµÄ¾³¢BLæIvæÍA{ÈçÎs¹{§ªÀ{·é׫±ÆÅ èAs¬ºvæƯÉvæôèðs¤Kvª èÜ·B
YÓP.17
ñ@íQh~væÉÖ·é
Ó©ER
@væôèÌ豫̧¾«ðmÛ·é½ßÉAȺÌð¾LµÄ¾³¢B
Es¹{§ÍALæIÈíQª¶µ¡Ìs¬ºÉæ餯væªKvÈêÉÍAÂyI¬â©ÉÁè¹bÛìÇvæðôè·éæ¤ÉÂÆßé±ÆB
EíQh~væÌôèɽèAYnæÌÐïIoÏIvöâ¹b̶ÔÉÚµ¢êåÆAnæZ¯A©RÛìNGOÌÓ©ð·±ÆB
EíQh~væÌôèÉ ½èAÇ̪ÇÌæ¤ÈoßðoÄôèµ½©Ac^ðöJ·éAÓuèßöð¾ç©É·é±ÆB
YÓP.20
ñ@íQh~væÉÖ·é
R@íQh~væÉèßé
iSjÎÛ¹bÌßlÉÖ·é
Ó©ER
EÎÛ¹bÌßļ
ußlÂÍA´¥ÆµÄíQhÎôÉæÁÄàíQªh~Å«È¢ÆFßçêéÆ«És¤àÌÆ·évi¹bÛìÆAî{wjAÆvæLÚj±Æð¾LµÄ¾³¢B±êÍAâÝàÈìÍAJ½µÄøðt³¸AêÉæÁÄÍíQðgU³¹é¨»êà é±ÆA¨æÑnæZ¯ÌÀS«ÌmÛÌÏ_ÉæéàÌÅ·B
@ܽAÎÛ¹bÈO̹bÌLQìð í¹ÄÀ{·éêÉÍAÎÛ¹bßlàõÆLQ¹bßlàƪ¬¯³êÈ¢æ¤ÉA]ÒÌW¯ðgÌɯAæÊð¾mÉ·é±ÆƵľ³¢B
Ó©ERP.21
¯
EÎÛ¹bÌßlvæ
@{ÌßlvæÉ¢ÄÍAKvLÚð¾Lµ½®ð쬵A»±ÉȺÌðLÚµA¹bÛìÆvæÆÌ®«ðmÛ·éàÌƵľ³¢B
EëÂÆÌÖWÉ¢ÄFÎÛ¹bÌßlvæÍAëÂÉæéßlÆd¡µÈ¢æ¤É·é±ÆAßlÍAëÂÉæéßlðÜßÄvæð§Äé±ÆB
EßlúÔÌÝèFúÔÍAÂúðOµA´¥ÆµÄíQª¶¶Ä¢éṳ́¿AÅàøÊIÉßlªÀ{Å«AnæÌÀîɶ½ßlð³È®·é½ßÉKv©ÂKØÈúÔÆ·é±ÆB
EßlÌãÀFnæÂÌQÌÛS̽ßÉAvæúÔàÅßlÂ\ÈÌãÀðݯé±ÆB
EíÈÌËÝÂÌãÀFíÈÌËÝÂÍAêúÉ©ñèÅ«éÂÉÀè·é±ÆB
EíÈðËݵ½êÍAK¸ÅáÅàPúÉPñÈãÌ©ñèðs¤±ÆB
EëÁÄÎÛ¹bÈO̹bªßl³ê½êÍA¬â©Éú¹b·é±ÆB
Eöëßl³ê½¹bÉ¢ÄàAíiÂ\Å êΫÊAqEålÌÊjAßln_AßlóµÉ¢ÄL^ðµÄ¨±ÆB
Ó©ERP.21
¯
EÂ ÀÏC
@s¹{§mÍA ÀÏCɯӵȢêƵÄAYnæɹbÌLæIÈÛìÌKv«âAó«ª èAÂ̪µ¸µÄ¢éíª¶§µÄ¢é±ÆðAOɾç©ÉµÄ¨±ÆƵľ³¢B±Ì[uÍAÁÉN}âTÉ¢ÄKvÅ·B
@s¹{§ÍAs¬ºvæɨ¢Ä ÀÏCª éêÉÍARcïÈÇêåÆÌÓ©ð·ÆÆàÉAö®ïÅêÊ©çàÓ©ð®æ·é±ÆƵľ³¢B
YÓP.22
iUjíQh~{ôÌÀ{̧ÉÖ·é
@EíQÎôÀ{àÉÖ·é
Ó©ER
@íQÎôÀ{àðÝu·éêÉÍAàõÌvÉ¢ľLµÄ¾³¢Bá¦ÎAàõÉÈéÆëÂÅ̸ƪȳê½èCte̪eÕÉÈé±Æ©çA±êð¾½¢ª½ßÉüà·éÒª»êÈ¢ÆàÀèܹñB@¥ð
çµAÀnÌo±ªLxÅAnæɨ¢ÄàM]Ì él¨ðIC·éæ¤ÉµÄ¾³¢BܽA§Ââá@ßlðs¢AßÉâíê½ÒÍàõÆÈé±ÆªÅ«È¢±Æð¾LµÄ¾³¢B
@³çÉAàõÌÉÍA춹b̶ÔyÑ»nÌnÉÚµ¢m¯Æo±ðL·éÒªK¸ÜÜêĢȯêÎÈçÈ¢±ÆƵľ³¢B
@±êçÍAKØÅøÊIÈßlyÑnæZ¯ÌÀS«ÌmÛ̽ßÉKvÈðÅ·B
YÓP.24
iVjßlµ½ÎÛ¹bÌÉÖ·é
Ó©ER
@ßlµ½¹bÉNö·é´õǪ¶µÈ¢æ¤Éæèµ¢ãÌÓâq¶ãÌÎôAyÑ궵½êÌA̧ð¾LµÄ¾³¢BëÂɨ¯ép©ç¶µ½aÍÂlÓCÅ·ªAs¬ºÌÂÉæé÷pÌêÍA̪¶µ½êÍ©¡ÌÌÓCªâíêÜ·B
@ßlµ½ÂÌÌwp¤ÉpÍ ÜÅA¹bÌÛìÇÉ·é¤ÉÀè³êÄ¢é±Æð¾LµA¤ÆpâÀ±pÖ̬pÍFßçêÈ¢±Æð¾LµÄ¾³¢B
@ßlµ½ÂÌðEª·éêÍAÂ\ÈÀè¬â©ÉêÉÌÈ¢û@ðæé±Æð¾LµÄ¾³¢BßlÌ»êÅÍAµÎµÎìAoEAMÆ¢Á½ñl¹IÈEªªsíêĨèAêÊÉßlª«´ðø©êéRÌêÂÆÈÁĢܷBÁÉíÈÉæéßlÌêÍAeÉæéu¯ß³µvªÅ«È¢½ßAßlBÉúu·éÆ¢¤áª©çêÜ·BbãtÉ˵AÀyEuð·éKv«É¢Äà¾LµÄ¾³¢B
YÓP.24
S@íQh~væÌÀ{óµÌñ
Ó©ER
@ßlÉÖ·é³mÈñÍA¹bÌÛìÇÌ{ôð§ÄéÛÉÅàdvÈf[^Å·ªA]ÍA±êª«¿ñÆsíêĨç¸Avɳµ½f³êĢȩÁ½«ç¢ª èÜ·Bs¬ºvæɨ¢ÄÍà¿ëṉ̃ÆAvæªÈ¢êÅàAßl̬â©Å³mÈñÍAºÐÆà§ãµÄ¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
YÓP.25
O@¯ÌðÆÖSÌi
Ó©ER
@춹b̤ͯLàYÅ èA»ÌÛìÇÉ¢ÄÍö¤IÈÆƵÄÊuïçêöïªü³êé±ÆÉÈèܵ½B[ÅÒâÁïÒª»Ìïpª³Å é©Ç¤©ð»f·é½ßÉàAíÉîñöJðs¢ALÖSðàÂlXÌQÁƦÍð£µÄ¢×«Å éÆl¦Ü·B
@춹bÍA_Ñ
YÆÉ«e¿ðyڷΩè̶ÝÅÍÈA¶Ônð\¬·éêõƵĻ̶ݩÌÉ©¯ª¦ÌÈ¢¿lª èÜ·B춹bÍA©RÌÉo©¯ìRÈÇðUô·é½ÌlXÉÆÁÄyµÝâìÑÌÎÛÅ èAÔ¹ð¤Åéú{Ì`IA¶»IàYÅà èÜ·B
@±Ìæ¤Èwi©çA¹bíQÎôɨ¢ÄÍAÀÕÈìÌÝÉé±ÆÈAíÉIÈÏ_ÅíQhÎôðSÉæègÞ׫±ÆðA{wjÌ´¥ÆµÄ¾LµÄ¢½¾«½¢Æv¢Ü·B
Èã




![]() @ALIVEÌÐî@
@ALIVEÌÐî@![]() @춮¨@
@춮¨@![]() @Y[¥`FbN@
@Y[¥`FbN@![]() @Æ뮨@
@Æ뮨@![]() @{Y®¨
@{Y®¨
![]() ®¨À±
®¨À±
![]() ¶½Ï
¶½Ï
![]() CtX^C
CtX^C
![]() ®¨Ûì@
®¨Ûì@![]()
![]() @¿W@
@¿W@ ![]() @rfI@
@rfI@ ![]() @ïñuALIVEv@
@ïñuALIVEv@![]() @æèµ¢}@
@æèµ¢}@![]() @Ql}Ðî@
@Ql}Ðî@![]() @N@
@N@![]() @¨â¢í¹@
@¨â¢í¹@![]() @¿¿
@¿¿