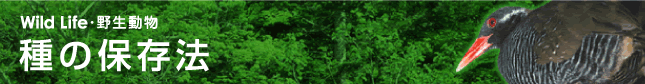①
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
(1)登録票等の管理方法の改善
<意見内容>
*鳥類において、登録票等希少種の管理については、種の保存法施行令別表第1、および別表第2の表1に掲げる種についても対象とするべきである。
<理由>
現行法において、登録票が必要とされているのは、国際希少種のうち、ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(別表第2の表2)であり、二カ国間渡り鳥保護条約/協定(日中・日米・日露・日豪)に基づく種(亜種)(別表第2の表1)、また国内希少種(別表第1)については登録票は存在しない。しかし、実際には、傷病等で保護された個体のうち野生に返せない希少種の鳥等が、一般公募のボランティア等に預託・飼養されるケースもある。中には、自治体が預託した傷病鳥の追跡調査を行わないことが多いために、希少種のオオタカ等を「放鳥できない傷病鳥」と偽って、鷹狩りのイベントに連れてきているという通報もある。また、登録票等がないことを悪用し、「傷病鳥で保護した個体」と偽り、密猟が疑われる個体を飼養していることもある。希少種の飼養個体については、すべて登録等を義務化するべきと考える。
②
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
(1)登録票等の管理方法の改善
<意見内容>
*登録票については、譲渡時を考慮するのではなく、すべての希少種飼養個体について義務付けるべきである。また、定期的な更新制度を設けることとする。
<理由>
現行法においては、対象種の売買やそれを目的とした陳列について、登録票の予めの交付を受けること、登録票をともにすることが義務付けられているが、終生飼養する場合には登録票は必ずしも必要ではない。しかし、実際には、室内飼育が主である希少種(特に爬虫類や鳥類等)については、不正な手段で入手した個体であってもその違法性が露見することが少ないために、登録票がないまま秘密裏に譲渡が行われていることもある。また、動物取扱業者において、登録票のみが店に残り、当該個体のみが売買されていることもある。これは、密輸した個体に登録票を使いまわしする目的で行われる。さらに、死亡時の登録票の返還率が著しく低いことも問題である。死亡した個体の登録票が、売買されることもある。登録票については、定期的に更新を図ることが必要であると考える。申請時に幼齢である個体の場合、時間の経過に伴い、申請時の体長や特徴、添付写真の外貌と大きく変わることがあるため、3~5年での更新を行うべきである。
③
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
(1)登録票等の管理方法の改善
<意見内容>
*登録個体については、種に応じた個体識別措置を徹底して行うべきである。
<理由>
動物愛護管理法において、特定動物(旧・危険動物)については、マイクロチップ等の個体識別措置を行うことが努力義務となっている。希少種の飼養個体についても、前述したような不正防止のために、種に応じた個体識別措置を行うべきと考える。マイクロチップについては、
種によっては挿入した後の健康不良が一部問題になっているため、個体の健康を損ねず福祉に配慮した識別措置を行うことが必要である。
足環の装着等のほか、猛禽等ではDNA登録(採血)等も検討するべきである。
④
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
*希少種(亜種)の交雑種については、現行法における登録に準じる制度を設け、規制するべきである。
<理由>
現在、猛禽の中でも、ハヤブサ科の種・亜種間交雑種が問題となっている。(ハイブリッドファルコン、トライブリッドファルコン等) 希少種であるシロハヤブサのハイブリッド(シロハヤブサ×セイカー、シロハヤブサ×ラナー等)、希少種同士のハイブリッド(シロハヤブサ×ハヤブサ)等もある。動物取扱業者の中でも、人工授精で国内でハイブリッドを作り出している者もいる。これらは、種の保存法の本来の意味・目的を蹂躙するような、環境犯罪行為であるとも言える。希少種の交雑個体についても、規制の対象とし、同時に、遺伝子をいたずらに撹乱するような行為をやめさせるよう措置を講じるべきと考える。
⑤
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
*ワシントン条約附属書Ⅱ掲載種について、流通規制を設けるべきである。
<理由>
猛禽については、種の保存法の対象種以外のほとんどの種がワシントン条約附属書Ⅱ掲載種であるが、国内への輸入数は依然として多い。繁殖個体(CB)だけでなく、多くが野生由来(WC)である。しかし、原産国でそれらの種について精度が高い生息調査が行われているかどうかは不明であり、日本が輸入することにより他国の生態系を破壊し、種を絶滅に追いやることになりかねない。附属書Ⅱだからよい、という動物取扱業者や飼養希望者の認識を変えさせるために、附属書Ⅱ掲載種についても、種の保存法において規制を設けることが、一般への啓蒙にもなりうると考える。
⑥
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
*都道府県に種の保存法の所轄部署を設置し、警察と常時連携を保てる体制づくりが必要と考える。
<理由>
種の保存法については、現在環境省が直接所轄となっており、地方行政に窓口がないために動物愛護法、鳥獣保護法に関する通報時対応と比較すると行政機関・警察との迅速な連携がとりにくいという難点がある。
動物愛護法では、特定動物飼養施設の登録は、都道府県の生活衛生課(法的には都道府県の知事宛)に申請を行うことが定められているが、これにより行政が立入検査や指導を行うことができる仕組みになっている。種の保存法についても、希少種の不正な飼養や流通を防止し、違法事実の発見につなげるためにも地方自治体が同法に関与できる体制構築を目指すべきである。
⑦
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
改正動物愛護法(第12条の6)により、種の保存法等の関連法規に違反した動物取扱業者については登録の取り消しが可能となる方向ではあるが、不正に国内流通している個体を発見しやすくするためにも、地方動物行政においては同法を視野に入れた指導監督業務の履行(抜き打ちの検査、取引実施状況台帳等の記載義務徹底等による業者側の社会規範、法令遵守への意識高揚)が望まれる。
上記の実施にあたっては、過去に摘発された業者の多くは犬猫以外の販売業者であった事実に鑑み、環境省所轄部署に対し、犬猫以外の業者における個体管理の杜撰さ、行政による指導の甘さを指摘し、政省令等による規制強化の必要性について継続的な要請を行う必要がある。
<理由>
ワシントン条約で絶滅危惧種に指定され、 平成19年9月から原則として譲渡が禁止されているピグミースローロリスを販売したとしてペットショップ経営していた指定暴力団幹部が逮捕された事件では、絶滅危惧種の違法取引が暴力団資金源になっていた可能性があるとの報道がなされていたが、摘発されたのは氷山の一角にすぎないと思われる。
希少な動植物を生息地から持ち去り個体数を減らすことは大きな問題ではあるが、違法に持ち込まれた個体を反社会組織の資金源に供される現状も許されるべきではなく、ひとつでも多くの違法取引を発見するためには、自治体による動物取扱業者への抜き打ちによる立ち入り調査(店頭のみならずバックヤードなど)が不可欠であり、取引実施状況台帳等の記載義務徹底等による業者側の社会規範、法令遵守への意識を高めることも必要と考える。
⑧
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
*違法押収個体の把握・追跡調査を徹底し、個体の福祉を図るべきである。
<理由>
種の保存法に違反して没収・押収された生体が、どこでどのように飼養されているのかを、把握・追跡できるような仕組みづくりが必要であると思われる。希少種の場合、原産国に返還されずに動物園などの展示施設のバックヤードでの飼養となるケースが多いが、飼育員等の不足により、十分なケアが行き届かないこともある。没収された個体の福祉のためにも、飼育体制等の抜本的な見直しが必要である。
⑨
<該当箇所>
1・希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置
(2)罰則の強化
<意見内容>
*違反を犯した者については、懲役・罰金等罰則の強化だけではなく、没収された生体の飼養に係る費用あるいは原産国への返還費用、野生復帰に係る費用等を負担させるべきである。
<理由>
改正動物愛護法において、関連法規(種の保存法等)に違反した動物取扱業者については、登録の取り消し等の措置がとられる方向である。しかし、種の保存法違反は、動物取扱業者のみではなく、一般の個人(購入者・飼養者)も含まれることから、さらに罰則を強化し、また没収された個体について、飼育・返還に伴う一切の費用を負担させることが必要と考える。
⑩
<該当箇所>
2・わが国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
*レッドリストの評価対象種に、海洋哺乳類も含まれるよう早期に検討されるべきである。
<理由>
現在のレッドリストの評価対象種の基本的条件のなかで、哺乳類において、ジュゴンを除く純海産種は対象外とされている。しかし、海洋哺乳類は、海の生態系保全の中で要となる重要な存在であることに鑑み、陸棲哺乳類同様、平等に本来の生息域における種の存続が図られるべきである。
⑪
<該当箇所>
2・わが国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関して講ずべき必要な措置
<意見内容>
*レッドリスト見直しの際には、関心のある全国の市民団体や個人、学識者等の声を反映することができる仕組みづくりが必要である。
<理由>
環境省第四次レッドリストは、平成24年8月末に公表されたが、それまでの検討会の経緯や議論内容等については明らかにされていないため、公表の前に、パブリックコメント等を募集し、国民も意見を言うことができる場を設けるべきと考える。(※第四次レッドリストでは、準絶滅危惧種(NT)であったヤマネがランク外になっているが、長年にわたり全く調査を行っていない自治体も多いことから、公表後に見直しの基準等について疑問視する声も多く挙がっている。)
⑫
<該当箇所>
その他
<意見内容>
*「学術目的」という名目で希少種の輸入が行われることについて、監視を強化するべきである。担当部署に野生動植物の専門家を配置し、書類審査段階でも専門家やNGO等の協力を得て内容をチェックする仕組みを設ける等、事前の監視体制を徹底すると共に、輸入後の追跡調査も行うべきである。
<理由>
ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種の野生個体は、学術研究目的であれば輸入が可能となっている。日本では、動物園が学術目的で希少種の輸入を申請することがあるが、実際には別の目的で飼養されていることも多い。2001年には、野生生息数(当時)が170羽しか確認されていないスミレコンゴウインコが学術研究目的と称して不正輸入し、後に転売したことが判明し関連者が逮捕されているが、実際に申請に名前を使われたのは、三重県内の非常に劣悪な環境にある動物園であった。日本では、動物園を名乗る施設に基準もライセンス制度も設けていないために、動物園を自称すれば通用するのが現状である。また、アジアゾウについても、展示や娯楽(ショー等)の目的で飼養するものであっても学術研究目的と称して野生個体を輸入申請した事例が複数残っている。これらのアジアゾウについて、個体の福祉や環境エンリッチメントが図られず、習性を無視した飼養方法がとられていることも問題である。輸入後、どのような施設で飼養されているのか、追跡調査を行う体制づくりを構築すると共に、学術研究目的で輸入申請をした飼養施設には定期的な研究報告等を行うことを義務付けることも検討されるべきである。
以上
 野生生物保護法の制定をめざすネットワーク
野生生物保護法の制定をめざすネットワーク
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求