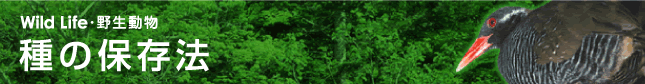「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)は、1993年に、生物多様性条約の批准を機に制定されました。
この法律は、大きく2つの目的をもっています。
一つは、国内の希少野生動植物の種を、その生息地を指定して保全することです。
もうひとつは、絶滅のおそれのある野生動植物の商取引に関する国際条約(ワシントン条約)にもとづいて、野生動植物の輸出入を規制することです。
種の保存法は、今年(2003年)で制定後満10年となります。この間、国(環境省)および都道府県版のレッドデータブック(絶滅のおそれのある種を記載したリスト)では、絶滅のおそれのある種は急増しています。
それにもかかわらず、種の指定が遅々として進まず、法の実効性がないために、何ら打つ手が状態になっています。
また、海外からの稀少な野生動物の密輸はあとをたたず、密輸が発覚しても処罰が甘いために、抑止力がありません。
制定後、これほどのザル法であることが明らかになってしまった今、抜本的な法改正が必要な時にきているのです。
まず、直ちに着手しなければならないことをあげてみます。
1、国内希少種の指定を増やす
国内希少種の種の指定の数があまりに少なすぎます。現在、絶滅のおそれがある種を記載した国の「レッドデータブック」(RDB)には、なんと2239種もがあげられています。
ところが、このうち、種の保存法によって国内希少野生動植物種として指定されている種は全部で62種、わずか2.7パーセントに過ぎないのです。
哺乳類に至ってては、ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコの2種のみです。
種の絶滅は、生物多様性の保全の上で最も危機的な状況をさしており、国は緊急に科学委員会を設け、RDB記載種を順次指定種に含めていくべきと考えます。
2、地域個体群を対象に含める
西日本のツキノワグマ、東日本のニホンザルのように、小さな個体群が孤立した状態になっていて、地域によっては絶滅寸前の状態にある種がたくさんあります。それにもかかわらず、未だにツキノワグマは狩猟獣のままですし、ニホンザルは無制限に有害獣駆除の対象となっています。
種の絶滅は、一気に全滅するのではなく、地域の群れが先細り、小さな群れとして孤立することから始まります。いったん、そのような状態になってしまうと、種内の遺伝的な多様性が失われ、絶滅から免れることはたいへん難しくなってしまいます。
法律の中に、孤立した地域個体群を保護するという規定を導入する必要があります。
3、生息環境の回復計画を設ける
しばしば、野生で絶滅しても、動物園などで飼育繁殖させればいいのではないかという言い方がなされます。
確かに、「生きた標本」としてはある程度保存できたとしても、その動物がもつ行動学的な表現形態や、親から子に伝達すべき経験の体系は、まったく切断されてしまうのです。
また、動物園や植物園の中での繁殖は、生態系の保全や生物多様性の確保にはつながりません。
何よりも、絶滅のおそれのある種の生息環境の調査および繁殖を阻害している要因を解明し、回復計画を立てる必要があるでしょう。
4、国際希少種の密輸入の阻止
1999年におこったオランウータンの赤ちゃんの密輸事件では、7頭が密輸計画のえじきとされ、3頭が途中で死んでいます。2頭は麻酔をかけてジャケットの下に隠して機内持ち込みされ、2頭は箱詰めにされて「ふつうのサル」として手荷物ではこばれたと言います。
これを取り締まるべき税関での監視、および「種の保存法」には、以下のような抜け穴と限界があります。
(1)違法取引を摘発した際、動物を没収できない。
(2)生きた個体が任意放棄された場合、国の保護収容施設がない。
(3)生きた個体の原産国への返送規定が適用された例がない。
(4)ワシントン条約付属書IIの種に対しては何の規制もない。
この対策としては、ニュージーランドのように「密輸探知犬」をおくことも有効かもしれません。
また、密輸犯人に対しては、不法に持ち込もうとした動物の購入先、仕入れ先まで自らの費用で返還させる規定を設けるべきでしょう。もし、それができないというのであれば、国内で一生その動物を飼育するためにかかる費用は、全額犯人負担とするべきです。
5、生きた個体の保護施設を設ける
税関で密輸を摘発しても、任意放棄された動物を保護する施設がありません。希少動物を保護する施設がないためにく空しく死なせるのでは、「種の保存」の目的に反してしまいます。
犯人のよって任意放棄された動物は「国有財産」となるのですから、本来ならば国が保護シェルターを設けて、そこに収容すべきではないでしょうか。動物は、現地で密猟され、日本まで密輸されてくる途中、長時間、餌や水も満足にあたえられないまま、劣悪な取り扱いを受けて、輸送されてきています。
ストレスによって免疫力もおとろえ、わけのわからない病気にかかっているおそれもあります。適切なケアを施し、原産国(地域)または適切な飼育施設に収容されるまでの期間、リハビリのできる施設を設ける必要があるでしょう。
日本世界最大の野生動物消費大国でもあります。日本人の欲望の犠牲とされている野生動物を保護すること、かれらをその生息地から引き離し、現地の生態系、生物多様性をも破壊している行為に対して処罰することは、国の責任ではないでしょうか。




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求