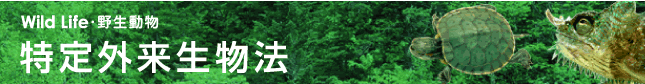2003年11月5日
記者会見資料
移入種対策に関する措置の在り方について(中間報告)
パブリックコメントに対する意見
(財)日本自然保護協会・(財)世界自然保護基金・(財)日本野鳥の会・地球生物会議(ALIVE)は、各団体で上記に関する意見を、本日、環境省自然環境局野生生物課に提出しました。各団体の提出した意見の集約の概要は下記のとおりです。
■主な意見・論点
1.法制化に向けた課題は多く、実効性がある外来種対策法がはたしてできるか
関連法案の改正・調整がなければ、ザル法になってしまう
1-1)外来種に関する制度、法令は多岐に渡り、生物多様性の視点がないものが多い。これらの法令・制度との整合性を図るために改正が必要であり特に飼育・流通に関して動物愛護法、国内移動種に関して自然公園法など関連法を強化しなければ、外来種対策の実行性は担保できない。
1-2)国及び地方公共団体の役割分担が不明確であるうえ、予算的措置も検討されていない。水際対策や所持・飼育規制、被害対策・防除などは、環境省だけで対処しきれず、実効性を担保するには関係省庁や地方自治体との連携が必要である。
1-3)世界貿易機関(WTO)との関係について留意するとあるが、相手国が規制緩和を求めてきたとしても、我が国の生物多様性に影響を脅かす種であるならば輸入を認めない姿勢が必要である。
2.問題の要となる外来種の水際対策
2-1)予防原則にもとづき、税関等における水際規制、動物輸入業者の規制などを徹底するため植物貿易法、家畜伝染予防法等の関連法制度の改正を行うべきである。
2-2)すべての生物種の輸入を届け出制とし実態を把握するとともに、動物取扱業者を免許
制にし、悪影響を及ぼす種や絶滅の恐れのある種を輸入し販売した業者は、罰則を課すだけでなく、免許を取り消すなど厳しい措置をとるようにすべきである。
2-4)「悪影響を及ぼすと判断された種(ブラック種)」については、「環境検疫」という視点から関連法を抜本的に改正し、輸入禁止とすべきである。「悪影響を及ぼすおそれのある種(グレー種)」についても、科学的な事前評価によって「悪影響を及ぼすことがない種(ホワイト種)」と判断されるまで、輸入を認めるべきではない。ホワイト種についても、マイクロチップ、ICタグなどの方法で個体識別と飼育者の把握ができるようにすべきである。
2-6)動物取扱業者を通さない個人輸入の規制または税関・検疫における水際規制を強化するため、本法律でブラック種と判断された種の個人輸入、国内持ち込みなどの「生態犯罪」に対して、厳しい罰則を課すことができるよう、関連する法律を改正すべきである。また税関・検疫において、野生生物の専門官(環境検疫官)および訓練された外来種対策犬の配置を急ぐべきである。
2-7)非意図的導入について、具体的な対応策を明記されていない。
2-8)「生物多様性への影響評価の実施」(リスク評価・分析)は、非常に重要なしくみであり、その方策が具体的に記述されていない。対象となる外来種の範囲についての判定にあたっては、対象となる種が多岐に渡るため、専門家の個人の意見だけでなく自然保護NGOや学会等組織的に広範囲の意見を集約し反映できるしくみが必要である。
3.導入された外来種の被害対策・防除について
3-1)導入された外来種の防除実施計画は、その対象地域、対象種の設定、目標、実施体制、モニタリング体制など、どのような基準と体制で設定するのか明確になっていない。
3-2)防除の実施は、国レベルのみならず、地方公共団体レベルの場合も多くなると考えられるが、その場合でも科学性、透明性、説明責任、合意形成は、必要条件となる。実施主体が、どのレベルであっても、これらの条件が担保できるように、関係する主体が参加した協議会を検討し、法律の条文の中に織り込むべきである。
■その他の課題
1.現状と問題の整理が不十分
1-1)生態学的用語の使用方法が曖昧であったり、不適切であったりするため、誤解を招きやすい内容である。過去の議論や専門家の知見を取り入れ、修文すべきである。
2.亜種や地域個体群の導入の問題
2-1)交雑が容易に起こる亜種や地域個体群の導入の問題は大きく、その事例を明記し、現在分布の確認されている在来種についても、分布域外に持ち出さないことを明記すべきである。
3.重要管理地域について具体的な方策が書かれていない
3-1)外来種対策法において、生物多様性保全上重要な地域の指定を行うことができるようにするとともに、特定の外来侵入種(国内移動を含む)の持ち込み、ペットの放し飼い・持ち込みなどを禁止する措置がとれるよう法改正を行うべきである。
3-2)地域住民や利害関係者が参加する協議会方式により「生物多様性保全計画」を作り、定めることができるしくみが必要である。
4.外来種情報収集は他省庁、市民の連携が不可欠
外来種に関するモニタリング体制を作るために、現情報の集約、情報発信できるシステムを早急に構築し、広く一般に情報提供することが必要である。また、IUCN ISSG(IUCN
Invasive Species Specialist Group)の他、河川水辺の調査など他省庁の生物相調査などや、市民活動との連携も必要である。
<参照>
日本自然保護協会(NACS-J)の外来種意見書のページ
http://www.nacsj.or.jp/old_database/inyudobutu/inyudobutu-031105-iken.html
世界自然保護基金日本委員会(WWFジャパン)の意見書のページ
http://www.wwf.or.jp/wildlife/index.htm




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求