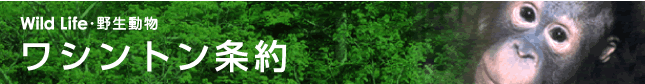■ なぜ密猟が起こるか
Q:ケニアではゾウの保護政策が効果をあげ、ゾウの個体数が増加しているとの記事を読みましたが、これは本当でしょうか(2008年2月3日 AP通信)。
A:確かに増えているといえますが、これは過去20年間の保護政策が効を奏したものです。ケニアでは1970年代には国立公園だけで4万頭、全土で約10万頭のゾウが生息していました。当時は象牙の取引が盛んに行われ、政府は乱獲を防ぐために1979年にゾウの狩猟を禁止しました。しかし密猟がたいへん多く、政府は1989年に野生生物局(KWS)を設け、象牙の商取引を禁止したのです。この当時、ゾウは全国で約1万2000頭にまで減少していました。
この20年間のゾウの保護政策により、ようやく現在2万7000頭まで増えました。しかし、これは増加というよりは回復というのが正しいでしょう。
Q:ケニアでは依然として密猟が存在し、レンジャーも生命の危機にさらされているとのことですが、密猟はそれほどもうかるものでしょうか?
A:密猟者にはそれほど多額のお金が懐に入るわけではありません。密猟者が象牙を1キロ20ドルで売っていても、最終業者のところでは1キロ800ドルになっています。その間のお金のほとんどは仲買人(ディーラー)の懐に入ります。
Q:密猟者は象牙を仲買人に売り、その仲買人を通じて日本の消費者に届くということですが、この仲買人とはどういう人々でしょうか。
A:国際的な組織です。販売ルートは組織的な犯罪者のネットワークで、銃、麻薬などといっしょに取引されています。
Q:ケニアで密輸が発覚した場合、罰則はどの程度でしょうか。
A:ケニアの法律では象牙の密輸は3年の実刑か300ドルの罰金です。密輸をする仲買人にとっては象牙で得る利益に比べれば、300ドルなどたいしたお金ではありません。従って大多数の者は罰金を支払い、実刑を受ける者はほとんどいません。また、密猟者のほうは、生きるためにせっぱつまって違法行為をすることが多いのです。
Q:もっと罰則を重くすれば、再発を防げるのではないでしょうか?
A:中国では絶滅危惧種のパンダなどを密猟、密売すると極刑が科せられますが、それでも違法行為を根絶できません。刑を重くしても密猟、密輸を根絶できない理由は、どんなに罪を重くしてもそれを上回る利益を得られるマーケットが存在するからです。密猟、密輸をなくするためにはこのようなマーケットを閉鎖するしかありません。
Q:マーケットを閉鎖するにはどうしたらよいとお考えですか。
A:象牙の90%は、ハンコ(印鑑)に加工されます。そしてそのハンコの大消費地は日本です。ハンコの需要がある限り、たとえ違法行為であっても供給は続けられます。ハンコがどうしても必要であるならば、日本人は象牙に代わるもの(代替品)を選ぶようにしてほしい。また、日本政府は、ワシントン条約(CITES)会議で、象牙を買いたいと要求しないでほしいと思います。
Q:日本政府が象牙をほしがっているというよりは、象牙組合などの業者団体が政府に圧力をかけているように思うのですが。
A:CITESの会議は政府の会議であり、発言し意思決定するのは政府です。ゾウが住むアフリカの国々は、象牙の取引で得られる利益はほとんどありません。日本政府が要求するので、供給体制が作られるのです。
Q:私たち日本人がそのことをほとんど知らないのが問題のようです。
 ■
「有効利用」論について
■
「有効利用」論について
Q:日本では、近頃、野生動物が農作物被害を起こすとして「有害駆除」しろという圧力が高まっています。ゾウが農作物を荒らすなどして駆除されることはないでしょうか。
A:住民を襲うなどして生命の危険があるときには、ケニア野生動物局(KWS)に報告がなされ、政府の許可で殺すこともありますが、それは年間10頭くらいです。その地域にいると危険である場合には、群れを移動させることもあります。
Q:殺したあと、肉や象牙を利用することはありますか。
A:政府の許可で肉は食料として配布され、象牙は政府の倉庫に保管されます。
Q:その象牙を売って「有効利用」したらよいという意見はありませんか?
A:象牙を売るというのは馬鹿げています。「有効利用」は、もっとゾウを殺すという事態を招きます。
Q:適正に管理すればよいという人(資源管理派の研究者たち)もいますが。
A:私のように現場でレンジャーとして働いてきた者からみると、理論だけの人とは大きなギャップを感じます。適正な管理は、理論的には可能かもしれませんが、そういう主張はこの世の中から犯罪者がいなくなってから言ってほしいものです。事実、2005年から2006年の間に、約26トンの密輸の象牙が押収されています。これは約2万頭のゾウが殺されたということになるのです。
Q:ワシントン条約会議では、適正な管理が可能であるとして、2000年に1回限りということで日本に、2008年に1回限りということで中国に、アフリカの3、4カ国から合法的に象牙の輸出が認められました。ワシントン条約当局は、科学的根拠に基づいて合理的な判断をしているといえるでしょうか。
A:私もワシントン条約会議には毎年参加していますが、科学的根拠に基づくというよりは政治的ゲームになっているように思います。日本や中国への輸出には、IFAWを含め多くの団体が、両国では適切な管理が行われていないという証拠を出して反対しましたが、取引が認められてしまいました。政府やワシントン条約当局は、商業的取引を行う人々に影響を受けています。やはり一般の人々が現実を知り、象牙を使わないようにしてもらう必要があります。
象牙を売っても儲かるのは犯罪的な仲買人だけで、現地の人々に還元されるものではありません。ほんとうにアフリカの現地の人々に利益がいくようにするのは、エコツーリズムなどの観光産業のほうでしょう。
Q: ケニアには、野生動物保護官(レンジャー)は何人いますか。その人々の社会的な地位はどんなものでしょうか。
A:2006年当時ではレンジャーは約2800人おり、実際の現場に約2000人が働いています。レンジャーになるためには大学で教育を受けることが必須で、社会からの尊敬を受ける職業の一つです。よく知られた職業であり、とても人気があります。
<講演会>
「ゾウについて知ろう」マイケル・ワミチさん講演の要旨
(写真)植松明香、アンセボリ国立公園で撮影




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求