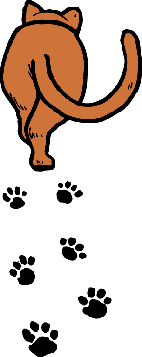 2006年に「遺失物法」の改正が行われ、所有者が不明の犬とねこは、警察では受理せず、行政に引き渡されることになる予定です。
2006年に「遺失物法」の改正が行われ、所有者が不明の犬とねこは、警察では受理せず、行政に引き渡されることになる予定です。
迷子のようにみえる犬や猫、ペットをみつけたとき、私たちは、どうしたらその動物を助けてやることができるのでしょうか?
環境大臣 殿
警察庁長官 殿
この度、遺失物法が改正され、拾得物としての犬とねこについては、改正動物愛護法35条を準用し自治体の動物行政で取り扱うようにするとのことです。この場合の一番の問題は、警察がその動物を迷子(遺失物)か遺棄(犯罪)かの判断に迷うことです。
その対処を明確にしておかないと、本来の飼い主の元に返還されなくなったり、犬猫の殺処分が増えたりするようになるおそれがあります。国民の多くが犬ねこを迷子として警察へ届けているのは、「飼い主の元へ戻してやりたい」という思いからきていることをお汲みいただき、動物愛護の精神にかなう対処をしていただくように要望いたします。
1.明らかに飼い主がいるとみなされる犬とねこについて
警察に犬とやねこが届けられた場合、その動物が迷子か遺棄か判断がつきかねるケースがほとんどです。何らかの理由でその動物が逃げ出したか迷子になったもので遺失物であることが明らかであると見なされる場合は、警察あるいは自治体の専用施設で、遺失物として3カ月保管することとしていただきたい。
これらの動物は人の財産であり基本的に飼い主に返還するべきものです。現在、自治体の条例では所有者不明の犬またはねこと判断された場合は、2日間の公示、3日目の処分としている場合がほとんどですが、飼い主が問い合わせたときには処分された後だったというトラブルがしばしば起こっています。
2.明らかに遺棄であると思われる犬とねこについて
状況からみて明らかに遺棄されたとみなされる場合は、動物愛護法による遺棄罪の証拠物件とみなされます。
大阪府では地元の動物愛護団体の要請を受けて、犬ねこの遺棄を警察が捜査するようになり、犯人が特定されて起訴されたケースも出ています。警察が犯罪と認知して取り組む姿勢を見せることにより、遺棄に対する大きな抑止効果が出ています。(新聞記事参照)
犯人が特定できる場合には、遺棄動物は証拠物件として保管しておく必要があります。
3.迷子か遺棄か判断がつきかねる場合について
犬やねこが数日間野外を放浪しているうちに毛が汚れたりけがをしたりすると、迷子なのか遺棄なのかしばしば区別がつかなくなります。その場合は最低でも2週間は保護し、動物を写真やビデオで撮影し、飼い主からの問い合わせにきちんと応えられるようにしていただきたい(東京都は条例で保護期間を1週間としています)。
大阪府では判断のつきかねる動物は警察署で2週間保管しており、その返還率は70%というたいへん高い数字になっています(別紙資料)。飼い主が必死に探しているにもかかわらず、所有者不明の犬ねことしてわずか3日後に殺処分されてしまうのは、財産権の侵害です。
4.自治体に一時保管用の専用施設の設置を
警察署で保管ができない場合は、役場や福祉施設など地域の公共施設の一角に専用の一時保護施設を設けるよう自治体に助言していただきたい。
例えば大阪府では、64警察署・607交番・46駐在所の計717カ所があり、ここで24時間対応してくれるので、地域住民にとっては利便性があります。一方、多くの自治体では犬やねこの収容施設の数が少なく、動物愛護センターといった集中管理施設が県に1カ所あるのみという自治体も少なくありません。自治体のすべての犬ねこが1カ所の施設に集中する場合、衛生管理上の問題も生じ、また飼い主にとっても探し行く時間や労力が多大なものとなります。地域住民の協力のもと公共施設が活用できるようになることが望まれます。
5.所有者明示の周知徹底を
所有者明示の義務についてよりいっそうの周知徹底に努めていただきたい。
はじめから犬やねこに迷子札や鑑札を付けたり、マイクロチップを装着するなど飼い主を特定できるようにしておけば、迷子や遺棄に対しての対処が容易になります。
6.環境省の迷子動物・譲渡動物の検索サイトの充実を
この4月3日から、環境省はインターネットによる「迷子動物・譲渡動物の検索サイト」を公開しています。取り組みは評価しますが、残念ながらまだ参加している自治体がごくわずかで、内容も充実しているとは言い難い状態です。これに全国の自治体が参画するようすすめていただきたい。
このことにより自治体レベルでの動物愛護行政の向上が促進されることを期待します。
7.自治体の犬ねこの収容施設の改善促進を
これまで自治体の犬ねこの収容施設は殺処分のみを目的としてきたため、人里離れた淋しい場所に隠れるように設けられてきました。一般の人々が容易に訪れることも許されなかったせいで、施設の改善も遅れ、そこで働く職員の労働条件もよいものではありませんでした。今後は、地元の動物愛護関係者の協力や参加を得て一般譲渡を促進するなどし、動物を殺す施設から、生かす施設へと、開かれた施設に転換していくよう助言していただきたい。
以上を、環境省が今回制定する動物愛護管理基本指針において、これを動物愛護行政の拠点の一つとして位置づけるように明記していただきたく、あわせて要望いたします。




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求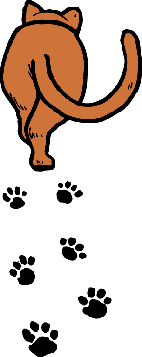 2006年に「遺失物法」の改正が行われ、所有者が不明の犬とねこは、警察では受理せず、行政に引き渡されることになる予定です。
2006年に「遺失物法」の改正が行われ、所有者が不明の犬とねこは、警察では受理せず、行政に引き渡されることになる予定です。