|
|
         |
|
HOME > 会報「ALIVE」 117号
> 2016年2月19日(金)開催 緊急院内集会「幼い犬猫を守る『札幌市の動物愛護条例』を応援する緊急院内集会 ~動物福祉向上のために、この取り組みを全国へ~」 発言録
|
|
|
|
|
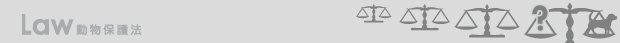
|
| |
 |
【緊急院内集会開催概要】
テーマ:
「幼い犬猫を守る『札幌市の動物愛護条例』を応援する緊急院内集会 ~動物福祉向上のために、この取り組みを全国へ~」
日時:
2016年2月19日(金)18時~19時30分
参加人数:
約140人
賛同団体:
動物との共生を考える連絡会/地球生物会議(ALIVE)/TOKYO ZEROキャンペーン
主催:
幼い犬猫を守る札幌市条例を応援する有志
【登壇者の発言録(発言順、一部抜粋、肩書は当時)】
●浅田美代子さん(女優)
こんにちは、浅田美代子です。今日のこの会は参加者が140名ということで、しかもそれが抽選で決まったということで、やっと日本も、こういう動物の命に対して、皆さんが気持ちを持ってくださってるようになったんだなと、本当に実感しました。
今回、初めての試みを札幌市がしてくださいました。8週齢というのは一番大事で、子犬たちが親と過ごす時間を、最低限8週齢過ごさないと、例えば噛む、吠える、人に懐かない、そういう問題行動を起こす犬がたくさん増えてしまいます。にもかかわらず、母親に教わるべき社会性とか、そういうものが一切なく市場に出され、ペットショップで売られてしまっている子犬たちがほとんどです。ましてやこれまで日本では、35日とか40日ぐらいで出されてきたわけですが、それは本当に離乳の時期に重なるんですね。
離乳の時期に、結局、餌、離乳食とか、そういうのをあげるのがお金が掛かるからという、業者の考え方もあります。もうこれはいけないと思いますし、そういう犬たちを買った人たちが、懐かない、噛む、うるさいということで捨てています。そういうことが、またあの殺処分になったりとか、もう負の連鎖になっています。何とか札幌市のこの条例を応援して、東京また神奈川、いろんな各地方でどんどんやっていっていただけたらなと、本当に思っています。
●山根義久さん(獣医師、動物臨床医学研究所理事長、前日本獣医師会会長)
紹介にあずかりました、山根でございます。本日午前中、鳥取県から参上いたしました。といいますのは、私は獣医師でもございます。大学で教鞭も15年以上とりました。さらに日本獣医師会で8年間、会長を務めたわけでございます。
ちょうど動物愛護管理法の改正に向かったときでございまして、きょうご列席の松野頼久先生とも、いろいろご相談させていただいたわけでございまして。実は会長を辞めまして、今は3年目でございます。私は全く、もう56日が当たり前のようになっていると思ったんですね。ところが動物愛護法の付則を見ますと、緩和措置が取られて、まだまだそれに到達していないと聞きまして、驚いたわけでございます。
で、あちらこちらに問い合わせますと、なんと56日にするゆえんはどこにあるか、エビデンスはどこにあるかという質問がございます。なら逆に、日本のように四十数日で離す良さというのは、エビデンスはどこにあるんですか。昔から欧米では、四十数日で離すと、犬にとって、猫にとってよくないから、56日にしようという流れがあったわけでございます。
私は3年前に、現実には2年半でございますけれども、「アミティエ」という動物保護施設を立ち上げました。鳥取県には県立の保護施設がないんです、残念なことに、予算がないという一点張りで。私はたまたま公益社団法人の理事長をやってるもんでございますから、何とかこれを立ち上げなければならないということで、私財を寄付しまして立ち上げたところが、なんとうれしいことに、立ち上げた翌年には鳥取県が名を挙げてくれまして、今、民間の団体と公益財団と鳥取県がコラボを組んで、頑張っているところでございます。
そこの事例を1例だけ報告いたします。猫しか私は経験ございません。犬の場合には、まだそういう子犬を扱ったことはございませんけど、猫の場合には、7匹8匹がまとめて生まれるんでございます。そうなりますと、目の開かないうちに川に流してしまえというような、風潮もまだある地区でございますので、非常に残念でございますけれども、結局回り回ってうちの施設に来ます。そうしますと、離乳食からやっていかないといけない。お乳からやっていかないと。目が開いてないから。
そうしますと、どういう子供ができるかといいますと、だんだん里親にもらわれていきますと、性格が全然違います。8匹が8匹とも違うんです。もうけんかはするわ、社会性がないわけなんですね。ところが、母猫に餌を食べるようなところまで育てられて、2カ月3カ月で拾われてきますと、その子たちは本当に社会性がそろっているんです。すぐ里親が見つかっていきます。帰ってきません。非常に飼うのが楽なんですね。その事例を考えても、これは、犬にも同じ話であると私は思っております。
ですからぜひとも、早く、早急に、この札幌市の条例を立ち上げていただいて、日本全国津々浦々に広がってほしい。法律も含めてすべての地域で8週齢規制になれば良いということでございます。以上でございます。
●松野頼久さん(衆議院議員)
皆さん、こんばんは。松野でございます。ちょっと中座させていただくもので、先にごあいさつをさせていただいて、お許しをいただきたいと思います。
この8週齢規制。こないだの動物愛護法改正のときに、8週齢規制を入れたのは私でございます。自民党からは、今は大阪維新に行きました松浪健太さん。民主党からは、私と田島一成さん。公明党からは、高木美智代さん。この4名でワーキングチームをつくりまして、今回の動物愛護法改正の文章を作成したメンバーでございます。
その中で私が強く申したのは、本文の中に8週齢という、8という数字を絶対に入れろということ。随分議論いたしました。動物行動学とか動物生理学とか、いろんな面からの議論もありました。でも、これを言い始めると、大型犬と小型犬がなぜ同じ8週なのかとか、いろんな学者さんの学説があるんで、もうその議論はやめて、とにかく先進諸外国が8という数字を入れてるんだから、8なんだという決まりなんだということで。例えば道路交通法の中で、この道は40キロ、この道は50キロ、この道は60キロ。それぞれそんなデータに基づいて決めてないじゃないですかと。これを言い始めると、どんどんどんどん話が拡散して、結局は決まらないで、ずっと今まで8という数字が入らなかったという経緯があるので、もう動物生理学とか動物何とか学は外して、国として決めるんだということで、8という数字を入れました。
ただ、非常に抵抗が強くて、段階的に激変緩和措置ということで、5年間で8にもっていきましょうというふうに決めたはずなんです。私は、前に衆院環境委員会で、この件について30分40分議論してますんで、国会中継インターネット放送を見ていただければ、そのときの議論が出てますけれども。本来は、5年後には8になるための、段階的な激変緩和だったんですね。でも、今は環境省がもう全くやる気がなくて、「5年後には8になるんですね? なるんですね?」って言っても、「なる」とは言わないんです。
同時に、そのときに、8という証明をどうするのかという議論もいたしました。マイクロチップをきちんと入れてとかね。一番いいのは、獣医の先生方の力を借りて、出産証明みたいなものを、販売する犬に関してはきちっと付けるべきである。それによって、生まれた日に、人間の子供たちが出産の届け出を出すのと同じように、獣医さん立ち合いのもとに出産して、出産証明みたいなものをきちんと出して、それによって週齢を確定させる。要は、5万円とか10万円とかのコストで売る犬であれば、それぐらいにコストは十分吸収できるんじゃないか、みたいな議論もさせていただきました。
ただ、非常に抵抗が強くて。5年後の改正までには、マイクロチップを研究するという条文も入っているはずでございますけれども、全く今は環境省がそれを怠っているという状況と同時に、せっかく入れた8という本文に入れた数字を、附則の段階的な変な解釈によって、今はやろうとしていないという状況でございます。
今回、札幌市では本当にすばらしい条例をつくっていただきました。ぜひ全国の自治体が札幌市のように頑張っていただきますことを、心から祈念申し上げます。
●福島瑞穂さん(参議院議員)
どうも、皆さんこんにちは。社民党参議院議員、福島みずほです。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」のメンバーで活動しております。この8週齢については、札幌市がこの条例を出したということで、何としても成立できるように、議連としても、国会としても、個人としても、本当に応援したいというふうに思っています。
いま松野さんがおっしゃいましたが、本当にそのとおりで、法律に8週齢とあるわけだから、それを実現すべきなんですが。それで、私も国会で質問をしています。ところが、調査研究をするっていうのが、環境省の答弁なんですね。環境省は「8週齢やるんだ」って言わないんです。
でも、札幌がこの条例を成立させて、8週齢のほうがいいんだっていう実績がどんどん出てきて――というか、札幌市の条例が先にできて、国会での法律の附則を変えることがあとになるっていうのは、実は国会的には駄目って感じで思っていますが。でも、札幌市の条例がとにかく成立することを心から応援して、私たちも、議連としても、もしかしたら、また役員で話して声明を出すとか、あらゆることを国会からも出して、札幌市の条例の成立を応援したいと思っています。
もちろん国会でも、8週齢の実例が、あのへんてこりんな緩和措置が取れて、環境省がきちっとできるように、国会の中でまた質問し、かつ議連あるいはものすごい超党派で、力を合わせてやっていきたいと思っています。何としても成立するように、みんなで本当に応援しましょう。
国会でやれることはありますし、今までも環境大臣にみんなで申し入れに行ったりしてきてるんですが、環境大臣も替わったので、また申し入れに行くとか、国会でこそやれることをやり、この札幌市の条例成立を、心から応援していきたいと思います。
応援の仕方はいろいろあると思いますが、できれば議連で何か声明を出すとか。そこでは別に議論が起きないので、何か考えて意思表示をして、また、国会の中でも8週齢が実現するように頑張っていきます。どうもありがとうございます。
●山田太郎さん(参議院議員)
参議院議員の山田太郎でございます。「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」のほうでは副会長もやらせていただいておりまして、きょうの会議場の調整とか少し、いろいろさせていただきました。
実は私は、ここで言うのもはばかられるんですが、なぜこんな運動を始めることになったかというと、もともとビジネスをやっていた時にペットショップに投資した立場でありまして、逆に言うと、現場はどういうことが起こってるかっていうのを、垣間見てしまった人間であります。ご案内のとおり、今回は8週齢って話なんですけども、議連のほうもそればかりではなくて、卸しの段階でどれだけ間引かれているのか。あるいは、売れない子は最後はどうなっているのか。これは大変な問題なんです。
もう一つ、環境省のほう。私、実は農林水産のほうにもいたことがありまして、鳥獣対策の件については取り組んでいました。鳥獣を捕獲するというのはいいんですが、結局、年間92万頭も殺処分しているわけであります。これの理由はなぜかという、まあ、ちょっと鳥獣の話。ペットの話は皆さんされると思いますので、鳥獣からも少しいきたいと思いますが。
広葉樹の山を切って針葉樹にしてしまって、ドングリがない。餌がない。そうすれば、山里に出てきます。それから、針葉樹の森をいわゆる間引きしながら管理すれば、山道ができて、やっぱり山里に動物たちが出てきます。決して動物たちは勝手に増えたわけではなくて、人間の一種の罪というか。しかも、この針葉樹がきちっと売れる木材であれば、一つの理由になるのかもしれませんが、実際にはペイしないということで、国有林野事業を生産するのに3兆使って、結局お金を使って花粉をばらまき、動物たちを殺処分に追い込んでいるという。
一気に問題は解決するとは思いません。欧米なみに、あるいは欧州なみに、ペットショップなんていうものは禁止するというところまで、一気にできればいいんですが、そういうこともなかなかできないので、一歩一歩階段を上がっていかなければいけないんですけども。動物たちを含めて、命といった問題を考えたときに、まずやれること。それは、まず産業面の、そちらをわれわれは議員としてしっかりやっていきたいと思っています。
これもできなくて、その先の、トータルな意味での、いわゆるペットと人間の共生というふうに、話は進まないと思ってますから。やっと日本もこの入り口に立ったということで、頑張ってやっていきたいというふうに思ってます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。
●高井崇志さん(衆議院議員)
衆議院議員の高井と申します。
私は、法律をつくる、変えるためには、賛同する国会議員が増えないとしょうがないんで、去年1年、環境委員会だけじゃなくていろんな委員会に、3つ4つ出張していって、動物福祉の問題を取り上げて質問いたしました。そのときに必ず私が言ってたのは、地元は岡山なんですけど、岡山の愛護センターで実際に殺処分されている状況――ガス室で窒息死させられて、そして火葬される。中には生きたまま火葬されるような例もある。そういう話をすると、国会議員は、そんな実態があるのか、そんなにたくさん殺処分されているのかと、驚かれます。そして、またフェイスブックでそのことを上げたら、フェイスブックの友達は3000人ぐらいなんですけれども、なんとシェアが900。「いいね!」でも、私は200か300しかいったことがないんですけど、シェアだけで900っていう。これだけ多くの国民の皆さんの関心事なんだと。そういう話をすると、国会議員もみんな、そんなに国民の皆さんが関心を持ってるんだということで、少しずつ動きだしてくれているようにお聞きします。
きょうのテーマの8週齢も、法律が骨抜きになっていますから、この法改正は5年に一度ありますので、再来年、また改正作業に入るということで。ですから、ことし1年が環境省もその準備をする期間で、検討会なんかも立ち上げます。この1年が勝負だと。この1年の間に、しっかり環境省にも申し入れ、そしてまた、国会議員の賛同者を広げる。このことが大事だと思います。
きょうのような皆さんが、こうして国会に集まっていただいて、開いていただくことも、本当に重要な意義のあることだと思いますので、一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。一緒に頑張りましょう。
●藤野真紀子さん(TOKYO ZEROキャンペーン代表理事、元衆議院議員)
皆さま、こんばんは。TOKYO ZEROキャンペーン代表の藤野でございます。
まず最初に、TOKYO ZEROキャンペーンで、きょうは呼び掛け人の方々が応援に来てくださっております。簡単にご紹介させていただきたいと思います。50音順になっておりますので。放送作家の梅沢浩一さん。そして、都議会議員の塩村あやかさん。そして、『それでも人を愛する犬』の著者、田辺アンニイさん。そして、Do One Good 理事の松原賢さん。ジャーナリストの松原耕二さん。放送作家、エンジン01の山田美保子さん。そして、デザイナーの継枝幸枝さん。これらのメンバーが駆け付けているということでございます。
それでは一言だけ。すごく簡単に短い時間で言わなくちゃいけないので、ちょっと早口になっちゃいますけれども。本当に8週齢8週齢って一生懸命頑張ってきて、前回は議員立法になったときに、この取りまとめが、実は自民党がうまくいかなくて、トレーサビリティで8週齢をどうやって証明するんだっていうところがあって、全会一致というところにいかないがために、今回のようなちょっとややこしいことになってしまって、そういった無念も晴らしたいということで、今回は、国の法律もぜひ8週齢を成立させたい。そのためにも、今回の北海道札幌市の条例、本当にこれは歓迎すべきことで、私にとっては、本当に私たちが応援しなくちゃいけないなというふうに思っております。
この応援をするっていうことが、すごく大事だなってことを思っておりまして。本当に頑張ってやってくれる国会議員の先生、そして地方自治体、そういったものに対しては、堂々と明確な賛成、支援の表明をするというのは、きょうは浅田美代子さんもいらしているんですけれども、国が共生社会を目指すよといったときに、本当に明確にはっきりと支援をしますと、その声にみんな同調してどんどん広がってくる。このボトムアップの力っていうのは、バカにできないと思います。
ですから、この8週齢、ぜひともこの北海道で確実に成果を上げてもらって、そして、その波及効果に期待し、そして、国の法律を確実に、今回は5年で何とか成立させていただきたい。これはもうこちらを向いて言ってるんですけれども、議員の先生たちのお力に頼るしかないと思っておりまして。もしかしたら49日で終わっちゃうかもしれない、みたいなところも若干あるので。もうぜひこれは、全国津々浦々、札幌からスタートして、全国に波及して、そして国にというところに。
それで、どうしたらいいのかなということなんですよ、私たちが。やっぱり声を上げて、その大きな声を力にしていただくということと、国会の先生方のお力のある先生を、私たちがはっきりと支援するということが、とても大事だと思います。
今、松野先生が、5年でやれよということを明確におっしゃった。そういう先生がいないと、うやむやに流されてしまいます。環境省がやる気がないというわけではないと思います。ごめんなさいね。私、夫もみんな役人なもんで。弟もおじもみんな公務員なもんですから、信頼性がないと言われるのは非常につらいところがあるんですけども、生真面目、杓子定規で、本当に臨機応変に動かないところがある。でも、その代わり、法律にのっとって着々とやるということだと思っておりますので。今回もぜひ、この札幌を何とかみんなの力で形にしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
●細川敦史さん(弁護士)
皆さん、こんばんは。弁護士の細川と申します。きょうは兵庫県から参りました。多分3番目に遠い人間だと思います。
先月も議員会館で、皆さん、多くが、それなりの方が勉強会にいらっしゃったと思いますけども。きょうもその続きじゃないですけども、条例案のことをまずおさらいしてみたいと思います。目的規定っていうのがありまして、法律でもそうですよっていうふうに、いつも言ってます。札幌市の目的っていうのは、動物愛護管理法と比べたらちょっと違います。
大体一緒なんですけども、2番のところが違うんですね。1番っていうのが、動物の愛護っていうのは、これは、法律にも大体同じようなことが入っています。2番目が、動物の健康と安全を保持しますってことが入って、結構大事なところです。あとは、動物の福祉の向上、推進っていうのも、これも非常に目新しいというか、今まで法律ではあまり入ってない概念ですね。ここは非常に大事です。3番目が、動物の管理をしましょうっていうのは、これは法律にも入ってますんで、これは一緒です。4番目でもっていうのは、1、2、3の目的を、最終目標としては、人と動物の共生社会っていう、これは法律も一緒なんですね。ですから、札幌市の条例案の目的規定で違うところは2番のところ。ここを押さえといてください。
法律はどうなってますかっていったら、これは、先月勉強会でやった同じ中身なんですけども、1番目が、動物愛護の気風を高めましょうね、動物に優しい社会をつくりましょうねっていうのが、1番です。2番目っていうのが、動物の管理をしましょう、人に危害を加えないようにしましょうっていうのが、2番目ですね。3番目が、共生社会をつくりましょう。ですから、2番のところが違うところですね。黄色が条例の話をしています。ブルーのほうが、法律の話を大体をしてると思って聞いてください。
飼い主の順守事項っていうのが、今回条例案の中に入っています。ここが大事なところですよね。飼い主の義務として定められているんですね。飼い主ってなんぞやっていったら、所有者または占有者となってますので、飼い主といったら一般の飼い主さんっていうイメージなんですけども、そうじゃなくて、繁殖業者さんとかペットショップさん、犬猫を持っている人っていうのは、おおよそ含むということになります。
1番から12番までいろいろあるんですけども、その中で4番。譲渡は原則として離乳を終えてからですよということ。ただし、犬猫については生後8週間は親子を共にしてと、この前の、この勉強会というか、これと一緒です。ここと同じ文言が入っています。生後8週間は親子を共に飼養してから、譲渡してくださいね、そのように努めてねっていうふうに、書いています。ここが違うんですね。
じゃあ法律に戻って、法律でどうなってますかというのは、先ほど松野先生、福島先生がおっしゃっていたのと、同じことです。犬猫の販売業者さんは、所有者とは微妙に違うんですけども、こういう人たちは、出生後56日を経過しないものについては、引き渡しとか展示しちゃならないですよというふうに、法律にズバッともう書いてるんですね。これで、56日規制、8週齢規制はできるんじゃないか、よかったと思うんですけども、この附則っていうのが、文字がいっぱいあって、もう訳が分からない感じなんですけども、一応整理しました。
1番。ことしの9月までは45日。2番。ことしの9月からは、別に法律に定める日までって、よく分かんない日までは、49日なんですね。3番目。「別に法律で定める日」ができると、やっとここで56日。こういうふうになっています。その日っていつ決めるんですかといったら、アイウの項目を平成30年までに検討して、それで決めましょうねっていうふうになってるわけです。これは、販売業者の業務実態を考えましょうとかですね。
2番目が、今回は大事なところなんですけど。科学的な調査なんかをしたりして、結局いつがいいんですかというのを考えましょうと。ここで、社会一般への定着の度合いっていうのも、結構見てくださいと書いてあるわけです。ですから、世の中の人にとって、どれぐらいで引き離すのがいいのかなっていう部分を、どれぐらい定着できるかっていうのが、一つのファクターになっているという話です。生年月日の証明なんかの充実具合なんかも見ていきましょうというのが、書いてあることですね。とにかくこんな文字に書いてあるので、非常に未確定な状態になっているわけですね。
こういった激変緩和措置で、いつ変わるか分からへんみたいな、こういうのは、過去に1個だけ私は全例を見つけているんですけども。昭和58年に貸金業法の改正で、サラ金業者さんがすごい高利で昔は貸してたんですね。貸すことができてたんです。年利100%って、訳分かんない数字なんですけども。これが、40.004%に改正しますよと。すごく安くなりましたと。だけども、急に40%なんて下げられたら困るわって、業者のすごい抵抗があって、附則が出て、しばらくは54%にしますと。そのあと、別に法律で定める日まで40%になりません、みたいなふうになっていまして。そのあとどうなったかっていうと、平成元年ぐらいに、ある議員さんが「これ、どうなってんだ」みたいな質問をして、結局平成3年にようやく40.004%になりました。ですから、58年の法律改正から平成3年まですから、大体8年ぐらいになっています。
8週齢規制したら何がいいのかっていうのは、これはもう皆さん、私なんかが言うような話じゃないんですけども、人間にとっては飼育に困らない動物たち、犬猫が手に入りますよ。飼いやすいのでいいですね、みたいな話が、これが1番ですね。ちょっとこれは人間都合の話ですけどね。犬猫にとっては、問題行動の個体が減りますよとか、飼育困難を理由に、保健所に持ち込まれたり、遺棄されるような犬猫が減りますね。殺処分ゼロに貢献しますよねっていう話ですよね。これは、犬猫にとってみたらありがたい話なわけです。
3番目は、業者さんにとっても悪い話でもないわけで。小さい犬猫を衝動買いさせる手法は、もう使えなくなるんじゃないか。ちょっと大きくなってから売らなきゃいけないわけですから。そんなので、金もうけのためだけの悪質な業者は、ここで退場しなきゃいけなくなって、ある意味真面目な業者さん、うちはすごいこだわりがあるんだみたいな、頑固おやじみたいな業者さんが残ってくれる。というふうなシステムになると、いっぱい生ませて、いっぱい売って、いっぱい殺されちゃうっていうか、あとは知りませんみたいなビジネスは、変わっていくでしょっていう話が言えるんじゃないかなと思います。
条例案の8週齢規制はどこがいいんだって話になると、先ほども出てましたけども、他の自治体に波及するんじゃないですかって話とか、あとは、法律で56日規制の布石になるんじゃないですかっていうのは、いいことだというふうに言えるんじゃないですかね。というのが私の説明なので、あとは、これを踏まえて先生方の発表があるかと思いますので、ちょっと覚えといてください。以上です。
●太田光明さん(獣医師、東京農業大学農学部教授)
こんばんは。太田です。8週齢っていうのはイギリスが最初にやったので、その話を最初にちょっとさせていただきます。
イギリスっていう国は、動物愛護に関しては先進国です。非常に有名な法律が、ここにある動物保護法という法律です。日本は、ある意味ではイギリスに見習って、動物愛護に関しては考えてきました。ただ、日本の法律は、最初にできたのが1973年の動管法です。この左端にある、動物の保護及び管理に関する法律。これは1973年です。そのあと、1999年に改正。これは、愛護になったんです。保護ではなくて、愛護及び管理に関する法律で、動物愛護法という形になっています。もうちょっと詳しく見てみますと、1911年にイギリスは、動物保護法(Protection of Animals Act)と書いてありますけど、これを見習って、実際は1999年に改正動物愛護法というのをつくったんです。
先ほど言いましたように、イギリスは、8週齢というのを書いた法律がありまして、それは1951年です。40年後ですけども、1951年に、「Pet Animals Act 1951」とそこに書いてあって、この文章を読むと、そこの中に、母親と引き離される子犬は8週齢以上ということが、書いてあります。したがって、随分古いんですよね。ものすごく古くて。要するに、各国はこれを見習って、もうほとんどの欧米の先進国が8週という形になっています。
日本も何とか8週にしたい。そのためには何をやったかっていうと、まず日本の状態はどうなってるのかということで、2007年に共同研究をしました。そのときに、一般家庭で犬を飼育する飼い主の79%が、犬の問題行動を訴えている。要するに8割の人が何か困っているわけです。日本人は無理して犬を飼ってる。
これは調査研究ですので、これをオキシトシンの面から見てみようということで、実際は55組の犬とその飼い主で、実験しました。30分間触れ合ってもらって、実際に自分の飼っている犬といい関係にある人と、そうでもないという人がいて、実際にオキシトシンを測ったんですけど、そのときの結果がこれです。23.6%。55組のうち13組しか、オキシトシンが上がってこなかったんです。残りの76.4%、42組は、オキシトシンが上がってきませんでした。要するに、飼っててもほとんどメリットがない。そこに犬はいるけど、あまり大きなメリットがない。そういうことがありました。
先ほど山根先生も紹介されたんですけど、非常に大事な、脳の中に3つの神経伝達物質があります。ノルアドレナリンとセロトニン、ドーパミン。そこにちょっと書いてあるんですけど、ドーパミンというのはやる気を出す。車で言うとイグニッションで、点火する。ノルアドレナリンが、アクセル。セロトニンは両方やるんですけども、アクセルの場合もあれば、ブレーキもする。このドーパミンは、黒質とか、ここにちょっと書いてあって、難しいんですけど。そこの左の端に、ドーパミンの簡単な説明があります。私は神経科学を長くやってきましたので。
このドーパミン神経の発達に最も重要な要素が社会体験です。犬の社会化の期間は決まってるわけじゃなくて、大体12週までなんです。その一番大事な時期が8週なんです。これを外してしまうと、ドーパミンがうまく出てこない。先ほど言いましたように、この3つの神経伝達物質がうまく出てこないと、飼ってても犬らしい行動ができないし、飼い主さんがいくらコマンドを与えても、ちゃんと反応してくれないということになります。それが、先ほど言いましたように、約8割の飼い主さんが苦労しています。それを解消するためには、どうしても8週齢が必要なんですね。だから、私はそういった面で長く、犬ということはこういう特質であるということで、最近ではオキシトシンの研究をしてまいりました。
一番私が言いたいことは、マハトマ・ガンディーさんが言っている言葉です。「国家の偉大さや道徳的な進化の度合いは、その国が動物をどのように扱っているかで判断できる」。ありがとうございました。
●大屋雄裕さん(慶応義塾大学法学部教授)
ご紹介いただきました、大屋でございます。最初にお断りしなければいけないのは、私は動物愛護とは何の関わりもない人間でございまして、普通に猫を飼ってたりして、8週と聞くと、いいことなんだろうなと思ってるだけでございます。
今日まいりましたのは、私が前に研究したことのある、法律と条例の関係という観点から、今回の札幌市条例案について、問題点を指摘する。何を言ってるかというと、相手方が攻めてくるとしたらここだろうという話をします。というのは、皆さんには、それを踏まえた上で、じゃあ自分たちはどこを守ればいいのかということを、考えていただきたいという趣旨で、申し上げるのでありまして、こういうのを大体悪魔の代弁人と言っているので、われわれ法律家がやることになっているというお話でございます。
今回条例という形を取って実現しようとしていますので、問題になっているのは、それが地方自治体の条例でできることなのかという、条例制定権の限界を巡る問題でございます。これについては、憲法94条と地方自治法14条1項というのがありまして、条例をつくっていいよと書いてあるんですけど。当たり前ですけどね。「法令に違反しない限りにおいて」といったような、あるいは「地域における事務及びその他の事務」といったような、限界が付いているわけです。
こういった限界が具体的にどういう形で規制の可否に効いてくるかというと、従来、上乗せ規制と横出し規制という区別をよくしてきました。例えば典型的には、環境部門における大気汚染物質の規制なんかで論じられてきた話なんですが、こういう法律があったとして、何か規制物質について規制値を決める法律があったとして、別の観点から別の規制物質を追加するような、つまり、目的とか手段が違うような横出し規制というのは、これは基本的にOKである。これに対して、規制物質が同じで、目的も同じで、単に規制を強化するような上乗せ規制については、一定の疑問がある。許されないとは言えないが、その場合は、法令の趣旨というものを検討して、許されているかどうかを判断しなければいけないというふうに、言われてきました。
その規制の趣旨というのはどういうことかという話で、大変生臭い例を出して恐縮なんですが。例えば刑法177条というのは強姦罪ですけれども、そこでは13歳未満に対して姦淫したら、これは強姦罪になるんです。13歳未満に対する姦淫を禁止したものだと考えられますが、禁止した裏側として、13歳以上ならやってもいいですよっていう、性交の権利を積極的に保障したものとは、普通は考えないものである。だから、ここについては、多少別の目的があれば、例えば青少年保護育成条例と典型的に呼ばれている、各都道府県条例において――長野県だけないんですけれども。例えばみだりに性交することは禁止ですよといった、規制を加えることが許されるというふうに理解されています。
他方、道路交通法22条1項というのがありまして、つまりスピード違反が禁止されているわけです。これも禁止ですね。この禁止は、しかし、最高速度を越えてはなりませんよという禁止の裏側である、最高速度未満は走行していいという自由、これを保障しているように見えるわけです。単に最高速度から上は駄目ですよというだけで、その下は何も言ってないというのではなくて、免許を持って合法的に運転するんだったら、例えば規制速度が60キロだったら、59キロまでは自由に出していいですよと、そういう積極的な意味があるだろう。そうすると、例えばこの速度を、何とか市は40キロに一律制限しますみたいなことをするのは、法令の範囲を逸脱して、許されないというふうに考えられるのではないか。
そうすると、規制の文言であるとか、目的であるとか、そういったものから、積極的な保障を含むのか含まないのか。全国一律の規定を意図しているのか、意図していないのか。こういった問題を考えていく必要があるということになるわけです。
さて、そこで今回の問題ですが。抵触する法令として考えられるのは、当然ながら動物愛護法です。内容については、細川先生からお話がありましたが、ポイントは、要するに最終的には56日、8週齢を、法律も実現すべきだと言っておるわけですね。そして、今回の札幌市条例もここを目指そうとしている。背景にあるのが動物愛護であるというところも、大筋では変わらないとすると、まあ、これは普通に考えると、やっぱり上乗せ規制じゃないかなと言われそうな気がするわけです。
法律の趣旨に反しているわけではないから、法律に正面から盾突いているとは言えない。しかし、法律の側も一定の配慮から経過規定を設けているところを、前倒しでやってしまおうというものですから、その前倒しをするところで、経過規定の趣旨を逸脱するのではないかという攻め手を、多分向こうは打ってくるだろう。こういうふうに考えられるわけです。
そもそもなぜこういう経過規定がつくられるのかといいますと、一般論として申し上げると、やっぱり信頼の保護なんです。国が一定の規制をします。規制している状況があるときに、先ほど山田先生がおっしゃいましたけれども、ビジネスをやる側からしたら、その規制は基本的にまず変わらないであろうと信頼して、投資をするわけです。それが、ある日突然変わりましたと言われると、これは、投資としても困るわけであって、営業の自由というのも憲法上の価値ですから、一定の信頼というのは保護しなければならないであろう。そういうことですね。しかし、これについては、3年5年たったんだから、もういいじゃないかという返し技は、取りあえず使えるだろうと思います。
次は、個別具体的な事情でして、ここは附則7条3項が影響しているところです。詳しくは細川先生がご紹介されましたが、販売業者の業務実態、調査研究、引き離しの理想な時期に関する知見、生年月日証明の担保措置、こういうものがそろっているかどうか。
もう一つ。文言をこちこちに読むならば、あくまでも「5年以内に検討する」ということです。つまり、先ほどの話で、49日まではもう自動で、あらためて法改正がない限り移りますが、そのあと56日にするとは言った。しかし、それがいつかとは言ってない。それを決めるのも、5年以内に検討を始めるとは言った。すみやかにって書いてあるじゃないかっていうのは事実なんですが、この日本という国には「当面の間」というのを60年続けたことがあるわけでございまして。全然別の法律ですが。あまり明確に期限が切れるものではない。こういうところが問題になってくるわけです。
これに対抗する側からの観点で申し上げるならば、考えられる対応としてまずあるのは、努力義務であるっていうことを言うことです。要するに、法律は義務。義務づけですが、あくまで努力義務を課したものだから、正面からぶつかっていません。ただしこれは、正直言うとあまり言いたくない話だと思います。なぜならば、「分かりました。努力はします」と、向こうも言ってくるに決まってるからですね。
それが許される事情として、札幌に特有の事情があるということを強調していくというのが、先ほどの法令との抵触を避ける観点からは重要であろう。札幌だけにとは言わないです。少なくとも札幌においては、例えばですね、市民とか販売業者に対する衆知の状況が優れている。あるいは、生年月日証明を行う担保措置の枠組みというものができつつある、できた、進行中である。あるいは調査研究ですね。ここにおいてしっかりと成果が出ている。こういうものを積み重ねれば、札幌は、先ほどのような、業者さんの信頼を保護する必要性というのが薄れてきているのだから、つまり、業者さんの側でもう分かっていて、取り組みを進めているというようなことが、例えばあればですよ。なのに、みんなで待つことはないじゃないか。さっさとやろうということが、言いやすくなるわけです。そのあたりが、ポイントしては挙がってくるであろうと思われる。
もう一つ。附則7条3項の――善意に解釈すればですよ。悪意に解釈すれば、違うのかもしれませんが、善意に解釈すれば、要するに、状況が整ったら56日にしますって書いてあるわけです。ただし、その状況っていうのが整っているかというところが、問題である。その中で、札幌は整いました、あるいは、ほかの何とか市は整いました、何とか県は整いましたというのが、次々と出てくるとするならば、それはやはり国の側としても、「なるほどそうですね。もう全国的に整いつつありますね。じゃあ、56日です」という議論が展開しやすくなるであろう。
朝日新聞のコメントに、取り組みが今後広がっていくことが重要だっていうことを、申し上げた理由はここにありまして。最終的には法律の附則がアクティブになって、全国的に均一に法律で56日の義務が出てくるのが望ましいということなんだと思います。そこに持っていくための手段として、札幌市条例を考えた場合に、ここでとどまるのではなくて、状況の進行、懸念の解消というものを証明していくことが、求められるであろうと思うというのが、法律家的な観点からのお話だということになります。
ありがとうございました。
●青木貢一さん(獣医師、「動物との共生を考える連絡会」代表)
皆さん、こんばんは。青木でございます。皆さまのお手元に「連絡会ニュース」というのがあるかと思いますが、この中身は、次回の法律改正に向けての、われわれが「こういうところを変えてくださいよ」というリクエストの部分です。きょうは、このことを目的に話すわけではございませんので、56日規制、8週齢規制についてのお話ですが。
私どもは、最初の法律改正のときから、いろいろと国会議員に陳情させてもらいました。環境省ももちろんですね。そのときから、一番最初の改正が行われる寸前。ばらしますと、56日規制ができるというところまでいってたんです。あるたった1人の発言で、ひっくり返っちゃいました。非常に悔しい思いをしています。それから今日に至るまでの間に、こないだの法律改正の中で、極めて中途半端な法律改正。56日というのが本文に出ているのにもかかわらず、余計なものがくっついてる。附則というものがついている。私にとってみれば、この法律って、本当にほれぼれする法律なのかというと、とてもとても言えない。そんな状態なもんですから、何とか法律をきちっと有効性のあるものに変えるべきであろうと。
56日規制というのは、最初の法律改正のときに変えれるというふうな、ニュアンスがあったにもかかわらず、なくなっちゃった。じゃあ、なぜなくなっちゃったかということを考えますと、エビデンスの問題であるというのが、出てきちゃったわけです。
実はここに、2014年、平成26年の5月に、『獣医畜産新報』というのがございまして、これは獣医師向けの雑誌です。民間の雑誌です。JVMという雑誌ですが。その中に「改正動物愛護管理法に関連する犬猫幼齢動物の取り扱いについての調査」というのが、日本小動物獣医師会というのがございまして、そこが調査しました、それの結果報告が出ているわけです。
このアンケートは60日という数字を出しているんです。56日ではないんですが、まあ似たような数字なもんですから、いいでしょうということで。45日とか40日とか、その当時、昔は40日ぐらいで平気で売られているわけです。その売られている状態から、獣医師に対するアンケートの中で、56日規制がいいですよと言う人のほうが、圧倒的多数なんです。けども、中には「もっと若くてもいいですよ」みたいな論点で書いた人もいます。ということは、われわれ獣医師そのものが、獣医行動学とかいろんなものを、十分学んでない結果だと思います。
われわれとしては、何としても、動物のためになる法律、動物を救える法律というもの。要するに虐待防止法的なニュアンスを含めた法律に変えていただくということを、目指したいと思っているわけです。
お手元の中には、犬猫問題だけじゃなくて、今回新しくこの連絡会としては、何とか水生哺乳類にもというようなところまで、かなり幅広く組み込んだ改正を、飼育下にある全ての動物に対して、改正が今後できるような仕組みがほしいということで、活動しているわけですが、なんせ前回の法律改正のときには、地団駄を踏んだ状態がございます。それまでの間に環境省が二十数回にわたって、在り方検討会というのをやってくださったんです。その中でかなりの部分がいいところまでいってるのにもかかわらず、何かいつの間にか、変わってしまったんです。
こういうことだとすると、日本の法律改正の仕組みっていうのは、きょう国会議員の先生がおみえになってますが、何かどこかでどんでん返しが起こる。そのどんでん返しの一つのポイントとしては、業界擁護っていうのがありました。ペットショップ関係者の生活を守るためには、売れる状態でなければいけないみたいな論点が、そこに出てきちゃったような、ニュアンスが出てきてました。その結果、附則というものが出てきたんじゃないかなと、思っちゃったわけですね。どうしてそういうふうになっちゃったのというのを聞いても、教えてくれません。
もう1例。せっかく法律改正されたのにもかかわらず、法律がむちゃくちゃになっちゃってるんじゃないかなと。というのは、名古屋のほうの警察庁が、警察官が、捨てられてた猫ちゃんを――迷子の猫ちゃんですね。その子猫を保護した。で、動物愛護センターに持っていったんですけども、センターが拒否して、困っちゃって、その警察官はまた捨てちゃったんです。そういう事例が出たときに、不起訴になったんです。遺棄というものが犯罪になってるはずなのに、なぜ警察官だから遺棄をやっていいのよと。で、私は警察庁に問い合わせしました。残念ながら、個別の回答はできませんという、回答です。非常に腹が立ちましたね。この法律が、末端の警察官まで通じてくださることが願いでありますけども、われわれは警察庁とお話しさせてもらいましたときに、通達はしてくれるんですけども、末端まで届いてないなというのが、今の現状だと思います。そういうことのないようにするために、皆さん一人一人の声を、警察も含めて、声を届けていただければと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
●入交眞巳さん(獣医師、日本獣医生命科学大学講師)
今ご紹介いただきました、日本獣医生命科学大学の入交と申します。なぜ私がこの場できょうお話をさせていただいているかと申しますと、私は動物行動学のほうを専門にしておりまして、日本で獣医師免許を持っておりますが、アメリカのほうで10年間勉強して、行動学を学びました。ということから、声を掛けていただきました。
青木先生のおっしゃった、いわゆる8週齢という日数に対するエビデンス、いわゆる科学的な証拠のお話をここでさせていただきたいと思います。
まず、犬に関して申し上げますと、1950年代から70年代にかけて、アメリカの東海岸でスコットとフラーという研究者が、犬の遺伝子の研究をするために、5種類の犬を使って、掛け合わせて、F1といういわゆるミックスをつくって、その子犬たちの行動とか性格とか、遺伝子的に、犬種が混ざるとどうなるのかなというのを、研究したという事実がございます。
当時、行動学的なものを見るために、あるいは遺伝子を見るために、昔ですから、今みたいにPCRはないですけれども、子犬が成長するに当たって成長の段階に、いろいろな行動学的特徴がある。おそらくそれは、神経科学的にもつながるものだけれども、まだ50年代60年代ですから、行動学で主に見ていました。そのときに、面白い事実があるなということで、厚い本にまとめて出版されています。
その中で、いわゆる離乳が行われるのは、中型犬で調べているんですけど、7週から10週齢ぐらい。10週齢ぐらいたつと、どんな犬種でも大体離乳は済むでしょう。というふうにまとめています。ということで、離乳期は7から10週齢ぐらいというふうになります。
では、早期離乳。たとえば6週でお母さんから離しては、ちょっと早すぎるよということが、今問題になってるわけですが、4週とか6週の早い時期にもし離乳してしまうと、これはもう最近の研究になっているんですけれども、お母さんがいろいろなものを子犬にまだ教えていないという状態になります。まず精神医学的に、ちょっと不安傾向が強いという性格をもって、お母さんの元を離れてしまうということになります。
2点目は、お母さんは離乳という動作を通しながら、犬の場合、子犬にいろいろなことを教えていくことが分かっています。例えば犬同士のコミュニケーション。「お母さん、お乳ちょうだい」といって、歯が生え始めた子犬がおっぱいにかみつきますと、痛いわけですから、お母さんが子犬に対して「やめなさい! 痛い!」といって攻撃的になります。大きい犬が非常に強く攻撃してきた場合に、子犬はどう対処しなければならないかというのを、そういうところで、お母さんを通して子犬は学ぶ。「ここで行動を止めなきゃいけないんだ」「ここでおなかを出さなければいけないんだ」「ここでやめなければ大変なことになるんだ」というのを学ぶので、あとでほかの犬とのコミュニケーションに、それが役立っていきます。
さらに、離乳を通じて、子犬が「お母さん、離乳食ちょうだい」ということで、お母さんの口をなめておねだりします。お母さんが、それに対してゲボッと、胃液と混ざった離乳食を与えるんですが、この「お母さん、離乳食ちょうだい」という口をなめる行動は、甘える行動や、「あなたに私は抵抗する気はありません」という、言葉というコミュニケーションのツールになっています。皆さんがワンちゃんに口をなめられるのは、これです。甘えられているんです。口をなめる行動なんかも、ここで、離乳を通してお母さんから教わるということになります。
そういう犬の大事なコミュニケーションを、全く教われない状態で出てきてしまうと、やはり問題が大きくなってくるんじゃないか。社会化期と言われてますが、そのスタート時点でつまずいちゃってるということになって、われわれ人間には教えきれない部分がある。だからやっぱり、お母さんからいろいろ教えてもらってほしい。さらに、お母さんから早く離してほしくない。ということを考えますと、せめて離乳が始まった8週齢ぐらいまでは、待たせてあげないかというのが、西洋での考え方です。
今は8週というのが一人歩きしていますが、別に9週でも10週でもいいのかもしれません。これは、もうちょっと皆さまと考えていかなければならない点かとも思いますが、諸外国が8週にしているのは、おそらくこのような理由があると思います。
今、獣医師があまりこういう事実が分からないということも、青木先生からお話をいただきましたが、獣医学部のほうでは、コアカリキュラムというのが始まりまして、全国の獣医師が「この教科書を使って学ばなければいけない」というのがもう出ております。全国の大学全てで始まっております。この教科書を学んで、ちゃんと試験を通らないと、獣医師になれないので、多分あと4年後ぐらいには、出てくる獣医師さんはみんな、この事実を知っているという状態で出てきます。その獣医師が一般の方々を教育することになると、多分消費者のほうも、お買い求めになるときに、いろいろ考えていただけるのではないかなというふうに考えております。
私がきょうお話ししなければいけないのは、このぐらいのことだと思います。以上。
●西山ゆう子さん(日本および米国獣医師)
西山ゆう子です。はじめまして。よろしくお願いします。時間も押してますおんで、簡潔にぱぱっと、早くやりたいと思います。
私は、24年間アメリカで、通算日本で約6年ぐらい、本当に臨床現場で、動物病院の診察室で、毎日現場を見てます。なので、ちょっときょうは場違いで。こんな場に呼ばれて、偉そうに言える立場ではないんですけども。8週齢、現場の人間はみんな知ってます。8週齢以前に親から離れた子たちは、弱いです。駄目です。きょうは現場の立場として、臨床獣医師として、日本とアメリカの両方の国で臨床をやってきた経験を元に、8週齢以前で親から離れた子犬、子猫たちに、よく見られる問題点――あくまでも医療的なものですけれども、4つシェアしたいと思います。
1つ目、ワクチン。いつワクチンを打つんですか、早く離したら。早く離せば離すほど、早く打たなければいけない。早く打てば打つほど、ワクチンは打ったとしてもつかない。免疫がよく反応してくれない。あるいは、ワクチンの副作用で具合が悪くなる、あるいは死亡してしまう。これは明らかに起こってることです。早く離せば、早くワクチンを打たなきゃいけない。ワクチンの問題があります。これは忘れないでほしいと思います。
2つ目、伝染病。これはワクチンとは特に関係なく、例えば親が死んでしまったとかっていうことで、別にほかの犬とか猫とか、ペットショップとかそういうのを経由しないで、きれいな、ほかにも伝染病にかかると思えないような状況に、新しい飼い主さんがいったとして、そういう場合も全て踏まえた上で、若く親から離れた子犬、子猫は、伝染病にかかります。早く離せば弱い子です。これはみんな知ってます。現場の人間はみんな知ってます。当たり前のことです。
伝染病って何ですか。もちろん、ワクチンで予防できる、できないはありますけども。パルボとかジステンバーとかね。それ以外に、ジアルジア、キャンピロバクター、アデノから、結膜炎、クラミジアから何から、とにかくワクチンと関係なく、早く離れれば、何らかんらの病気持ちに。どうしてこんなものをこの子が。真菌なんかもそうですよね。長くなってしまいました。言いだせばきりがないですけど、現場の人間はみんな知ってます。なので、伝染病にかかりやすくなります。弱くなります。なので、親から早く離すことはよくないです。
3つ目、下痢。親から早く離す子は、下痢をします。なぜでしょうね。科学的なエビデンスがあるんですか。よく分かんないです。現場の人間は、みんな知ってます。下痢になります。もちろん免疫とかそういうものもあるでしょうし、母犬、母猫というのは、子犬、子猫のことを、24時間ぺろぺろぺろぺろ。排便したら排便したで、何かちょっとよだれがついた、目やにがついたっていったら、きれいにきれいにぺろぺろなめてるじゃないですか。あるいは、母犬、母猫の、口の中の最近フローラか何かうまくいってるのか。理由は分からないけれども、生後8週齢に満たない子犬、子猫が、排便、排尿したらべたべた踏んでしまいますし、それがよくないのかもしれない。そういうのもあるでしょうし、いろんな理由が重なると思うんですけども、若く離すと下痢をします。治りません。治すの大変です。これは、現場として確実にあります。
4つ目。これは偏見です。反感も多いと思いますけども、あえて言いますけれども、日本には生後3カ月未満の子犬、子猫を、そこそこきちんと育てられる人が、ほとんどいません。みんな下手くそです。日本人、アメリカ人って、別に言ってるわけじゃないんですけれども。獣医学としては、生後12週齢までをペディアトリック(小児科)、12週齢からは若犬、若猫っていう形で、一応区別してるんですけれども。12週齢以下のペディアトリックに関しては、育てるのはやはり大変な仕事だと思います。別に完璧に全てやれって言ってるわけではないんですけれども。何もやる気がなくて、犬を飼っちゃったからとか、そんなんじゃなくて、一生懸命勉強して、一生懸命頑張って、一生懸命飼育しようとしてる方でも、日本人の方は下手くそです。
フードを1日何グラムあげたらいいんでしょうかとか、1日何回排便したら。ちょろっとこの最後のところに、こういうような透明のゼリー状の粘液がつくんですけど、大丈夫ですか。そんなこと聞いてくるアメリカ人はいませんよね。支えてる基盤自体が、文化的になかなかそろってないんじゃないかと思います。悪口を言ってるわけじゃなくて。子犬を飼い始めて、大体9週、10週、11週齢、12週齢、ペディアトリックのときですよね。そのときに飼ってる日本人の飼い主さんは、「もうどうしていいんだか分からない。どうしてこうなるの? ほんとにちゃんと育ってるのかしら」もう心配ごとでいっぱいです。アメリカ人は「どう?」「エンジョイしてるわ。パピーって早くなりすぎちゃって困るわ。もうずっとパピーでいてほしい」みんなそういう答えが返ってきます。その文化の違いはあると思います。
以上です。
●稲垣真紀さん(「HOKKAIDOしっぽの会」代表理事)
皆さん、こんばんは。北海道から来ました、認定NPO法人しっぽの会 代表理事をしています、稲垣です。
北海道は、残念ながら、非常にこの問題に関して、皆さん意識がほとんどありません。私たちぐらいが「すごくいい条例なんだよ」っていうことを、うたっているような状態で、道内のテレビ、それから新聞、この条例はどうなんだろうっていうような、非常にマイナー的な状況に捉えられているような状態です。ですので、ぜひ東京の皆さん、こうやって札幌の条例を盛り上げようっていうか、応援しようと言っていただいているので、これを持って帰って……。副代表が札幌在住なので、検討のほうにも参加させていただき、条例のほうはずっとかかわってやってきています。ですので、ぜひその思いを持ってかえって、北海道で応援していきたいというふうに……。
行政の方も、すごく一生懸命この条例をつくりました。なので、私たちもこれから、メディアですとか、議員さんですとか、そういった方に、行政のできない支援をして、応援して、情報を拡散して、この問題に取り組んでいきたいと思いますので、皆さん、きょうは本当にありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。
●松井久美子さん(「動物環境・福祉協会Eva」事務局長)
本日は、当協会の代表理事である杉本彩が、仕事の都合で出席かなわず、代理で私のほうからコメントさせていただきます。
前回の法改正では、世論は明らかに規制強化の声が上がったにもかかわらず、業界主張の45日齢、そして欧米並みの8週齢の間を取った、7週齢という、なあなあの形で終了しました。なぜ附則が本則を上回り、8週齢規制が実現しないのか。答えは簡単です。度重なる動物愛護法の規制強化に、既に嫌気がさしている業界は、今後も法改正において規制緩和の主張をさらに強くしてくるでしょう。
皆さんもご存じのとおり、今回の8週齢規制だけでなく、使用施設の基準や繁殖回数の制限、ブリーダーの免許制等々、まだ解決すべき要件はたくさん残されています。私たち、そして個人で活動されている皆さま、そして多くの団体の皆さまも、いろんな活動をしておられます。ですが、どうしてもできないことは、直接法律に関わること。だからこそ、今ある山積した問題について根気強く議論し、決して事態が後退しないよう、行方を追っていくことが必要だと思います。
また、8週齢規制については、8という数字はもちろんのことなんですけれども、それまでの時期をどのような環境で過ごすのか。また、8週たったから、そのあと親犬から引き離し、小さな段ボールに入れられ、その後、長時間の流通に乗ることは、幼齢の個体には非常にリスクが高く、8週齢を過ぎたからといって、解決につながっていることとは到底思えません。全てひっくるめての議論になるのだと思います。今までは、ペットの命を商品として扱う人間の目線で、物事が進んできたように思いますが、動物の福祉の向上は当然ですが、動物の目線に立って物事を考えるべきだと思います。
札幌市と同様に、この取り組みが他の自治体へと、広く広がっていくように、切に願っております。
●山田佐代子さん(「神奈川県動物愛護協会」会長)
こんばんは。神奈川県動物愛護協会で会長をしております、山田と申します。1分ということですので、手短なんですけれども。
平成23年に、8週齢規制についての、法についてのパブリックコメントを、皆さん覚えていらっしゃると思うんですが。そのときに、8週齢規制に対して反対の意見という中で、今までのお話の中でもあったものですけれども。「社会化の妨げにならないよう、生後6週齢とすべき。長く親元に置きすぎると、歯が生えてきて、親犬が子犬に攻撃するようになる」こういうことで、まともに反対意見を述べていらっしゃるんですね。「生後50日を越えると動きが活発になり、親犬ももてあまして嫌がる様子が見られる」。ですから、繁殖・販売の方々が、こういった感じで、だから早く売ってしまったほうがいいと、そんなような意見をお持ちなのは、全くの間違いであると。それは、もうぜひぜひ、皆さんからも言っていただきたいと思います。
おそらく札幌市の条例が通過するのは、3月10日でよろしいんでしょうか。そのあたりになるのかなと思うんですけれども。ちょうどうちのほうでは、実は今月の末に、ポスターを駅とかに掲示する予定になってまして、本当は違う内容の文言がここに入るつもりだったんですけども、急遽、8週齢まで親元に置き、人との適切な触れ合いをしていくことを、私たちの団体は支持しますというのを、入れたポスターをつくりました。
8週齢規制のポスターも、もうそれだけで独自でつくるような方向で、何しろ応援していきたいと思いますので、皆さまもどうぞよろしくお願いいたします。
●和崎聖子さん(「動物実験の廃止を求める会(JAVA)」事務局長)
NPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)の事務局長をしております、和崎と申します。
8週齢規制については、先の動物愛護法改正のときに、当会でも、せめて8週齢までは、親きょうだいから離さずに一緒に暮らさせることを、要望してきました。しかし、ご説明があったとおり、いまだ動物愛護法では実現していません。そのような状況の中で、札幌市が今回条例にこの8週齢の条項を入れたことは、とても評価できることだと考えています。
ただ、一方で忘れてはいけないのが、この札幌市の条例案には、猫の駆除を促しかねない、猫の所有明示の義務づけですとか、地域猫活動の阻害となりかねない、飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者の順守事項も、盛り込まれています。さらには、先ほど松野先生もご指摘されていましたけれども、愛護条例にはふさわしくない、野犬捕獲・掃討の条項も、既存の「畜犬取締り及び野犬掃とう条例」から引き継がれているというように、問題点も多々あり、修正の必要があるということも否めないと思います。
ただ、本当にこの生後8週間の条項については、動物愛護法とか全国の条例の先駆けとなるもので、ぜひここは実現していただきたいという思いで、きょうは参加させていただきました。皆さんでぜひ協力して、全国の条例とか動物愛護法を、人間の都合重視のものではなくて、本当に動物を守れるものにしていきましょう。
どうもありがとうございました。
●東さちこさん(「PEACE」代表)
PEACEという団体の代表をしております、東と申します。PEACEという団体自体は、2012年の法改正のあとにできた団体なのですけれども、過去2回ばかりの法改正の運動に結構関わってきました関係で、きょうもこの集会をお手伝いさせていただきました。
これまでの経緯を見ていて感じますことは、この8週齢という問題に、あまりにも多くの時間とリソースを割かれてきているということです。きょう、これまでの話をお聞きになって、割ともう自明のことと保護団体でも受け止めているような数値を法律に盛り込んで、それを実際に運用されるところまでに、こんなにも大変なのかというのが、実感としてあると思います。
一つは、科学的根拠というところが、非常に強調されてきたということがありますし、今環境省が行っている研究の結果というのも、どういう結果が出てくるかは分かりません。
ただ、動物実験のことにも関わっていますので、人の安心安全のための数値規制というところにも、ちょっと関わらせてもらうときがあるんですけれども、その場合というのは、人で被害が出ないようにというのは、実験結果の数値がそのままが規制値になるわけではありません。必ず、被害が出ない安心安全、社会の安心感との調整をつけるところに、数値規制というのは置かれるわけです。動物の場合は、1匹たりともっていうところは、なかなか難しいのかもしれないですけれども、なるべく多くの犬猫が保護されるような数値で決定していくというのが、やはりそれは政策、科学だけではなくて、政策の問題だと思っております。
むしろ本当に分析していただきたいのは、なぜ8週齢が業界の方は実現できないのかというところですね。やはりオークションと店頭販売を介して日数もかかりますし、繁殖場の飼育の状況もよろしくないので、早く引き離したいというところもあるかと思います。そういったところについても、今後規制強化を行っていく。
次の改正は、まだまだほかの動物についても、いろいろな問題が残っていますので、実験動物、畜産動物、全部保護する条項をつくっていただきたいです。次の法改正の前に、別な法律で定めるところ、56日を実行するんだという立法を、ぜひ先生方にお願いしたいと思っています。
そのために、今回の札幌市の条例は、非常に画期的だと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
●梅田達也さん(保護猫カフェ「ねこかつ」代表)
保護猫カフェという、猫の保護譲渡をしております、梅田と申します。埼玉の田舎のほうでちっちゃく活動しているのに、こういった場でお話しさせていただくのは、大変恐縮なんですけれども。
行政の殺処分をゼロにしよう、減らしていこうというのは、これはもうコンセンサスが取れているんだと思います。これは、国でも自治体でもそうだと思います。年々減ってはきています。この減っている部分は、私たちのような保護譲渡をしている、たくさんのボランティアの、ほとんどその努力の成果だと思っているんですけれども。今後ゼロにしていくために、いろんな施策が、国や自治体や議員さん、いろんなところから出ています。その中で多くを占めるのは、ボランティアの協働というところがあるかと思いますけれども。もう既にボランティアは血を吐くような思いをして、本当に生活を削って、全精力を傾けて、保護譲渡をしています。
蛇口を締めないで保護譲渡だけしていても、ボランティアがつぶれていくだけで、全く解決にはならないです。この蛇口を締める中に多くの割合を占めるのは、この生体販売の問題だと思います。その突破口としての8週齢規制は、ぜひ実現させてほしいと思います。
ここに、多分、議員さんだとか行政の方、たくさんいらっしゃると思いますけれども、ボランティアとの協働を求めるのであれば、ぜひ蛇口を締める部分で本気を出していただきたいなと思います。それをしないで、ボランティアに協働というのは、ボランティアをただ使い回すだけで、虫のいい話だと私は思っておりますので、ぜひ蛇口を締めるその突破口としての8週齢規制、札幌市条例、それを全国に広めて、国にも実現してほしいと思います。よろしくお願いします。
●太田匡彦さん(『犬を殺すのは誰か』著者)
個人的なお話として申し上げます。
札幌市の条項ができるという記事を書きました。先ほど来の話の中で、少し補足をさせていただくと、札幌市を取材しておりますと、まず職員の方々の熱意でできた条項です。実態がどうなのかっていうお話があったかと思うんですが、取材の中では、札幌市の繁殖業者さんのほうでは、法律で、犬猫等販売業者は、健康安全計画というのを提出しなければいけないんですが、ここに数字を書かせているんですね、札幌市さんは。その実態を見ていきますと、既に57日以降に出荷しているというところが、6割を越えているそうです。そういった意味では、大屋先生が先ほどおっしゃったような実態というのが伴って、並行してできていってる話であろうと思いつつ。
一方で、環境省さんと法律の関係を見ていきますと、実は日本のブリーダーでも――繁殖屋という言葉とブリーダーさんという言葉を、使い分けさせていただきますが、とっくに2カ月齢、3カ月齢で出荷しているブリーダーさんが、結構たくさんいるんですね。環境省は、実はそういったところにチャンネルを持ってないなというのを非常に感じてまして。今やってる科学的知見を蓄えるための調査については、ペットショップで売られた犬猫についてしか、サンプルが採れていません。こうなると、この結果が出たときに、日本だけ大変珍妙な計画が出る可能性があります。
これはご存じのように、ペットショップの仕入れ先であることを考えていただければ、分かると思うんですが、そこについて非常に問題視しているという話を、今日はさせていただきます。ありがとうございます。
●浅田美代子さん(女優)
本当に繁殖業の8週齢規制っていうか、それは本当は最低限の条件だと思います。それが、なぜ日本ではいつまでたっても実現してくれないのか、本当にいらだっています。今度の法改正のときこそは、必ず、必ずこれは入れてもらいたいですし、やっぱり命を大事にするという気持ちで、先生方どうぞよろしくお願いします。8週齢を通してください。
きょうはどうもありがとうございました。
●福島瑞穂さん(参議院議員)
貴重な意見もたくさん聞かせていただいて、本当にありがとうございます。いろいろ課題は山積していますが、一つは、この8週齢規制をやることで、次のステップに行くことも、かなりできるというふうに思っています。条例ができると、かなり国の施策にも反映するので、札幌市と、負けないように、早く国会の中でやりたいですし、議員連盟の役員で早く集まって、この札幌市の条例を応援するみたいな、議連としての声明なり意見が出せればと思っています。
きょうは本当にありがとうございました。
●山田太郎さん(参議院参院議員)
再び山田太郎でございます。今、福島さんと目の前でこそこそ話したけど、議連ですぐに動こうということを話し合いましたんで、すぐやっていきたいと思ってます。
一部の方からもありましたけども、あるいはブリーダーとか、先ほどちょっと言いました、売る側、現場の告発もしていきながらやるという、そういう立場の人も必要なのかな。まさにおっしゃっていた、ワクチン。もう早すぎて、効かないのが分かってて打ったりとかですね。伝染病の子が1人出ると、全部殺してます。もうきりがないほど、いろんなことが現場で起こってるということです。
動物愛護の問題と人間の問題。同じ命を、一緒に幅広く考えていって、優しい豊かな国をもう一度われわれはつくり直したい。欧米に比べて、先ほど先生のほうからもありました、60年日本は遅れている。イギリスに対して遅れてるって発表がありましたが、児童養護のほうも実は50年遅れてます。私も、秋にずっとイギリス、それからオランダ、ドイツというふうに回ってきたんですけども、とてもじゃないけれども、日本はやっぱり遅れている。これで先進国なのか。私も議員になって思い知らされたことがたくさんあります。ぜひ皆さん、一緒になって、幅広くこの問題を捉えてやっていきたいと思います。
議連のほうは、きょうは役員が2人、誓い合いましたので、何とか頑張ってやっていきたいと思っていますけども。松野さんもさっき、絶対やるということで。3人そろえば文殊の知恵じゃないですけど、バカ力を出してやっていきたいと思います。どうか応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。
(司会:渡辺眞子さん[作家]、会場運営:塩村文夏[東京都議会議員]、佐々木修さん[埼玉県三郷市議会議員])
以上
|
 |
 |
|
|
|
HOME  ALIVEの紹介 ALIVEの紹介  野生動物 野生動物  ズー・チェック ズー・チェック  家庭動物 家庭動物  畜産動物 畜産動物
 動物実験 動物実験
 生命倫理 生命倫理
 ライフスタイル ライフスタイル
 動物保護法
動物保護法

海外ニュース  資料集
資料集  ビデオ
ビデオ  会報「ALIVE」 会報「ALIVE」  取り扱い図書 取り扱い図書  参考図書紹介 参考図書紹介  リンク リンク  お問い合わせ お問い合わせ  資料請求 資料請求
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求