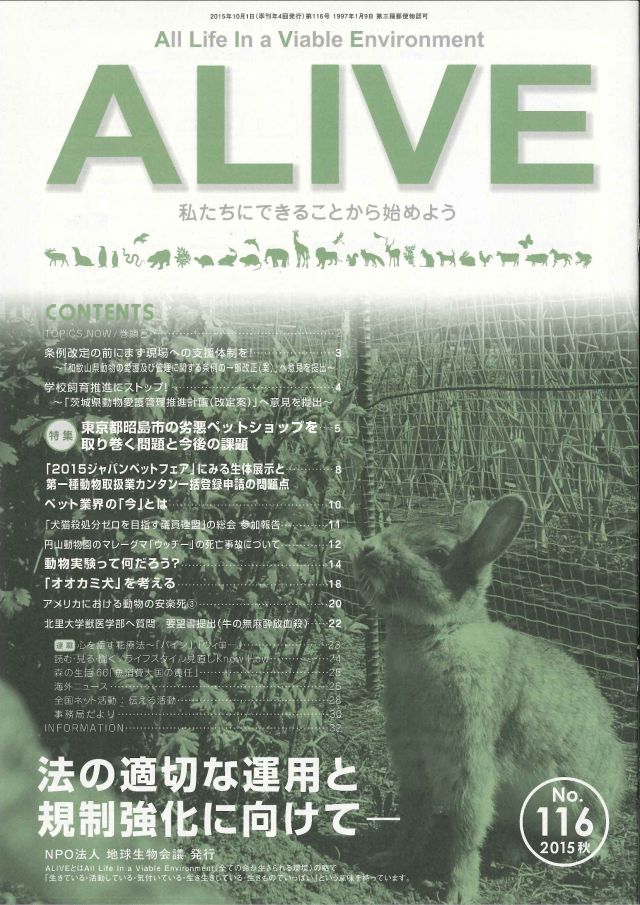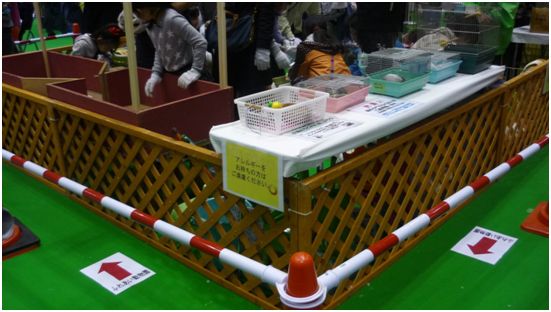|
®¨E«Éâ³µ¢CtX^CÌñÄA®ÉÖ·éÄÑ©¯âîññðs¤½ßÉAALIVEÅÍAïõÌFlÉN2ñAïñwALIVExð¨ÆǯµÄ¢Ü·B
@
| ïñuALIVEv 116ÌTvÆvñ |
¦ÈºÍLÌvñÅ·BLÌS¶ð¨ÇÝÉÈè½¢êÍAICVbvÉÄ{ïñð¨¢ßº³¢Ü·æ¤¨è¢\µã°Ü·BobNio[ਢ¨ß¢½¾¯Ü·B
¦ïñu`khudvÌèúwÇð²ó]ÌFlÌïÖ̲üïðSæè¨è¢\µã°Ü·B
ïñu`khudv 116 i2015.10.01sj
@ÌKØÈ^pÆK§»Éü¯Ä\B
¡ Rec
yTopics Nowz
Eªª¾
y®¨Ûì@z
EðáüèÌOÉܸ»êÖÌx̧ðI
@`uaÌR§®¨Ì¤ìyÑÇÉÖ·éðáÌêü³iÄjvÖÓ©ðño`
EwZçiÉXgbvI
@`uï駮¨¤ìÇivæiüèÄjvÖÓ©ðño`
y®¨æµÆz
EÁWºsÌò«ybgVbvðæèªâèÆ¡ãÌÛè
EAWAÅåÌybgCxguALL JAPAN PET EXPO IN TOKYOvA
@u2015WpybgtFAvÉÝé¶ÌW¦Ææêí®¨æµÆJ^êo^\¿Ìâè_
yÆ뮨z
EybgÆEÌu¡vÆÍ
@`C^[ybg@rWlXEtH[ñ`
Eu¢LEª[ðÚw·cõA¿vÌï@QÁñ
yW¦®¨z
E~R®¨Ì}[O}uEb`[vÌSÌÉ¢Ä
yÀ±®¨z
E®¨À±ÁĽ¾ë¤H
yÁ讨z
EuIIJ~¢vðl¦é
yCOîz
EAJɨ¯é®¨ÌÀyB
yÀ±®¨z
Ek¢åwbãwÖ¿â^v]ñoi̳úEj
yCtX^Cz
ESðü·ÔÃ@
EÇÞE©éE·
ECtX^C©¼µKnow How
EX̶UU
yCOj
[Xz
ySlbg®z
y񀙊z
y¨mç¹z
yTopics Now^ªª¾z
ªª¾
@uú{nIsvð²¶m¾ë¤©Bpl«CUxEo[hªPWVWNÉk©çkC¹É©¯Ä·µAú{l̶ⶻAið`ʵĢ·sLÈ̾ªAOlÌÚÉféÌú{Ìlqª¾É`©êĢĻ¡[¢B»ãÆÍÊ¢EÅAí¸©S\NΩèÅÌÏÔèÉÍÁΩè¾B
@·ÌsæXÅnðæè·¦é±ÆÉÈé½ßnÌLqའéªAµ¢É¢Ìn½¿ÉεÄAkÅÍú{lª{Á½èA@¢½èAÚðĽèAܵÄsÒ·éæ¤È±ÆðÚɵȢB¢ÍlÔÌÆ°ÌlÅ è¹ÄÍ¢ÄàÝȸâ©Å éB÷HÍSÊIÉíêĨèAo[hÍ{ðèÉüêéÌÉêJµAÉÍH×éÌÅÍÈðæé½ßÆRàÂB
@®¨½¿ðåXIÉp·éÐï\¢Í»ãÅͽèOÆÈÁÄ¢éªAÀÍßN}¬É\z³ê½àÌÅ éBÍAߢ«K¸s«ß¬½ÈwÍÄl³êéÆvÁÄ¢é̾ªAàׯDæÅ®¨ðmƵ©Ýȳ¸É¤Æp·é»ÝÌ®¨Ìæèµ¢ÍAÅàð©Ès×ƵÄfß³êéÌÅÍÈ¢¾ë¤©B
@½¿ú{lÌcm`ÉÜ꽶½ÏA®¨ÉηéÏÏÍæèß¹é̾뤩\H
Ë@ALIVE̪ª¾
y®¨Ûì@z
ðáüèÌOÉܸ»êÖÌx̧ðI
`uaÌR§®¨Ì¤ìyÑÇÉÖ·éðáÌêü³iÄjvÖÓ©ðño`
@ðáÅsªFè·éÈOÌìÇLÖÌaâèðÖ~·é±ÆÅbèÉÈÁ½ssɱ¢ÄA¡xÍaÌR§É¨¢Ä©gÌ¢LÈOÖÌaâèð´¥Ö~·éûüÅðáªüè³êé±ÆÆÈèܵ½B
¡ ±êÜÅÌoÜ
@QOPSN12AssªsÌÀ{·éuܿ˱®vÈOÌaâèðÖ~·éæ¤ÈðáðV½É§è·é±Æð\µÜµ½B{eBAÅ»êÉgíéÂlEcÌÈÇ©ç½Ì½Î⩼µðß麪 ªèܵ½ªAðá̼Oðuss®¨Æ̤¶Éü¯½}i[ÉÖ·éðávÉÏXµAQOPTNVPú©ç{s³êܵ½B
@»ÌãAaÌR§ªìÇLÉÖ·éêîªãðâ½È¢±Æðó¯ÄAs¹{§xÅßįlÌðáð§è·é±Æðö\Aï©çÍåÉȺÌæ¤ÈÓ©ðñoµÄ¢Ü·B i
Ó©ÌRÉ«ܵÄÍAïñ116ð²¾³¢Bj
aÌR§®¨Ì¤ìyÑÇÉÖ·éðáÌêü³iÄjÖÌÓ©
@ næLÎôªL§¯Ép³êéæ¤ÉA{qÄCÌunæLÎôðs¤ÒÌ
çvÌ©¼µðs¢AðÉaÈÇðs¤×«Å éB@ܽA»ÝA§ÆµÄìÇLÎôÉε¬àðtisD¨èpSÈÇjðÀ{µÄ¢È¢æ¤Å éªA§¯ÌSð}¦Aæ讵ⷢ«ð®õ·é½ßÉAnæLÎôÌxÌÚððáÉ·èÞ׫ŠéB
A u³Èaâès×vÉæÁÄìÇLª¦½©Ìæ¤ÈóÛðó¯é¨»êª é½ßA{qÄÌO¶Éu¢å̢ȢLv̪{Iȶ´öÉ¢ÄLڵĨ׫ŠéB
B næLÎôÉ®³È¢Âl{eBAÉæÁÄKØÈÇ̺ÅsíêéaâèÉ¢ÄÍA
u³Èaâès×vÉYµÈ¢Æ¾mÉí©é¶¾ðLڷ׫ŠéB
C ðáü³É ½ÁÄA½ªçÍo§ð·èÞ׫ŠéB
D 춮¨Éηéaâès×Ì´¥Ö~É¢ķèÞ׫ŠéB
y®¨Ûì@z
wZçiÉXgbvI
`uï駮¨¤ìÇivæiüèÄjvÖÓ©ðño`
@uï駮¨¤ìÇivæiüèÄjvÉ¢ÄÌÓ©åWªAVRú©çWPúÜÅÀ{³êܵ½Bö\³ê½ïé§ÌivæÌàeÍA¼Ì©¡ÌÆä×ÄAuwZ³çÆÌAgvðæèf°AwZçÌKv«ðà¢Ä¨èAÈ©ÉÍuwZbãtÌÝuª]ÜêéƱëÅ·BvÈÇÆ¢¤¶¾à©ó¯çêܵ½Bµ©µAwZçÍ®¨ðmÛ·é±ÆªÉßÄ¢ïÅ èAqÇàÉÔáÁ½F¯ð^¦ÄµÜ¤Â\«à èÜ·B±ÌwZçÉÅ_ð ÄAïªñoµ½Ó©ÌTvð²ñ¢½µÜ·BÚµÍïñ116ð²¾³¢B
¡ wZçÌiÉXgbvI`khudÌñoÓ©ÌTv
@ wZbãtÌÝuâwZ箨Ì{É¢Ä
@üèÄÉLÚ³ê½uwZbãtÌÝuvÍ@IªªÈAßÌÀø«à³¾©ÅÍÈ¢½ßí·×«Å·BwZ箨ÍA»ÌÇÒªÆ뮨{ÛÇîÉîëKØÉ{·é±Æª`±Ã¯çêĨèAîð
çÅ«È¢êÍç·×«ÅÍ èܹñB
A ®¨Óê ¢³ºÉ¢Ä
@u®¨Óê ¢³ºvÉÍlXÈâèñªñ¹çêĨèAiEÎÛgåÍs¤×«ÅÍÈ¢Æl¦Ü·Bbãt⮨¤ìiõÅநðOñƵ½®¨îÝ®ªs¦éÆÍÀç¸A»ÌíÉηéÔáÁ½ðâÖW«ð³¦ÄµÜ¤±ÆÉÈè©ËܹñB½ÌåسðwԱƪÚIÅ éÈçή¨ðgí¸ÆàÂ\Å é±Æ©çu®¨ðgíÈ¢®¨¤ì³çv̱ü¢É¢ÄLڷ׫ŷB
B wZ箨Ìçx̧Ì\zÉ¢Ä
@®¨ðçµÄ¢éwZ̽Í[ªÈç\ZªÈAlXÈÛèðø¦Ä¨èA²{IÈüPÍúÒūܹñB®¨¤ìÇ@ðÇ·ésEõªÆ뮨Ì{yÑÛÇÌîÉîëKvÈw±ðs¤|AüèÄÉLڷ׫ŷB
C ÐQÎôÉ¢Ä
@åKÍÐQÌÝÈç¸AÐƽÑäâJÈÇÌ©RÐQª¶·êνÌwZªxZÆÈèAwZ箨ªæèc³êé±Æà èÜ·B®¨¤ìÇ@ðͶßAÆ뮨Ì{yÑÛÇÉÖ·éîÌÖW@ßÌümOêð}é׫ŷB
y®¨æµÆz
ÁWºsÌò«ybgVbvðæèªâèÆ¡ãÌÛè
@ß37ñàÌsw±ðó¯éàüPªÈ³ê¸A2015N4ÉsÛÇ©çƱâ~½ßªo³ê½ºsÌybgVbvÌÀÔªñ¶çê½ÌÍL¯ÉVµ¢B
@µ©µ»ÌãAæOÒÉ¢Lð÷èn·Ìw±ÉæèAÅIIÉÌÚIÌ¢LÌðOɵĢLÌÆðp~Aá@ªüP³ê½ÆµÄu¢LÈOÌ®¨vÌÌÆðÄJµ½ÀÍAÖWÒÉëÁ½bZ[Wðé±ÆÉÈçÈ¢©\B
i®¨ÌNÆÀSÌÛãÌâèÉ¢Äw±EüP³¹é±ÆªdvÈÌÅ èAÌ®¨ðybgiÆ뮨jÉÚs·é±ÆðFß½èAæOÒÉ÷èn·µÄªí¸ð}é±ÆÍüPÎÛƷ׫Û̹¸ðµ«©Ë¸A@ªKØÉ^p³êÈ¢¨»êà éB{É©©íés¶i½¬26N7ÉsÌ®¨ÄõoÌÓw±jÉÍAusKªFßçê½vƵÄ33Éí½éYª èAæ5ð2uj@®¨ª¾aÉ©©èAÍáQðÁ½êÉÍA¬â©ÉKvÈuðs¤ÆÆàÉAKvɶÄbãtÉæé¡Ãð󯳹é±ÆBvàÜÜêÄ¢éÌÅ éBj
@»¤O·éBÉÞ¯ÄA±ÌâèɸÍIÉæègÜêÄ«½scïcõ̺ ⩳ñªAsªÜÅÌoÜðÔÁľ³¢Üµ½B
- - - - - - - - - - - - - -
ïñuALIVEv116ÌÁWLƵĺ â©scæè²ñe¢½¾¢½{eÍA
©úV·Ðª^c·éybgîñMTCgurvÉfÚ¸¢Ä¨èÜ·ÌÅAȺæèS¶¨Çݸ±ÆªÅ«Ü·B
sàÌò«ybgVbvðæèªâèÆ¡ãÌÛè@i©úV·Ðurvj
@@http://sippolife.jp/issue/2015110400003.html
y®¨æµÆz
AWAÅåÌybgCxguALL JAPAN PET EXPO IN TOKYOv A
u2015WpybgtFAvÉÝé
¶ÌW¦Ææêí®¨æµÆJ^êo^\¿Ìâè_
@QOPTNSQú`TúÜÅÌSúÔArbOTCgÉÄAAWAÅåÌybgCxguALL@JAPAN@PET@EXPO@in@TOKYOvªJóêܵ½B
@ïñ115Å|[gµ½uC^[ybg2015ÉÝéybgYÆÌ®üÆíªvɱ«A
¡ñÍWpybgtFAihttp://www.jppma.or.jp/petfair/jÉoWµÄ¢½Ú®®¨ÌÀÔÆAæêí®¨æµÆo^ÉÖ·éâèðæèã°Ä¢Ü·B
¡ åKÍybgCxgÌêo^
@WpybgtFAÍAú{ybgpiHÆïªå÷éCxgÅAu©Â¯æ¤IybgÆéç·ìÑðvðe[}É¡NÍPROàÌéÆoWª èܵ½ªAXe[WCxgÉócüãq³ñA³©ÈNÈÇÌ|\lªµ©ê½½ß©Aúöâ©Åµ½B
@mFÎÛÌuybgÆÌÓê ¢R[i[vÍïêüûtßÉ èA¡NÍUÂÌÆÒÉæé¶ÌW¦ªsíêéÆ ÁÄL¢GAªmÛ³êĢܵ½ªAJÃúÍ®¨ªÀü³êĢȢ×AP[WÙ©{{ÝÍ®¬µÄ¢Ü¹ñŵ½Bµ©µAæêí®¨æµÆÌo^\¿Éº¤§ü¸Í»ÌóÔÅÀ{³ê½Æ̱ÆAÀÛÉW¦³ê鮨ÌíÞâÌ·EðmF¹¸ÉAÖW@ß
çâu{ÝÌ\¢yÑKÍAÝõÌíÞvÈÇÌÚ×ðð½µÄ¢é©Û©Ì¸ªÂ\ÈÌŵ天B
i¦sÉæêí®¨æµÆÌo^ðsÁĢȢÆÒªsàÅcÆðs¤êA
KÍÉàæéÆ¢íêĢܷªAÖXãu1úð´¦È¢ÍÍvÌ»sÈOÍo^豫ªKvBj
@åKÍybgCxgÅÍW¦®¨ðL·éoWÆÒÉãíÁÄåÃÒi»såjªÆÌo^\¿ðêµÄs¤±Æª èÜ·ªA»êÉæ趵½âèðͶßAW¦®¨Ìæèµ¢Æ@ß
çóµÉ¢Äñ¢½µÜ·B
iïñÅæèã°½4ÆÒ̤¿3ÆÒðfÚAðàÌêðC³Eâ«µÄ èÜ·Bj
¡ ybgÆÌÓê ¢R[i[
~N®¨iïé§î~Sj
yW¯Ìf¦zYÆÒÌW¯ªf¦³êĢȩÁ½B
yWõÌlzQ¼@w¶{eBA¼
y®¨íÆzMi¶ãQ©jPAETMRAbgTAfO[PAp_}EX¡
y¹íÆzqR½AngQACRåPAZLZCCRUA¶¹QAJiAQA\o
S
@u~N®¨vÍA©ÂÄu®¨¤ìtFXeBo_Þì2013vÉoWµ½³o^ÆÒÉ®¨Æo^W¯ðݵĢ½±Æª»¾Asª®¨ÌÚ®óµÈÇÌÇÕ²¸ðsÁ½±Æà éÚ®®¨Å·B
@¡ñÍMûÞÌÝÈç¸A¬¹ÜÅÓê ¢É³êĨèAHðØÁÄò×È¢æ¤É³ê½¬¹½¿ª¹©²ÌãÉu©êAqÇàBÍv¢v¢ÉGÁĢܵ½B ië¯ð´¶Aj¹ßĹJSÉüêÄÙµ¢ÆWõÉðµ½¼ãAÇ¢ñµ½èÍñ¾è³êÄ¢½\o
ª°Éºµ½uÔðÚAﲸõª·®ÉE¢ °ÄWõÉ°½Æ±ëWõªuåävvƾ¢ú¿A»ÌãàqÇཿªp_lY~ðèÌÐçÉRÏÝɵÄVñ¾èAÐæ±ðhÍÝɵÄàÙFµÄ¢Üµ½B
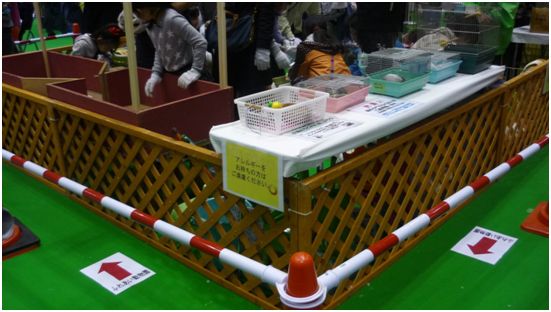 EeBXÅÍíê½Xy[XÉÍ¢LÈOÌlXÈMûÞE¹ÞªW¦³êÄ¢½B
EeBXÅÍíê½Xy[XÉÍ¢LÈOÌlXÈMûÞE¹ÞªW¦³êÄ¢½B
EBeÍJêÔàÈ¢ÔÑä¦ÊHÉl͢ȩÁ½ªAãÉrØêÊ·ÖÌñªB

HØè³êÄò׸AñèY¤\o
½¿B
JSÌü±¤¤Í3H̵ª~ÜèØÉc
| 
JiAA¶¹àGèúèÉÈÁÄ¢½B
ÉÍeíÉüêçê½½ÌqRªc
|
_Þ짡lsàÌÚ®®¨
yW¯Ìf¦zYÆÒÌW¯ªf¦³êĢȩÁ½B
yWõÌlzQ¼
y®¨íÆz~[ALbgUARcJE\PAA}WPAt~bV
WCAgETMSARXUPAREPA
nX^[AV}XAW[rAsO~[nlY~AsO~[}EX¡
@u©ÄAÓêÁÄA¦é®¨vÌLb`Rs[ÅL¼È±ÌÚ®®¨¯ÆÒÍA©ÂÄÀXÜɨ¯é®¨Ì{ÛÇãÌâèÅnæs¯©ç½ÌêAsª§üèÉüÁ½±ÆªbèÉÈèܵ½B
@¡ñÌCxgÅÍA¡ªÌ~[ALbgðW¦iÚGÂjAA}WÌøÁ±ÈÇAì¶RÌ®¨ðÓê ¢ÉpµÄ¢Üµ½Biá½s×ÅÍ èܹñªA®¨Ay[ÌÏ_©çÝÄâèÍÈ¢Ìŵ天Hj

¿µ¢A}WͽÌêÒÉlCª è
½ç¢ÜíµÅø©êĢܵ½B
| 
BêéêàÈlûg§¾ÌT[NÉ
IúüêçêÄ¢½~[ALbg½¿B
|
_Þì§à̬®¨êåX
yW¯Ìf¦zYÆÒÌW¯ªf¦³êĢȩÁ½B
yWõÌlzOiIúsÝj
y®¨íÆz``RC
@u~N®¨vÌÎÊAïêÊH¤ÉÍ2ÂÌP[WÉDFQCÌyAÆF1CÌ``iêÚjªW¦³êĢܵ½ªAWõªIúsÝÅ Á½±Æà èAêÒªP[WÉwðüêéÈǵĢ½Æ«É``Bª¦°fÁĢܵ½B
@P[WÌ¡ÉͱÌÆÒÌ`Vªu¢Ä èܵ½ªAo^ÔâÓCÒ¼ÌLÚªÈA¯XÌEFuTCgãÅàmFÅ«È©Á½×AsÉüPw±µÄ¸«Üµ½B

lÊè½¢ÊHÉW¦³êÄ¢½``B
ißOÉÆÒªÝA»ÌãIúsÝj
| 
BêéêªÈ÷ɦ°Þ``B
@
|
¡ sÉñ…ñÍuÆÒ²ÆÌo^Ôt^vÆW¯f¦`±Ì
çð
@½ÌWqª©ÜêéCxgÉÚ®®¨ÆÒÈǪoW·éÓê ¢R[i[ÍA½Æ¦WõðzuµÄ¢ÄàuåÈpl§ÀvðsíêÈ¢ÀèW¦®¨ÌXgXy¸ð}é±ÆÍ¢ïÅ·BÚ®®¨ÉæéoWð¨T¦¢½¾±ÆªÅPÅ·ªAÈÆàuÆÒ²ÆÌo^Ôt^vÆuW¯f¦`±Ì
çvÍRÅ é±Æ©çACxgI¹ãɺLÌâè_É¢ÄsÉñµA¡ãÌÎÉ¢Ģðßܵ½B
ƼÌAíÊAo^ÔÈÇðLÚµ½W¯i¯ÊÍjªf¦³êĢȩÁ½B
¦åÃÒi\¿ÒjÉt^µ½o^Ի̼ÌîñðLÚµ½W¯ÍïêÌDZ©Éf¦³êÄ¢½ÌÅÍHÆ̱Æŵ½ªAuybgÆÌÓê ¢R[i[vüÓÅÍmF³êĢȢBiN઩¦éAí©èâ·¢êÉÍf¦³êĢȩÁ½Bj
êÆÒɨ¢ÄAW¦®¨Ì{ÛÇ¾ßéu»ÌÚGª\ªÈm¯ðL·éÒðzuÍ»ÌÄÂ̺Év¨±ÈíêĢȩÁ½B
¦_Þì§à̬®¨êåXÍA³lóÔÅ``ðW¦µÄ¢½B
¦u~N®¨vÍAHØèµ½¬¹ðÓê ¢ÉpAºÌඵĢ½B
æêí®¨æµÆÌo^ðsÁĢȢéÆu[Xà¶ÌW¦ðsÁÄ¢½B
¦Ú®®¨ÆÒªfBXvCpÉÝoµð¨±ÈÁÄ¢½B
¡ o^ëª{Å«È¢âèà
@WpybgtFAÉoWµÄ¢½¶ÌW¦ÆÒÌo^îñ{ªÂ\Å é©s®¨¤ìkZ^[ÉmFµ½Æ±ëA·ÅÉpƵĢé½ßöJÅ«È¢Aâ¢í¹Éà¶çêÈ¢ÆÌŵ½B
@±êÍÈO©çâèɳêÄ«½±ÆÅ·ªA®¨¤ìÇ@Éæè{ɳêé±ÆÉÈÁÄ¢éÉàÖíç¸ACxgJÃúÔ̽úÉðÉoü±ÆªÅ«È¯êÎAƼÌAÓCÒ¼AíÊAo^ÔAW¦®¨ÌíÞAªÈÇÌîñðmé±ÆªÅ«È¢AyúxÕúÉo^\¿iyÑpÆÍ̯ñojµÄ¢éÆÒÉ¢½ÁÄÍAÀãAϪūȢÌÅ·B
¡ u1úð´¦È¢ÍÍvÌoÒ¬Ío^E§üèsvIHÚ®W¦ÆÒÌÀÔc¬ð
@{|[gÅÍAÚ®®¨ÆÒÌ®¨Ìæèµ¢à³é±ÆȪçAuCxgåÃÒª¡ÆÒÌÞðÆèÜÆßÄo^\¿ðs¤ÆAåÃÒi\¿ÒjÉo^Ôªt^³êé±Æ©çAeÆÒ̼ÌAÝnAíÊÈÇð¾Lµ½W¯ªf¦³êÈÈévÆ¢¤âèÉ¢Äæèã°Üµ½ªAÚ®ÌEÚ®W¦ÆÒͼÉàÚðü¯é׫âèª èÜ·B
@¤Æ{ÝEZîW¦êÈÇÅ©©¯éAÚ®®¨ÆÒÉæéu®¨Óê ¢R[i[vÌCxgÍyújÕúÈÇÉJóêé±Æª½¢±Æ©çiðÌxÝÆdÈéjAu1úð´¦È¢ÍÍvÌcÆÍAáOð¢ÄuJÃnðÇ·ésÖÌÆÌo^vªÆ³êĢܷªA±êÍ@¥E×Úɾ¶»³êÄ¢éí¯ÅÍÈA«ÈàBÉ·¬È¢àÌÅ·B
@úÀèÌ»s̽ßɼݳê½W¦{ÝÉsEõªoü«AmFðs¤±ÆÍ»ÀƵÄﵢƢ¤ºà èÜ·ªAÆÉY·és×ðs¤SÄÌÆÒÍ®¨¤ìÇ@ÉæèucÆêð·é©¡ÌvÉAæêí®¨æµÆÌo^i×ÚKèð½·{ÝÌ\¢ªOñjð¨±È¤±Æª`±t¯çêĢܷB»Ì½ßA
EcÆúÉæéo^Æðr·éiáOÈo^E§üèàs¤j
EÆÌÍÍð§ÀµAÇææOÌcÆÍ´¥síȢƷéB
EuZúÔÉÚ®ðJèԵȪç¼ÝÌ{Ýɨ¢Äv®¨®¨ÍGꢮ¨ðW¦·é`Ô»ÌàÌðÖ~·éB
¢¸ê©É·éÙ¤ªö½Å è@ÉKÁĢܷB
@³çÉA³o^ÆÒÅÍÈ¢±ÆÌmFA®¨É[ªÈx{ªmÛ³êÄ¢é©Ç©¡ÌªÚ®W¦EÚ®ÌÆÒÌcÆÀÔðc¬·é½ßÉàîñ¤LÌû@ð¢·éKvª éÌÅÍȢŵ天B
¦Hiq¶@ɨ¢ÄÍA¼ÝcÆðs¤êÅàucÆêðÇ·é©¡ÌvÖÌÂ\¿ðvµAÂÌÍÍà§ÀµÄ¢é©¡Ìª½¢B
¼ÝcÆÉ¢ÄÌptbg
http://www.city.sendai.jp/business/d/__icsFiles/afieldfile/2010/07/14/kasetsu.pdf
¢©®ÔÉæéHiÖWcÆÂÉ¢ÄÌptbg
http://www.city.sendai.jp/kenkou/seikatsu/food/contents/pdf/kurumapanhu_27.8.pdf
yÆ뮨z
`C^[ybg@rWlXEtH[ñ`
ybgÆEÌu¡vÆÍ
@uC^[ybgvÆÍA¡NÅTNÚð}¦éú{ÅåÌÛybgYÆ©{sÅAÙÆíR{[VÉæèybgrWlXÌìðL°éAlÆybgÌV½ÈCtX^CÌñÄðRZvgÉA2011NÉJóêĢܷBïÍA2014NæèAybgYÆEÌ®üÆíªÉLb`Abv·é½ßɯCxgðKêA±êÜÅÉàïñu`khudvPPREPPTÅÆè °ÄÜ¢èܵ½B
@¡NVPUúÉàAuybgYÆ̾颢ðÇÌæ¤Éï»»·é©IH`[J[AµA¬AbãNjbNAwZ¼ÍA¡A½ªoé©`vÆ¢¤e[}ÌàÆAC^[ybgÌrWlXEtH[ªAJóêܵ½Bïñm`khudnPPUÅͱÌCxg©ç©ÑãªÁÄ«½ybgYÆEÌu¡vðÆè °Ä¢Ü·BÚµÍïñ116ð²¾³¢B
¦È¨A©úV·Ðª^c·éybgîñMTCgurvÉ{eÒWLªfÚ³êĨèÜ·B
@@http://sippolife.jp/issue/2015103000002.html
¦2020N2ÇL
©úV·Ðª^c·éybgîñMTCgurvÉfÚ¸¢Ä¢éïÌïñÒWL̤¿A2015N716úÉJóê½C^[ybg@rWlXtH[ÌÀÔðñ¶½{e¾¯ªí³êĨèܵ½ÌÅAȺÉS¶fÚ¢½µÜ·B
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
`C^[ybg@rWlXEtH[ñ`
ybgÆEÌu¡vÆÍ
uybgYÆ̾颢ðÇÌæ¤Éï»»·é©IH@`[J[AµA¬Abã
NjbNAwZ¼ÍA¡A½ªoé©`vÆ¢¤e[}ÌàÆAçÌghâ
AuybgYÆ̾颢ðÇÌæ¤Éï»»·é©vÆ¢¤cèÅplfBXJb
VªsíêAeÆEÌÖWÒªMSÉc_³êĢܵ½B±ÌCxgÅ©Ñã
ªÁÄ«½ybgYÆEÌu¡vðȪȪç²ñ³¹Ä¢½¾«Ü·B
¡¢ÌÝÈç¸Là窸Xü©Aë@´ðøÆE
@±êÜÅïªñÉí½èsÁ½²¸ÉæèAybgYÆEÍ¢ÌçªÌ¸É
ë@´ðø¢Ä¢é±Æªí©ÁĢܷªA±ÌtH[ÅàAêÊÐc@lybg
t[h¦ïÌÅV̲¸iQOPSNjðàÆɵ½à¾ª èANA¢Ì窪
¸µÄ¢éÆ¢¤ñªÈ³êܵ½B
@ܽALÌçªÍQOOVN©çÏ»ªÈA¡Î¢-÷ÌXüÅ Á½àÌÌ
AQOOVN©çä×éÆqLÌ窪¸ÁĨèA13ÎÈã̪ÈÁÄ¢
é±ÆÉ¢ÄAqî»Ìe¿ª éƾy³êĢܷB¢Æ¯lA±ÌÜÜÅÍ
Nã©çLàçªÌ¸ªnÜéÌÅÍÈ¢©AÆ¢ë@´ðøÆEÌOª
´¶çêܵ½B
¡uwZÅÌøÁ±Ì@ïvÅêÚêIHçªðâ·ÆEíª
@plfBXJbVÅÍAbãtE¬EwZEybgpiÈÇÌÆEÖWÒªo
dµA¼OÉȳê½çªÌ¸É¢ÄÄÑc_ªnÜèܵ½BÆEÖWÒÌÓ
©Í±êÜÅÊèA
EîÒÆqÇàÉÅ_ðÄÄA¢©É±Ì^[QbgÉ®¨ðçµÄà礩
EÇÌæ¤ÉÌHðgå·é©
Æ¢¤bèªSÆÈÁĢܵ½B»ÌÈ©ÅAâÍè±±ÅàA
uàÁÆCyÉÉBÅ«éæ¤É·×«v
uÆEƵÄAêÚêAøÁ±·é@ïðâ·½ßÉAwZðÜßÄ
l¦È¯êÎÈçÈ¢v
ÈÇÌïÌIȾª èAÆEÌûü«ÍÏíÁĢȢ±ÆªmF³êܵ½B
@uybgYÆ̱ê©çÉ¢ÄvÌcèɨ¢ÄÍAybgÌçªðâ·½ß
ÉAlÞç¬â¿ÌüãAÙÆíÆÌR{[VgåAnæïPAVXeÌ\
zAÈÇÆ¢¤bµªÈ³êܵ½Bµ©µAqî»Alû¸Ai·Ìgåin¢
âèjc ú{A»µÄàÁƬKÍPÊÌnæÐïÍÏÌúð}¦Ä¢Ü·B
@±¤µ½È©ÅA®¨ÉεĻÌðÛáµAuK³vÉ{Å«éêÊÆëÍÀ
çêé±Æª\z³êÜ·ªA±Ìæ¤ÈybgÆEÌíªÍ»óɦµ½àÌÈÌŵ
天BÆEªf°éuybgÆ̤¶vÌ^ÌÚIÉ¢ÄA¡ãLêÊÉümð}
ÁÄ¢Kvª 軤ŷB
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¦ïª|[gµ½ C^[ybg@rWlXtH[ÌàeÍÀÅ·B
@ ybgîñTCguybggD[vlÅà¯lÌ|[gðfÚ³êĢܷÌŲÄࢽµÜ·B
ybgÆEÌ¡ðaéC^[ybg rWlXEtH[ 1
@ https://petomorrow.jp/news_dog/5489 æèê²
ug[NZbVJn¼ãAܸÍXàVªwçªÏ»@¢xÌf[^É
ÚBu¢Ì̸ª±¢Ä¢éÆ¢¤Æ±ëÍAñíÉë@´ðo¦Üµ½B»ÌÈ©Åàq¢Ìª·²¸ÁÄ¢évÆ»óÉ¢ÄRgB
³çɱ¯ÄuSÌƵÄFBÌƱëÉq¢ª¶Üê½Æ©Aà¢Ä½ç½Ü½Üq¢ÆoïÁ½Æ¢¤±Æª¸µÄµÜÁ½±ÆªAq¢ð¤`XªÈÈÁ½Æ¢¤vöÉÈÁÄ¢éÌ©àµêÈ¢B¶á ¡©çâ¹Ü·©H¡©çìÇ¢âµÜµå¤ÈñıƾÁÄàÈñÌÓ¡àÈ¢BE¤`Xðâ·ÈñıÆÍūȢŷËB¾Æ·éÆAÆEƵÄÍAoï¤`XAêÚê·éAøÁ±·éAÆ¢Á½±ÆðÓ}IÉǤâÁÄâµÄ¢Ì©AÌÙ¤ð»·éÌÆí¹Äl¦Ä¢±ÆªåÈè§ÄÉÈéÆv¢Ü·vÆq×½Bv
yÆ뮨z
u¢LEª[ðÚw·cõA¿vÌï@QÁñ
@¢LÌEª[ðß´·cõA¿iÊÌFnbs[[cAjÍA¡NQÉݧ³ê½´}hÌcõA¿Å·Bï·ÍöÒGvQc@cõi©¯}jA±Ç·ÍݸÙQc@cõiЯ}jÅA50¼ÈãÌïcõÌûXª¼ðAËĢܷBcõA¿Ìݧ͡NÅ·ªAðN©çݧõïðJ÷éÈǸÍIÉ®ð³êĢܷB
@VUúÌïÍ¡ãÌcõA¿Ì®ûjðßé½ßA®¨âèÌêåÆâs¯cÌðµ¢ÄA»ê¼êªø¦Ä¢éÛèÈÇðqAOµAÓ©ð·â®væðbµ¤½ßÉJóêܵ½B±ÌxAï̱êÜÅÌ®ð]¿µÄ¢½¾«AuõÅsíêéqAOɨº|¯ð¸«Üµ½B
¡ ^ÉEªðÈ·½ßÉ
»êÅ®³êÄ¢éûXÉæéîñMAV·âerÈÇÌñ¹ÈÇlXÈ`Å¢LEªâèªæèã°çêA¢LÌEªâèͽÌûXªméƱëÆÈèܵ½Bµ©µA¢¾É13ªÆ¢¤cåÈÌ¢LªEªÆ¢¤ßµ¢Hð}¦Ä¢Ü·BܽAuEª[v̾tªÆè૵Ģé»óà©ó¯çêéæ¤ÉÈèܵ½B±¤µ½ÀîðÓݽãÅAïÍ^ÉEªðȵĢ½ßÉïÅodµAºLÌð¨bµ³¹Ä¢½¾«Üµ½B
iv|ÌÝfÚAÚ×Íïñ116ð²¾³¢Bj
@ næLÎôÌiAÁÉâèÉæègÞûÉηéöIx
@@i¢LÈOÌ®¨É¢ÄàÎôðu¶éKvª éj
A ÀqÌ¢ð¸ç·XÈéæègÝÌi
B êí®¨æµÆÒɨ¯éu®¨ÌæègÝvÌ@§»
¦¼cÌAL¯ÒA»ê{eBAÌûX©çàA®¨ªµÈ¢æ¤È`ÅEªð¸çµÄ¢±ÆðÚwµÄ¢×«Ì¨bª èܵ½B
yW¦®¨z
~R®¨Ì}[O}uEb`[vÌSÌÉ¢Ä
@2015N725úA~R®¨É¨¢Äè30ÎÈãÌÌ}[O}uEb`[vªSµ½ÉÖµADys·Æ~R®¨·¶ÄÉv]ðño¢½µÜµ½B
v]ÌS¶Í±¿çÌy[Wð²¾³¢B
@Eb`[ÌSÌÉ¢ÄADys®¨ÇZ^[iȺFZ^[jÍA~R®¨Eõ©çÌî®æâ§ü¸ðÜÞ²¸ðs¢AW21úÌLÒï©Åu~R®¨ÉüP©ðsÁ½v|ð\µÜµ½B
@üP©ÌàeÍAuàSÄÌ®¨ÉWéÇ̧̩¼µAKvlõÌmÛAvæâ}j
AÌ®õvuSEõÖ̳çðüßÄÀ{·é±Ævu{ÝÌ_À{ÈçÑÉüP[uðu¶é±ÆvÅA®¨ÌNâÀSð۵ȪçA“gDƵĔ®¨ÌK³{ðs¦éæ¤É·é½ßÌàÌÅ·BܽA±Ì©ðó¯A~R®¨ÍüPÊÉ¢ÄX30úÜÅÉZ^[Éñ·é±ÆðßçêĢܷB
@ܽAZ^[ÍAüP©¾¯ÅÍÈAkC¹x@ÖîññðsÁ½±Æð¾ç©ÉµÜµ½B±êÍA®¨¤ì@æ44ðæQÌuµ½®¨ÌKØÈÛìðsíÈ¢±ÆvÉY·éÂ\«ªl¦çêé½ßÅ·BipfÅ éÆv¢Üµ½Bj
@Eb`[ÌöÍAaðUÌÊA°ÇÌ¡uwjAÅ é±Æª»¾µÜµ½BEL`Æ̬ÌÊA]ªÜêA»Ì]ª¡uðúEµ½ÌÅ·B¯Pû̬ÌÊÅ é±ÆÍA~R®¨àFßĢܷB
@Z^[ÍAu¯PûÌÀ{É ½èAgDƵÄ\ªÈO¢Aîñ¤LAÓvèªsíêĢȩÁ½±ÆvðwEµÄ¢Ü·B~R®¨Ì“gDƵĔÌüPÊÉ¢ÄÍA¡ãàµÄ¢«½¢Æv¢Ü·B
@¡ñÌÄÍAC^[lbgãÅÌîñMiÁÉ®¨EIb`[ÌûXÉæéjªAø«àÆÈèAå«ÈbèÆÈèܵ½Bµ©µAbèÉàüPÉàÂȪé±ÆÈAâèáðø¦ÈªçcƵĢ鮨W¦{ݪSÉ é±ÆàYêÄÍÈçÈ¢Æv¢Ü·B
@±êÜÅàASenÉ éN}qêÅÍAN}¯m̬ÉæéS̪¶µÄ«Üµ½BiÅßÅÍAQOPSNAF{§ÌJh[h~jIiE¢hN}qêjɨ¢ÄAÒÌÚÌOÅAaÌæè¢ÉæéN}¯m̬ÉæèAN}ªSµÄ¢Ü·BjܽAl×IvöÉæéÆvíêéW¦®¨ÌSÌÍA¼ÉàN«Ä¢Ü·BbãtsÝÌW¦{ÝའèÜ·B
@Eb`[̲»ðFéƯÉA®¨W¦{ÝÌ èûðª{IÉ©¼·úÉ«Ä¢éÌÅÍÈ¢©Æv¢Üµ½B
y®¨À±z
®¨À±ÁĽ¾ë¤H
Ú×ͱ¿çÌy[Wð²¾³¢B
y®¨À±z
k¢åwbãwÖ¿â^v]ño i̳úEj
Ú×ͱ¿çÌy[Wð²¾³¢B
yCtX^Cz
Sðü·ÔÃ@ |upCvuEB[v
ÇÞE©éE· | èªÆ¤À±®¨½¿
CtX^C©¼µKnow How | éxÅAj}EFtFA
X̶UU |ÁïåÌÓC
| uALIVEvobNio[ÌÐî |
|





![]() @ALIVEÌÐî@
@ALIVEÌÐî@![]() @춮¨@
@춮¨@![]() @Y[¥`FbN@
@Y[¥`FbN@![]() @Æ뮨@
@Æ뮨@![]() @{Y®¨
@{Y®¨
![]() ®¨À±
®¨À±
![]() ¶½Ï
¶½Ï
![]() CtX^C
CtX^C
![]() ®¨Ûì@
®¨Ûì@![]()
![]() @¿W@
@¿W@ ![]() @rfI@
@rfI@ ![]() @ïñuALIVEv@
@ïñuALIVEv@![]() @æèµ¢}@
@æèµ¢}@![]() @Ql}Ðî@
@Ql}Ðî@![]() @N@
@N@![]() @¨â¢í¹@
@¨â¢í¹@![]() @¿¿
@¿¿