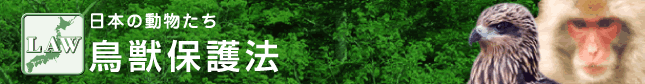鳥獣保護事業の実施に関する基本指針(案)に関する意見の募集について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7615
期間:平成18年10月21日(土)~平成18年11月19日(日)17:30まで
=========================================================
[件名]鳥獣保護事業の実施に関する基本指針案に関する意見
[宛先]環境省自然環境局野生生物課 御中
[氏名]地球生物会議代表 野上ふさ子
[意見]
<該当箇所>
Ⅰ 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
第一 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する基本的な考え方
1 基本的な考え方
狩猟は、単に資源利用としての捕獲という側面だけでなく、鳥獣の個体数調整の手段として、鳥獣による被害の未然防止に資する役割を果たしているが
<意見>
「現代における狩猟は、主にスポーツや趣味・娯楽として行われているが、鳥獣を捕獲するという限りにおいて鳥獣の個体数調整の手段として、鳥獣による被害の未然防止に資する役割も果たしている」と修文する。
<理由>
狩猟で生計を立てている人はほとんど存在せず、おおむね趣味やスポーツとして行われている。狩猟の現実を正しく指摘しなければ、基本方針自体が間違うことになる。
以下、狩猟に関する記述はすべて修正するべきである。
<該当箇所>
2 地域における取組の充実
(1) 実施計画の作成の推進
<意見>
都道府県は、関係市町村が捕獲許可を実施計画に基づき実施する場合、「速やかに捕獲情報を都道府県に報告し、」特定計画に定められた目標数の達成が図られるよう、また捕獲上限数が超過しないように、必要な指示を行うものとする。
と「 」内を追加する。
<理由>
2004年、2006年のツキノワグマの捕殺数に見られるように、計画があっても目先の有害捕獲が優先し、たちどころに捕獲上限数を超えてしまう。捕獲情報は毎日、毎週、毎月の単位で報告するものとして、放獣の技術や場所の選定などを事前に協議し、捕獲数の上限を超えないように市町村に適切な指示を行うべきである。
<該当箇所>
第六狩猟の適正化
1 基本的な考え方
<意見>
鳥獣の科学的・計画的な保護管理「のためには、適正に狩猟が行われることが重要であり、(略)狩猟による鳥獣の捕獲等が鳥獣の個体数管理に果たす効果等を客観的に検証していく必要がある。」と「 」内のように修文する。
<理由>
現状では、狩猟を監視する機能はほとんどなく、錯誤捕獲の報告義務もなく、捕獲統計も数字のみで実数に即しているかも不明である。このような状態では狩猟によって鳥獣の科学的・計画的保護管理がなされると断言できるのか、根拠が疑わしい。
<該当箇所>
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
(3) わなの使用に当たっての許可基準
<意見>
(3) わなの使用に当たっての許可基準
①獣類の捕獲を目的とする許可申請の場合
「原則としてくくりわなととらばさみは使用しないものとする」とするべきである。
<理由>
くくりわなととらばさみは、錯誤捕獲の可能性が高く、放獣する場合に動物が暴れるなどして取り扱いに高度な技術を要する。時には麻酔をかける必要もある。放獣が困難であるために結局死なせる例が多い。放獣が困難で人にも危険なくくりわなととらばさみは、それ自体を禁止するべきである。
<該当箇所>
②イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする許可申請の場合
<意見>
捕獲の方法は、狩猟においても許可捕獲においても変わりはない。それにもかかわらず許可捕獲の方は規制がゆるく方法に差異がある。一般にはその差異が理解されておらず、しばしば混同されている。許可捕獲も狩猟の規制と同等の扱いをすべきである。
<該当箇所>
③ヒグマ及びツキノワグマの捕獲を目的とする許可申請の場合
はこわなに限るものとする。
<意見>
「筒型(ドラム缶式)のはこわなに限るものとする」と修正するべきである。
<理由>
鉄格子状のはこわなにかかったクマは、鉄棒を歯で噛みくだこうとするため歯を折ったり口部に損傷を受ける。中が暗い筒型の檻であれば、不必要な外部刺激を軽減させ口に損傷を与えることが少ない。
<該当箇所>
(4) 許可に当たっての条件の考え方
<意見>
「有効期間内に目的とする捕獲数に達した場合は、速やかにわなを撤去すること、また期間を延長する場合は、その都度わなの標識を付け替えることとする。わなの設置個数は1日に1回以上見回り可能な個数とする。」と「 」内を加え、修文する。
<理由>
有効期間を過ぎても自動延長させて1年中捕獲している例が多々見られる。有効期間の切れてもその上に上書きするなどして期限を偽ることがなされないように、期限が切れたらその都度、標識を付け替えさせるべきである。
<該当箇所>
(5) 許可権限の市町村長への委譲
<意見>
「鳥獣の捕獲許可に係る事務を市町村に委譲した場合は、市町村における捕獲情報を少なくとも月ごとに都道府県に報告するように求め、そのデータを整備して常に全域における最新の捕獲情報を入手するように努めるものとする。」を追加する
<理由>
都道府県は、1年に1回年度末を過ぎてから市町村の捕獲の数字を集計しているため、リアルタイムでの捕獲情報を持つことができない。そればかりか、市町村から上がってきた数値が正しいものであるかどうかをチェックする仕組みもない。さらに、都道府県レベルの集計が遅いために国の鳥獣関係統計の集計も2~3年後に公表されることになり、実態把握が常に後手に回っている。少なくとも月ごとに報告を求め集計をしていくべきである。
<該当箇所>
(7) 捕獲物又は採取物の処理等
<意見>
「特にニホンザルの捕獲個体は、違法捕獲や違法売買を防止する観点から、1頭ごとに個体の顔の写真を取り頭数確認のうえ、速やかに現地で処分すること」を追加する。
さらに、錯誤捕獲した個体については「可能な限り放鳥獣すること」を追加する。
<理由>
ニホンザルの捕獲には府県や市町村で1頭あたりの報奨金をつけているため、実際の捕獲数よりも多い数が報告されている場合がある。捕獲個体1頭ごとに識別できるように顔写真を添付するべきである。またそれによって違法捕獲や違法売買の防止効果を期待できる。
錯誤捕獲は、原則すべて放鳥獣しなければならないことを明記すべきである。
<該当箇所>
(8) 捕獲等又は採取等の情報の収集
<意見>
捕獲等又は採取等の実施者に対し、実施した地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物、捕獲努力量等についての報告を「求めるとともに、専門家あるいは大学研究機関等に委託して事業報告書を作成すること」と、「 」内を追加する。
<理由>
捕獲の許可権限が市町村に委譲されて以来、県では鳥獣の保護管理に関する必要な情報をほとんど収集しなくなり、ましてそれに基づく調査や分析など不可能となっている場合が多い。市町村からの報告を求め、そのデータを専門家あるいは大学研究機関等に委託して事業報告書を作成するべきである。
以上




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求