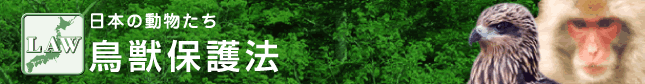【意見1】
<該当箇所>
10ページ 9~21行
<意見内容>
ノイヌ・ノネコについては、狩猟鳥獣から除外すべきである。
<理由>
ノイヌ・ノネコについては、鳥獣法上では条文上、明確な定義づけがありません。大日本猟友会の「狩猟読本」においては、ノイヌ・ノネコとは「直接人の力を借りずに、自然界で自活し、繁殖しているもの」と書いてある一方、「首輪がついていないからといってノイヌと見做すのは早合点である」「飼い主が所有権放棄した犬もノイヌではない。その犬は単に所有者のいない家犬にすぎないから、そのような犬の処理は他の法令に拠る行政措置(保健所業務)に任せなければならない」とも明記しています。さらに、ノネコについて「人家から離れたところで猫を見ても、気軽にノネコを判断してはならない」とあります。しかし、実際には、年間300頭を超える数の犬・猫が、狩猟や有害駆除で殺されています。
装薬銃や空気銃で殺されるケースもありますが、くくりわなや箱わなに捕獲された後の、ナイフでの刺殺や水没殺も横行しています。動物愛護法では、人の占有の有無を問わず「愛護動物」である犬・猫が、一方では狩猟者や駆除申請者の一存で殺処分されている実態があるのが現状です。
迷子や逸走した犬・猫も、わな等で錯誤捕獲される場合がありますが、狩猟者・駆除従事者の自己判断によって、その場で処分されてしまうことがあります。犬や猫がわなにかかった場合には、必ず、自治体の動物愛護担当部署に連絡をし、保護できるような体制を構築する必要があります。
殺処分ゼロ(犬・猫)へ向けての取り組みや、譲渡推進や啓蒙活動等、動物愛護行政が努力しているなかで、ノイヌ・ノネコの問題は長年放置されてきました。狩猟鳥獣からノイヌ・ノネコを外すことは必須と考えます。
【意見2】
<該当箇所>
29ページ 30~33行
<意見内容>
とらばさみは、有害駆除も含め、全面禁止にするべきである。さらに、旧式のとらばさみは、全自治体において回収をするべきである。
<理由>
とらばさみは、狩猟では禁止されましたが、有害駆除、或いは自分の敷地内において内々に使用され、犠牲になる動物が後を絶ちません。様々な動物種が、とらばさみの犠牲になります。錯誤捕獲があっても、とらばさみにかかり興奮状態にある動物を放獣することは非常に困難です。野生動物だけではなく、放れている飼い猫や野良猫等も、とらばさみの犠牲になっていることが報告されています。
有害駆除等で、とらばさみにかかった動物の処置も、安楽な方法では困難なことから、撲殺や刺殺等の方法がとられています。
また、とらばさみを未だに店頭販売しているホームセンターや小売店もありますが、販売するにあたり、有害鳥獣捕獲許可証の提示等も徹底されず、誰でも購入できてしまうという実態があります。インターネットでの通信販売も行われており、一部に、意図的に猫等を捕獲したい人等も購入している通報もあります。
さらに、旧式のとらばさみ(緩衝装置がついていないもの、鋸歯のもの)を所持し、違法に使用する事例も報告されています。最近では、市民公園において、標識のない旧式とらばさみが何者かによって設置され、タヌキが犠牲になった事例もあり、警察も捜査をしている事例もあります。旧式の危険なとらばさみについては、自治体の呼びかけ等により回収されるべきと考えます。
【意見3】
<該当箇所>
30ページ 21行目
<意見内容>
医学・薬学における学術研究の目的のために、野生動物を捕獲することに反対する。
<理由>
ニホンザルにおいては、過去、有害駆除等で捕獲された個体が、大学の医学部等に違法に譲渡されていた事例が、新聞やテレビ等報道で大きなニュースになったことがありました。日本霊長類学会も、医学分野において、野生由来のニホンザルを使用しない声明を出しています。野生動物を、医学等の目的に実験動物として使用するリスクは、医学に携わる専門家も危惧している現状があります。何より、自然のなかで生きる野生動物を、人間の医学目的のために捕獲し研究の材料とすることに、大きな違和感を覚えると共に極めて遺憾です。
【意見4】
<該当箇所>
36ページ 18~37行
<意見内容>
野鳥の愛玩飼養を、全面禁止すべきである。
<理由>
メジロやホオジロ、ヒバリ、ウグイス等の野鳥の愛玩飼養については、全国野鳥密猟対策連絡会が中心となり、長年にわたり、警察と連携しながら取り締まりを行ってきました。今もなお、摘発される野鳥の違法飼養・違法流通があるなかで、「野外で野鳥を観察できない高齢者等のために」野鳥飼養を認めることは許されません。メジロ等の鳴き合わせ会・飼養等にかかわるのは、まさに高齢者が中心で、隠れ蓑を法的に作ることに強く反対します。
【意見5】
<該当箇所>
37ページ 26~34行
<意見内容>
伝統的な祭礼行事等で、鳥獣を致死させることに反対する。
<理由>
21世紀になっても、未だ、鳥獣の殺生を伴うような祭礼行事があるのであれば、内容を改めるべきです。文化は、常に、時代にのっとった倫理観と寄り添うべきと考えます。
【意見6】
<該当箇所>
49ページ 27~30行
<意見内容>
鳥獣保護管理員については、選考方法を公募とし、鳥獣保護の各分野について専門性のある人物を採用すべきである。
<理由>
鳥獣保護管理員については、総数の7割以上が猟友会で占められています。しかし、一方で環境省は、鳥獣保護管理員の新たな役割として、鳥獣保護管理についての助言・指導や、鳥獣に関する環境教育への活動の充実、専門性の担保等も課題としてきました。
一人の鳥獣保護管理員が、すべての内容を網羅して活動することは困難であり、各分野における専門性を有する人材を鳥獣保護管理員に任命するためには、猟友会に依存した現体制を抜本的に見直し、選考の方法から変えていくことが必要です。
鳥獣保護管理員については、公平性・透明性のある公募制をとり、専門知識や技術を有する市民に参加してもらう体制に移行すべきと考えます。
【意見7】
<該当箇所>
51ページ 32行 ~ 52ページ 38行
<意見内容>
傷病鳥獣については、獣医師、民間団体等との連携、地域住民の参画等を普及啓発することに、大いに賛同する。一方、地域によっては、連携できる団体や参画できる地域住民等が乏しい地域もあることが否めないことから、「生命の尊厳」を重視し、さらに教育上・倫理上の問題を考慮し、自治体で定める救護対象種外の種であっても、一定の流れができるまでは、自治体で原則救護すべきと考える。
また、救護ボランティア制度については、講習や研修の義務付け、面接や適性判断を行うことが望まれる。
傷病鳥獣の追跡調査・個体識別については、可能な限り行われることが望ましい。また、放鳥・放獣が困難である個体について、終生飼養が余儀なくされるケースにおいても、第三者に譲渡できないような仕組みづくりも重要であると考える。
<理由>
傷病鳥獣救護の問題を考える際、「野生は野生のままに」という冷静な視点も必要であると思いますが、人為的要因である事故や化学物質汚染、開発等、彼らも様々な危機に常にさらされているということも考慮すべきと考えます。「生物多様性の保全」という観点から、傷病鳥獣救護というテーマは重要である一方、忘れてはならないのが、「倫理・教育」の視点であると思います。目の前で苦しんでいる動物を目撃した時に、「何とかしたい」と思うのは、人の本能といって過言ではありません。これを無視して、傷病鳥獣に関する施策を進めていくことは不可能です。
傷病鳥獣を保護し、行政で「救護対象種ではない」と告げられた側が、青少年である場合はどうでしょう。傷病鳥獣との付き合いの中で、命の大切さや野生鳥獣を取り巻く現状等様々なことを学んでいくのであれば、傷病鳥獣救護は重要な環境教育といえるのではないでしょうか。
救護ボランティア制度については、現在半数以上の自治体が設けています。しかし、「講習や研修を義務付ける」「面接や適性判断を行う」等の条件を設けている自治体は多くありません。野生鳥獣を扱うにあたり、ボランティアに対し、講習・研修を行うことは、本人及び当該動物の安全や、人獣共通感染症等の予防の上でも非常に重要と考えます。
傷病鳥獣の追跡調査・個体識別を行うべきという意見の裏には、国内における様々な野鳥の密猟・違法飼養が問題になっているという現状があります。実際、密猟者や違法飼養者は、様々な言い逃れをするケースがありますが、「傷病だから」と偽る事例も報告されています。
多くの自治体が、傷病鳥獣として保護収容した個体について、個体識別を行っていません。さらに、追跡調査や確認も行っていないことも明らかになっています。少なくとも、国内希少種、また違法流通の事例が数多く報告されている非狩猟鳥のメジロ、ウグイス、ホオジロ、フクロウ等の種については、足環等の個体識別を実施することが必要です。
また、野生復帰が厳しく、終生飼養となる個体について、当該鳥獣を第三者に譲渡させないこと等のように、ボランティアから第三者への委託・譲渡を禁止(監視)する事項を、自治体において定めることが必要であると考えます。
以上
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求