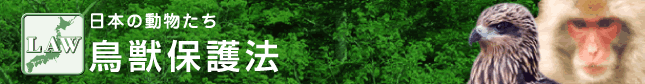●請願制度
請願は、憲法で保障されている国民の基本的権利の一つで、国民が国政に対する要望、、苦情等を直接国会に述べることができる。日本国籍を持つ者、日本国内に在住の外国人なら誰でも提出できる。
※憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
※請願法(昭和22年3月13日 法律第13号、昭和22年5月3日 施行
)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L013.html
|
なお、参議院と衆議院とは、それぞれ別個に請願を受け付け、審査される。
●請願書の書き方
請願は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所(住所のない場合は居所)・氏名を明記する。請願者の氏名は自署によることが原則。ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要。また、外国語や点字などで書かれた場合には、翻訳文を添付する。
●請願できる期間
請願は、国会の会期中、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間、いつでも提出できる。
ただし、請願の案件がすでに当期国会で審議されて通過した法案である場合は、受理されない場合もある。
●請願書の提出
国会への提出は、議員の紹介がなければ出せない。提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行う。
請願者は1名でも可能。請願者は1名でも10万人でも同じ一件として取り扱う。同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできない。しかし、請願者が異なっていれば、同一内容の請願をいくつ出してもよい。(例えば1万名の署名簿を請願代表者100名にわけて100件として出すことができる。この場合、種類は1件となる)
●紹介議員
請願署名を受け取った議員は自分の名前を紹介議員名として署名し、参議院・衆議院の各請願課に提出する。
案件によっては、議員は自分が所属する政党の政務調査会等に紹介し、党として請願を受けるかどうかの判断を受ける場合もある。政治的に論議のある案件については、議員個人が賛同であったとしても、党が「党議拘束」をかける場合もある。
●委員会に付託
請願課は、受理した請願書の文体を公文書スタイルに書き換え、請願のタイトルを付けて、その趣旨、請願者の住所・氏名、紹介議員名などを記載した請願文書表を毎週作成し、全議員に配付する。
また、請願課は、請願の趣旨に応じて、いずれかの常任委員会または特別委員会に付託する。野生生物法ネットの請願は、環境委員会に付託された。この間の実際の事務手続きは、参議院、衆議院の各環境調査室において行われ、環境調査室の担当が資料を添付して各理事などに説明に回ることもある。
※不適正行政により具体的な権利・利益の侵害を受けたとして、その救済を求めることを内容とする請願(苦情請願)については、行政監視委員会に付託される。
●請願の審査
付託を受けた委員会では、付託された請願について審査を行い、採択すべきかどうか決定する。一般に、請願は法案の審議が終了する会期末頃に、委員会にかかることが多い。(時間がないため実質的審議はほとんど行われないまま「審議未了」とされる場合がほとんど。)
衆議院では今現在、3500件くらいの請願が出されている(同じ内容のものが多い)が、厚生労働、文部科学にかかるもので請願の大半を占める。環境委員会に関わる請願は、今国会ではこの野生生物保護法の請願1件のみ。環境委員会にかかる請願自体の数が非常に少ない。
●審査の結果
法制度上は、請願は各委員会で採択か不採択かを決定されることになっているが、慣例的に不採択はこの37年間、一度もない。実質は「不採択」だが、保留扱い(審議をしない、棚上げ)として、国会の会期終了に伴い「審議未了」となる。
●請願の採択
委員会で採択された請願は、内閣に送付することが適当か否かをそれぞれ決定し、議長に報告する。議長は、これを本会議に諮り、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、内閣に送付する。
●内閣処理経過
内閣からは、毎年おおむね2回、その処理経過について参議院に報告する。
●請願状況の公表
国会にかかった請願の表題は、採択、審議未了を含め、すべてインターネットで公開されている。
誓願が採択されても、これを立法化する等の法的根拠はないが、国会で認められたことを行政機関は完全無視はできない。また、採択されなくても、さらに継続して請願を行い、議員に問題を認知してもらうよう努力していくことも大切である。
●採択、不採択(審査未了)の例
(第151回国会(平成13年度)環境委員会にかかった請願の例から)
◎参議院・衆議院採択「自然環境権の確立に関する請願」受理件数1、請願者32976名
◎参議院採択「霞ヶ浦における環境ホルモンについての調査研究及び解明に関する請願」
◎審査未了「名古屋市の藤前干潟をラムサール条約に登録することに関する請願」受理件数4件、請願者1500名
【参考】参議院のサイト「請願情報」から
第151回(平成13年1月~6月)国会に紹介提出された請願は、2,892件(150種類)であり、このうち特に件数の多かったものは、「小規模作業所等に対する成人期障害者施策に関する請願」207件、「食品衛生法の改正及び運用の充実強化に関する請願」205件、「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の早期成立に関する請願」131件などであった。
各委員会への付託件数は、内閣250件、総務65件、法務210件、外交防衛24件、財政金融309件、文教科学229件、厚生労働1,435件、農林水産1件、経済産業141件、国土交通138件、環境29件、議院運営8件、災害対策30件、倫理選挙21件であった。
取り下げられた請願は2件(付託前1件、付託後1件)であった。
請願者の総数は2,019万4,533人に上っている。
平成13年6月27日及び28日、各委員会において請願の審査が行われ、5委員会において264件(12種類)の請願が採択すべきものと決定された。次いで29日の本会議において「自然環境権の確立に関する請願」外263件が採択され、即日これを内閣に送付した。
今国会における請願採択率(採択件数/付託件数)は、9.1%であり、また、種類別の採択率(採択数/付託数)は、8.0%であった。




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求