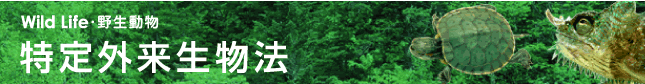|
移入種問題と動物福祉
皆さんは、移入種問題というのは、アライグマ、ブラックバスに代表されるように、人によって持ち込まれた後、自然界で繁殖し生態系を乱す「動物の」問題、というイメージをもっていませんか?
ひとくちに移入種問題といっても、その内容は動物から植物まで幅広く、問題の種類も、生態系のかく乱から農業等の経済活動への影響まで様々です。導入の経路も意図的なもの、非意図的なものがあります。しかし、動物の移入種に限って考えると、問題の大半は、原産地や導入先の生態系や動物本来の生活を無視したやみくもな利用、取引に起因しています。
もしも私たちが、「野生動物は野生のままに」という理念にしたがって行動し、こうした動物の利用や取引を自制してゆくことができれば、本来そこにいないなずの動物の野生化による問題のおおかたは防げるはずです。総理府の世論調査(2000年)では、国民の過半数がこの理念に賛同しています。
国内に定着している移入動物にしても、もし私たちが、「最後まで責任をもって飼育する」という飼い主責任を全うしていたなら、遺棄や逸出による野生化は起こらなかったでしょう。改正された『動物愛護管理法』は動物の福祉と適正管理という面から、飼養者責任を強調しています。
移入種問題にとりくむにあたり、もっとも大切なことは、問題を発生させている根本原因にさかのぼって、実効性ある対策を組み立ててゆくことではないでしょうか?
動物福祉とは?
Q 動物福祉とは何ですか?
動物の立場にたって、彼らの生活の質を高めようという考えで、世界動物保護協会の宣言文では、「福祉とは動物の身体的、行動的、精神的な要求の充足度をいう」と定義されています。
具体的には、不必要な殺傷や苦痛を与えることをできる限り避け、動物を飼育する場合はそれぞれの種が本来もっている行動パターンを自由に発現できるよう配慮を行います。英国で家畜福祉の目標として生まれ、その後、世界獣医学会で採択された「5つの自由(Five
Freedoms)」は、現在、国際的な動物福祉の標準として各国の法令に反映されています。
動物福祉の原則:5つの自由
(1)飢えと渇きからの自由。
(2)不快からの自由。
(3)痛み、傷害、病気からの自由。
(4)正常な行動を示す自由。
(5)恐怖と苦悶からの自由。
Q 人間の生活とどんな関係がありますか?
動物福祉は人間に本来備わっている倫理観にねざすもので、生活の中で動物とかかわりをもつあらゆる場面に関係します。そのため、先進諸国や多くの発展途上国で、動物福祉法が整備されつつあります。これらの法令は、家畜やペット、実験動物、展示動物の飼育、取り扱い、健康管理、輸送、訓練・調教、食用となる動物の屠殺、安楽死の方法などにおよんでいます。
Q 野生生物問題とどんな関係がありますか?
野生動物については、捕獲の基準と方法、取り扱い、輸送、飼育管理、展示する場合は展示施設の飼育基準が動物福祉にかなっているかどうかが問題になります。とくに有害鳥獣の駆除に際しては、捕獲の正当性と有効性、またその方法が人道的な(動物福祉にかなった)方法であるかどうか、動物の受ける苦痛を最小限に抑える努力をしているかどうか等が求められます
Q 日本の現状はどうですか?
2000年12月より改正『動物の愛護及び管理に関する法律』が施行されました。この法律は、他の先進諸国と比較すると規制が緩やかですが、動物福祉の理念が随所に盛り込まれ、また本法に基づく各種の基準は、人の占有下にあるあらゆる動物の適正な飼養管理を義務づけています。また、ペットショップ、ブリーダー、動物園など?種の動物取扱い業者の責任も明確にしています。野生動物と関連の深い順に、動物取扱業の基準。展示動物の基準、ペット等の家庭動物の基準、実験動物の基準、産業動物の基準?動物の処分方法に関する指針があります。
移入種問題と動物福祉
Q 動物福祉の考え方は移入種問題の解決に役立ちますか?
移入種問題の発生に至るまでには、入り口、中間、そして出口があります。入り口
とは動物の輸入や移動、中間とはこれら動物の飼育にかかわる各種の業者・飼養者、出口とは、これらの動物の遺棄あるいは逸出です。
動物福祉の観点からすると、まず、動物を住み慣れた環境から遠隔地に連れ出すこと自体、福祉に反することといえます。輸入や国内移動の際の長距離輸送も動物にとって大変過酷で、高い死亡率、疾病発症率をもたたらすため、多くの国が長距離輸送を規制しています。輸送を無事に終えた個体も、新しい環境に適応できなかったり、種に固有の生理・生態・習性を無視した劣悪な条件で飼育されるケースが多く、外国から持ち込まれる珍しい動物の飼育は、ずっと以前から動物福祉上の問題となっています。先進諸国ではこうした動物の販売基準や飼育基準を厳しくすることにより、問題の発生を減らそうとしてきました。そして、飼育動物の遺棄は多くの国で犯罪です。
動物の脱出防止についても、多くの国が動物福祉法の中で飼養者の義務としています。
このように、移入種問題の発生に至るまでの経路のあらゆるところで、動物福祉の問題がすでに発生しており、これらを規制する法令の枠組みができています。したがって、この観点からの規制を強め、上手に運用することによって、多くの移入種問題を未然に防ぐことができるのです。
Q 動物愛護団体は移入種対策に反対ではないのですか?
動物愛護団体というと、特定の動物種を何が何でも殺すなといった主張をするというイメージが流布されています。考えや方針が異なるさまざまな団体がありますが、「動物福祉」の考えにそった活動をしている団体の大半は、野生生物保護の必要性も理解しています。
しかしもしも、「移入種=撲滅」というような、短絡的で、言葉づかいにも配慮のない問題提起をすれば、動物愛護、あるいは動物福祉をうたう団体の多くはこれに反対するでしょう。なぜなら、問題発生に至るまでの過程に全然ふれず、彼ら自身も被害者である動物だけに不当な責めを負わせているからです。仮に愛護団体に加入していなくても、一般に無益な殺生を嫌う国民感情から、とくに情に訴えやすい動物種については反対の声があがる可能性があります。また、移入・外来・エイリアンといった用語についても、よそ者排除の意味合いから、人権問題への無理解をうかがわせることになりかねず、使い方には慎重さが求められます。
生物多様性条約の締約国会議の決議にもあるように、実際の移入種対策においては、駆除はあらゆる手段を尽くした後の最終措置であり、その前にやるべきこと、できることが多くあります。そうした防止措置は、生態系や人間の生活を守るためであると同時に、動物の福祉をも守るものでなければなりません。この点を双方がよく理解しあうことが大切でしょう。
すでに入り込んでしまった移入種については、1)その動物と共存する道はないか、あらゆる角度から検討する。2)現実的に可能で福祉にかなったコントロール方法を模索する。というステップを踏むことが必要でしょう。沖縄県では、ヤンバルクイナを捕食するノネコの問題については、「適正飼育が野生動物を守る」という観点で、地域の住民への理解を広げている事例があります。被害地域での捕獲処分の他、不妊化放獣、条件付きの終生飼育、教育を兼ねた収容施設での飼育等も視野に入れ、市民が自ら方法を選べる形を作り、皆が協力して、確実に効果をあげる道をつくることが大切ではないでしょうか。
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求