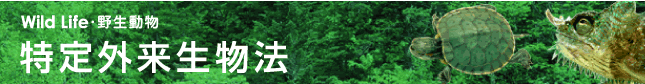野生動物の輸入・飼育が引き起こす問題
何よりも「水際規制」が必要
野上ふさ子
ALIVE No.51(2003.7-8)
現在、日本には昆虫を含め、年間8億匹という数の野生動物が輸入されているとのことです。その目的は農業用、実験用そしてペットなどです。人の手によって行われている動物の大移動は、さまざまな問題をを引き起こしています。
動物種別輸入状況(H13年)
| 関税法による貿易統計から |
フェレット |
31,583 |
| ハムスター |
1,005,488 |
| リス |
67,066 |
| プレーリードッグ |
13,407 |
| 哺乳類以外の動物 |
781,521,400 |
| 感染症予防法による輸入検疫実績 |
サル・霊長類 |
6,670 |
| 狂犬病予防法による輸入検疫実績 |
犬 |
12,097 |
| 猫 |
2,400 |
ペットショップに行くと、犬や猫ばかりでなく、プレーリードッグ、フェレット、トカゲやカメ類、カブトムシなど、さまざまな野生由来の動物が売られています。どんな動物でも売り買いしたり飼育できるというのは人の「勝手」なのかもしれませんが、そのために、以下のようなさまざまな問題が引き起こされており、今や法律で規制しなければならないところまできています。
野生動物の輸入や飼育には、以下のような問題があります。
1、生息地の生態系破壊
野生動物を捕獲することは、その地域の生態系を破壊することも意味する。野生動物にはそれぞれの生態系に占める位置があり、過剰捕獲によって食物連鎖が乱されるなど、他種の絶滅まで引き起こすおそれがある。
2、捕獲・輸送に伴う高死亡率
捕獲時のショック、ケージでの監禁、長距離移送のストレス等で、相当数の個体が病気になったり死亡する。野鳥類は8割もが輸送中に死亡すると言われている。1999年のオランウータンの密輸事件では7頭のうち3頭が途中で死亡している。
3、個体への虐待
本来の生息地から全く異なる地域や環境に連れ込まれることは、その動物の生理的機能にもダメージを与える。熱帯産の動物を気候・風土の異なる日本で飼うこと自体が、不自然。
4、飼育困難による死亡・遺棄
飼育者がその野生動物の習性や生態を知らないことから起こる飼育困難。不適切な餌を与えたり、必要な運動や飼育環境を与えることができなかったりして、衰弱死させたり、持て余して捨てたりする。
5、在来種への圧迫
捨てられた大部分の個体は、環境に適応できずに死ぬが、中には野生化して農作物被害を引き起こしたり、在来種を捕食して生態系をかき乱したりする場合も起こる。
6、感染症の拡散
野生動物が保有するウイルスなどが人間にとっては病原性を持つ場合があり、感染症をまき散らす恐れもある。最近の例では、感染症予防の観点からプレーリードッグが輸入禁止とされた。
このように、野生動物のペット飼育は、野生動物の捕獲によって、その生息地を破壊し、種を絶滅においやったりすることになります。また生まれ故郷や仲間から引き離してケージに監禁し、異なる環境につれてくることで、不幸な目にあわせ、さらには捨てられたり、果ては駆除されるなど、悲惨な末路を与えることになりかねないものです。
野生動物をペットとして飼育することは、人の「勝手」ではなく、「身勝手」な行為というべきでしょう。自然を大切にし動物の福祉を考える立場からすれば、原則として、野生動物の輸入・飼育は禁止されるべきだと思います。
法整備の遅れ
残念ながら日本には、動物の輸出入や飼育を規制する法律がほとんどありません。以下のような現行法があるのですが、それぞれの官庁が縦割りで、ごく限られた部分しかカバーしていないのが実状です。
▼税関(財務省が所轄)では、貨物の数量が統計対象で、機内携行動物は対象外。(関税法)
▼動物の検疫(農水省)はウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ウサギ、アヒルなどの家畜と家禽類などの限られた動物のみ。(家畜伝染病予防法)
▼感染症予防による検疫(厚労省)で、犬、サル、アライグマなどごくわずか。(狂犬病予防法、感染症予防法)
▼ワシントン条約(産業経済省)では付属書I類しか対象となっていない。(種の保存法)
生物多様性の確保の観点から外来(移入)種動物の輸入を規制できる法律はまだ存在していません。
日本はタイやインドネシアなど東南アジアの国々から大量の野生動物を輸入しています。一方、これらの国には家畜伝染病として恐れられている口蹄疫がまんえんしており、日本では東南アジア諸国からの家畜の輸入は全面禁止しています。口蹄疫は空気感染もするウイルスであり、どんな動物に付着して入ってくるかわからないにかかわらず、野生動物の輸入はフリーというのは理不尽なことです。ひとたび、このような脅威的な感染症が国内に入ってきたら、すべての家畜を殺すということになりかねず、倫理的にも経済的にも大きな問題となるでしょう。
動物問題ではしばしば、床にあふれる水を雑巾で拭くより先に、まず水道の蛇口を締めようと言われます。問題がこれ以上広がる前に、まず水際規制が必要なのです。
水際規制のために必要な措置
国内に持ち込まれた動物が逃げ出したり捨てられたりして野生化した場合、それを捕獲するためにはたいへんな時間と費用がかかります。感染症もひとたび広がってしまったら、原因の追及から治療法まで限りない労力が必要となるでしょう。
それを考えれば、島国である日本では輸入の際の水際対策が最も効果的です。また、動物の管理よりも人間の行為の管理の方が、意志疎通できる分、ずっと容易なはずです。対策には次のような措置が考えられます。
(1)輸出入の実態把握と規制強化
- 輸出入時、種名と数、販売目的等の項目を設け、税関貿易統計に記載する
- 機内携行の場合も、種名、数、目的の届出(自己申告)を義務付ける
(2)動物販売業者の規制
- 輸出入業者、ブローカー、販売業者を登録制にする
- 動物取扱業を許可制にする(動物の愛護及び管理に関する法律の改正)
(3)個体登録制の導入
- 絶滅危惧種、危険動物種、移入種、感染症媒介種等を指定して個体登録制にする。その場合、都道府県における担当窓口を一本化する。
(4)動物飼育者の責任制
- ペット飼育者に関する研修制の導入
- 飼育動物の遺棄、放棄の監視と罰則の強化。
- 動物取扱業者に対する研修・ライセンス制の導入など
放棄・遺棄・捕獲された動物の保護について
空港で、動物の密輸が摘発されると、その動物は「所有権放棄」され所轄の行政の所有になりますが、そのあと、それらの動物の取り扱い方法が定められていないため、また業者に払い下げらるような状態となっています。そこからペットショップに流れて売られているのでは、いったい何のための水際規制かわかりません。各地の動物園に引き取りが依頼されて、動物園が渋々受け入れていることも多いようです。
また、有害な移入種として捕獲された動物をどうするのかということが常に議論の的となります。動物保護の観点からは、以下のような対策が必要だと考えられます。
- 公共の保護収容施設を作り、動物への理解・環境教育の場にしていくこと、
- 動物園に受け入れを依頼する場合は、動物福祉の観点からの施設基準を設けること。
- 動物園における飼育動物の種・数・飼育スペース等のデータベースを作成し、どこが受け入れ可能かの判断を迅速にすること。
- 小動物の場合など飼育可能な施設や個人ボランティアの登録制を設けること。
- 衰弱等で回復困難な場合の安楽死の措置を設けること。
水際規制や飼育規制が強化された場合、一時的に放棄・遺棄・捕獲される動物が増えることも予測され、このような取り扱いついてのガイドラインについても、同時に制定していくことが求められます。
 参考:飼育動物関連法の図 参考:飼育動物関連法の図
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求