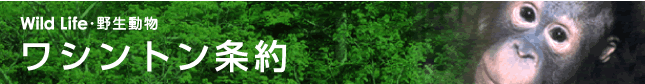この2月2日に、大阪のペットショップが密輸したオランウータン等が、原産国インドネシアに返還されました。当会では、昨年5月にこの事件が起こって以来、関係各方面に様々な働きかけをしてきたところです。
返還に先立つ1月29日、第3回目のオランウータン集会を、インドネシア大使館の後援を受け開催しました。集会にはインドネシア政府の自然保護当局ならびにオランウータン・リハビリセンターの責任者の方々5名が来日、オランウータンの保護に関するスピーチをされました。会場は満員で、この問題に関する国内外の関心の高まりを反映し、テレビ、新聞等の取材が多数あり、報道されました。
私たちは、今後とも彼らの野生復帰のプロセスを見守り、またその生息地の保全についての関心を向けていきたいと思います。
『オランウータンの返還によせて』
NGOと協力して野生動物保護を
いま地球環境の保全がたいへん重要な問題になっている。今回、日本の政府やNGOの努力でオランウータンが返還されることになったことをよろこばしく思う。この事件が教えたことは絶滅に瀕する野生生物を守ることの緊急性である。彼らを守るためには規制や法律の強化の他に、貧困や無知、欲望に対して、啓蒙活動や環境にやさしいライフスタイルを考える教育を徹底させることが重要だ。また政府と非政府機関が協力して動くことも大切だ。インドネシアでは絶滅のおそれのある種や野生生物の保護に非常に力を入れている。オランウータン、コモドドラゴン、スマトラトラ、バリムクドリなどの貴重種はエコシステムを保全する意味でも重要だ。しかし、わが国は貧困と無知という問題にも直面している。このセミナーでは具体的な提言をしてほしい。大使館は日本の非政府機関との協力をおしまないつもりだ。オランウータン返還に努力した日本政府、密輸業者を摘発した当局に深い感謝の意を表する。また飼育してくれた神戸の王子動物園に感謝する。
民主党の環境部会長として環境委員会で「種の保存法」をなぜ適用しなかったのか環境庁に質問した。諫早干潟がムツゴロウの存在で象徴されたように、オランウータンも絶滅する種の危機を象徴している。昨年動管法が改正されたが、この程度の改正で次世代への責任を果たせるだろうか。人間中心の今の日本社会のあり方が問われている。環境権や生態系、自然に生かされる人間という教育が大切と思う。これをきっかけとして、今後も国会の中でさらに議論を深めていくつもりである。
インドネシアにおけるオランウータンの
保護ならびに保全に関する政策
インドネシアには非常に多くの生物が住み、哺乳類は世界の12%が生息している。しかし今、生息地の消失、気候の変動、人間による自然破壊などによって多くの生物が生存を脅かされている。カリマンタンでは、過剰な開発と伐採により生息地が消失し、違法な伐採や耕地開発によって生息地が分断されている。密猟では赤んぼうを取るために母親が殺されている。密輸出も多い。肉も売られている。このままでいくと2010年にはオランウータンはほとんどいなくなる。生息地の消失、分断、狩猟、火事、干ばつ、出産率の低さ、病気などが要因だ。
少なくとも現状を維持するにはどうしたらいいかのアクションプランを考えている。保護活動を進めて充実させる。カリマンタンの保護地域を新たに作る。生息地間の回廊を作って交流をはかる。スマトラに新たにヒハビリセンターを作る計画をしている。観光ではなく啓蒙活動を行う。リハビリセンターの存在は野生のオランウータンの保護に問題があるということを意味しており、本当はリハビリセンターに1匹のオランウータンもいなくなることが望ましい。オランウータンは、生態系の頂点に立つ種であり、その保護が成功すれば他の種の保護も成功するだろう。
オランウータンの保護はインドネシアおよび世界の遺産を保全することである。BOS基金が運営する東カリマンタンのワナリサット・リハビリセンターは、オランウータンの野生復帰を目的とし、運営はインドネシアの法律に則って行われている。保護した動物の福祉と健康をはかり、野生個体のリリースはIUCN(国際自然保護連合)の規準に則っている。個体保護のために空輸システム、病気の伝染を防ぐための隔離施設や病院もある。亜種などの研究にも力を注いでいる。野生個体を生息地に戻す場合、新たに個体群を作ることになる。オランウータンの保護とエコシステムの保全のためには、地元の人への教育活動や国際協力も大切である。国際的な支援団体がアメリカ、オランダ、イギリスなどにある。日本の人々とも協力していきたい。
ワナリサットでは、これまでにリハビリを終えたオランウータン176頭をミラトスという所でリリースしている。大阪から返還される4頭は、検疫の終了後、「中途の家」に移す。そこは10ヘクタールほどの果物がたくさん成る木が植えてある土地で、木登りや食物の取り方、社会性を身につけさせる。人の顔は見えないようにしてある。この観察を通してリリースのタイミングをつかむ。
BOS基金によるリハビリセンターのやり方は新しいものだ。検疫施設を設け、個体の記録を取り、群れで飼育する、観光客を入れない、法律に従って運営する等である。ワナリサットには5人の獣医師と6人の熟練した医療スタッフ、70人の飼育スタッフがおり、病院、検疫施設などを備え、24時間の医療ケアができる。結核、肝炎、寄生虫等の病気を調べ、スタッフにも厳しい衛生管理を行っている。リリースには、野生個体がおらず、人もいなくて、しかもオランウータンが生息可能な場所を選ぶ。リハビリセンターは、政府の林業農園省森林食糧課の管轄で、現地の人々に果物の成る木を植えてもらっている。大人のオランウータンも保護している。訪問者には厳しい制限を加えている。観光客は入れない。しかし学校の生徒や子供を受け入れ、研究者や専門家には公開している。
森林の保全を第一に
1997~98年に飛行機でオランウータンの生息地の調査をしたが、私の調査の結論は、現在東カリマンタンのオランウータンの生息地は極めて限られ、生息数は2000~3000頭と推定している。ワナリサットに入れられた数は700頭に達しているが、そのうち30%以上の個体が死亡している。しかも、西カリマンタンや中央カリマンタンの個体も入れられている。私は、ここで亜種の問題の解明を求めたい。これは今後リハビリ個体をどこにリリースするかの問題に関わる。まず、
カリマンタン島のオランウータンの亜種の調査を両国研究者によって編成することを呼びかけたい。また、東カリマンタン、クタイ北部の石灰岩山地帯の分布地にはより強力な保護の手が差し延べられるべきであり、新たな保護地あるいは国立公園の拡大が計られる事が望ましい。亜種問題が確定出来るならば、収容個体はそれぞれの原産地での森林に戻されるべきものだ。特に国立公園周辺の地域の残されるべき森林は温存され、リリース用の森として活用されるべきであろう。
今回の事件が残した課題について
今回の事件は、日本にはいかに容易に野生動物を密輸できるかということを明らかにしたもので、税関や環境庁は実態について把握するべきである。また、警察の取り締まりを効果的に行えるように、保護した動物を収容する施設を整備する必要がある。種の保存法では原産国へ自らの責任で返送できることを定めているが、この返送命令が出されたことは一度もない。返送には、費用だけではなく、生息国の適切な施設を指定、運送の責任も負っている。日本としてもそうした情報を積極的に集めてすぐに対応できる体制を取るべきである。
世界で哺乳類鳥類150種の野生化が計画実施されたが、成功例はわずか16例で、野生復帰はそれほど困難である。ワナリサットのリハビリでは新しい個体群を作ることであるが、現存する個体群を増強することの助けにはならない。日本の行為が野生の個体群に致命的な損傷を与えていることを反省すべきである。
オランウータンの返還が多くの人の協力で返還されたことは喜ばしく思う。通産省は管理当局として今後も議論を尽くしてやっていきたい。
今回の事件は今後の教訓にしなければならない点が多々あると思っている。収容先については、動物園の関係者と話し合って当面は対応していかなければならない。今回の返還はいちばん効率的だったと思うが、今回のケースをもって今後法律の摘要を一切しないというわけではない。今後とも消費国と原産国のそれぞれの関係当局、あるいはNGOが手を携えてこういった問題が再発しないように対応を取っていきたいと思う。
オーストラリアでも野生動物の違法取引には水際の監視に積極的に取り組んでいる。武器、野生動物、薬物のブラックマーケットは非常に大きな利益を生み出すもので、取り組みは極めて重要である。ワナリサットの教育プログラムなどはそういった問題を解決する一つになるのではないか。
日本は野生動物の輸入大国であり、インドネシアからの輸入量は15%で最大である。昨年12月にはスローロリスやベンガルヤマネコも密輸された。オランウータンが野生のまま生きていけるようにするためには、生息国では密輸を取り締まり生息地を保全するとともに、消費国の日本では密輸入を厳しく取り締まる必要がある。今回返送命令を出すことができなかったのは非常に残念だ。政府は厳しい姿勢で法律を行使していただきたい。




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求