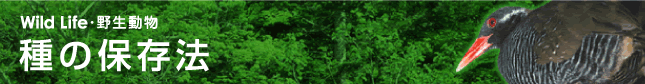1993年に制定された「絶滅のおそれのある動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)は野生生物を絶滅から守ることを目的としています。この法律は、国際的に希少な野生生物の商取り引きを規制するワシントン条約(CITES)の国内法としての役割と、日本国内で絶滅に瀕している野生生物の取り引き規制と生息地保護という二つの役割を持っています。
《取り引き規制の強化を》
【問題点】
密輸品の流通をチェックできない
野生動物は生きた個体としてばかりでなく、体の一部や製品としても取り引されます。日本は国民一人当たりワシントン条約対象種の消費量が世界第一です。私たちに身近なものとして象牙の印鑑などがあります。1970~80年代の象牙の印鑑ブームによって、アフリカで80%のゾウが殺されたと言われます。
現在、象牙市場は香港が第一、日本が第二ですが、香港からの加工品輸入を加えると日本が世界一の消費国となっています。南部アフリカ諸国は日本をターゲットにして象牙の売り込みをはかり、この四月にケニアで開かれているワシントン条約会議では規制の緩和を求めて攻防が繰り広げられています。
象牙ばかりでなく、トラの骨、クマの胆、ワニ革、べっこう製品など、日本人は多くの動物製品をぜいたくや迷信によって消費し、その結果、動物を絶滅の淵に追いやっています。種の保存法で、原材料から製品に至るまでの流通過程を追跡する仕組みを作らない限り、違法捕獲や密輸製品のチェックはほとんど不可能な状態です。
違法取引に対処できない
昨年大阪で起きたオランウータン等の密輸事件で判明したように、この法律には違法取引に対処する実効力がほとんどありません。具体的に言えば、次のような問題があげられます。
1.違法取引の動物を発見しても、税関で没収できない。
2.生きた個体が任意放棄された場合、国の保護収容施設がない。
3.生きた個体の原産国への返送規定が適用された例がない。
4.ワシントン条約付属書IIの種に対しては何の規制もない。
《緊急保護施設の設置を》
【問題点】
保護して死なせる状況
税関で動物の違法輸入が発見された場合、強制的に没収できる規定がありません。実際は、大部分の動物が任意放棄され、そのまま動物園や動物業者に保管が委託されます。その数は毎年増大し、どこの動物園も、もう受け入れは困難と言っています。
税関をくぐり抜け国内で違法取引が発覚して警察に摘発された場合、警察は動物を証拠物件として押収しますが、やはり動物を緊急保護する施設はどこにもありません。いくら警察が違法取引を摘発しても、押収した動物を保護する施設がないために、結局は空しく死なせてしまうのでは、この法律の意味が失われてしまいます。
【問題点】
保護のために予算を使うべき
絶滅動物を守るというのであれば、国の予算で保護施設(シェルター)を設置するか、または既存の施設に委託管理を委ねる費用を出すべきです。
放棄された希少動物のために検疫や治療、ケアを行えるような適切な施設を作ることは、世界中から金にあかせて希少な野生動物を輸入しまくっている日本の国としての最低の責務ではないでしょうか。さらに、違法に密輸された動物については、原則として原産国(地域)または適切な飼育施設に返還することとし、そのために原産国の支援を行うことも、ODA(政府開発援助)の仕事の一つとすべきではないでしょうか。
また、施設の運営費用の一部は、違法行為を行った者に請求して負担させ、密輸は割にあわないことを知らしめて、再犯の抑止力とすべきと思います。
《動物取扱業の規制を》
動物を取り扱う業者は、昨年の改正動管法で自治体への届け出制とされました。これで、業者の実態はある程度把握できるでしょうが、業の規制がどの程度できるかは不明です。
とりあえず、法改正に伴い公布される政令で、動物取扱業の中に、ワシントン条約対象種(I類、II類を含む)や種の保存法対象種を取り扱う業、危険動物を取り扱う業を指定すべきです。
最近は、猛禽類のペット飼育がブームになっていますが、これらはほとんどがレッドデータブック(RDB)にも記載されている絶滅のおそれのある種です。従って、届出の書式に、取り扱う生物の種名、RDB記載種、数、購入先、販売先等を記入させ、実態の把握や追跡調査ができるようにするべきでしょう。
《国内希少種の保護を》
国内の希少野生動物の保護についても、この法律では実効力がほとんどありません。
【問題点】
保護すべきほ乳類はわずか二種
まず、指定対象種の数が少なすぎるのです。環境庁が出している絶滅のおそれのある種として「レッドデータブック」に記載されているのは、ほ乳類は六八種、鳥類は一三二種です。ところが、「種の保存法」で国が保護すべき種としているのは、ほ乳類ではツシマヤマネコとイリオモテヤマネコのわずか二種にすぎません。鳥類も三九種しか指定されていません。
しかも今、種の保存法で保護されるべきイリオモテヤマネコ(国の特別天然記念物でもある)の生息地の国有林までもが農地開発で脅かされているのです。トキのように最後の1羽になってから保護のために何十億円もかけるより、今、まだ間に合ううちに、予算を使うべきではないでしょうか。
【問題点】
地域個体群の概念がない
野生動物は単独の個体として保護するだけではだめで、その地域に住んでいる個体群として保護されなければ絶滅してしまいます。例えば、西日本(中国山地)に住むツキノワグマはわずか一五〇頭前後と言われています。このクマたちはもはや中部山岳地帯や東北地方のクマと行き来はできません。人間の住む都市空間に囲まれ、生息地が孤立し分断されているのです。西日本のクマの絶滅は目前にせまっていますが、日本全体ではまだ絶滅ラインに達していないから、絶滅危惧種に指定はしないというのでは、その地域の生態系を保持することはできません。 種の保存法の中に生物多様性を維持するという概念を導入し、地域個体群を保護する仕組みが必要ではないでしょうか。
【問題点】
生息地の保護もできない
指定種にすると生息地の保護も行わなければならないので地元の利害関係が絡んでむずかしいと言われます。しかし、イリオモテヤマネコは絶滅危惧種に指定されていながら、国と沖縄県はヤマネコの生息地を開発しようとしているのです。これではいったい何のための法律と言うべきでしょうか。
開発による目先の利益と長期的環境保全の釣り合いについては、もっと幅広くさまざまな立場の人々の意見を採り入れて決めていけるような仕組みを作ることが必要不可欠と思います。




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求