| 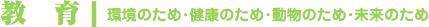
全ての生物が平和に生存できる世の中の実現に向けて
動物への思いやりと共感をはぐくむ
ヒューメイン・エデュケーション(Humane Education)について(その1)
角 恵美 (アメリカ在住 教育学/建築学)
「もし人が正しい道を望むなら、最初に自らに禁じなければならないことは動物たちを傷つけることである。」 トルストイ
「全ての生きものに対して慈しみの輪を広げるまでは、人は心の平和を得ることはできないだろう。」 シュバイツァー
|
今、世界は複雑な現代社会が作り出した様々な害悪のためにバランスを失いつつ
ります。そして、地球上のあらゆる生き物がその犠牲となり、不安や苦痛に悲鳴をあげています。
身近な生活や行動の中に潜む悪弊を払拭して事態の悪化を防ぎ、命あるもの全てにとって平和で安全な世界を構築するための意識改革と自助努力が、私たち人間一人一人に今こそ求められます。
世の中の行方は教育が左右するといわれますが、このような状況への機敏な対応が教育界にも緊急テーマとして課せられます。
全ての生き物が共生・共存可能な世の中の実現に向けた能力と実践力のある市民の育成を目的とする教育が、今ほど必要とされるときはないのではないでしょうか。
■人間性を高める教育の必要性
アメリカには、バランスを崩した世の中への予防薬とでも言うべき教育があります。これはヒューメイン・エデュケーションのことで、学校やコミュニティーにおいて幅広い年齢層の人々を対象に行われています。ヒューメインは、思いやりや慈悲といった人間の最善の性質を備えている様子を表す言葉で、日本語の
「人を高尚にする、人道的な」などに当ります。エデュケーションは、意図的な働きかけをすることによって人を望ましい方向へ変化させること、つまり教育のことです。ヒューメイン・エデュケーションとは、生命に対する敬意、思いやり、責任感、それに自分も社会改革に貢献できるという意識を持ち、人情味豊かな生き方ができる人材を養成することです。
人権、動物擁護、環境保全など自由かつ公正な社会には不可欠な相互関連する諸要素を学び、自分と他者、動物、自然環境との公平な関係を包括的に追究することを通じて、現代社会のあらゆる問題に適切に対処することがこの教育の狙いです。
人格教育、平和教育、多文化教育、環境教育といった他の学問と重なる部分もありますが、この拡張的な教育の特徴は、単なる知識の伝達を図るのではなく、その理論と実践において自分を含む全ての生き物とそれらを取り巻く自然環境を大切にする道徳的態度を育て、思いやりの輪を広げることに重点を置いている点です。
■動物との関わりから
ヒューメイン・エデュケーションが包括的な学問として認識されるようになったのは比較的最近のことで、それまでは動物虐待防止など動物福祉の観点から一般に広く知られていました。現在でも、動物擁護の分野においてかなり高い知名度があります。
ヒューメイン・エデュケーションの歴史は、19世紀後半にマサチューセッツ動物虐待防止協会(Massachusetts
Society for the Prevention of Cruelty to Animals)の創設者ジョージ・アンゲル(George
Angell)が全国の児童・生徒に広く紹介したことに始まります。彼は、動物虐待を防止する鍵を握るのは教育であると考えていました。そして、動物に対する正義感と思いやりを学んだ子供は、公平で倫理的なおとなに成長することも確信していました。
アンゲルは1882年、全国の学校において『バンズ・オブ・マーシー(Bands of Marcy)』というクラブの結成に着手し、子供たちが動物のことを学び、動物のためになる活動を行うことを促進しました。その後、「あらゆる面で全国の学校と家庭にヒューメイン・エデュケーションを導入するために」と、アメリカン・ヒューメイン・エデュケーション協会(AHES)を発足させます。この協会の働きによってバンズ・オブ・マーシーはさらなる発展を遂げ、1923年までに14万以上の団体において400万人以上の子供たちが入会しました。
さらに、アンゲルはAHESを通じてアンナ・シュウエル(Anna Sewell)の代表作、小説『黒馬物語(Black
Beauty)』など思いやりを題材とした本を学校に広く普及させました。そして、ヒューメイン・エデュケーションは1922年までに、20州において必修科目に指定されました。
このような出だしのよさには、多民族国家の子供たちに共通する文化と道徳心を持たせる上で学校教育が担う役割や、主な社会問題の解決に教育制度が重要な役目を果たすという概念が提唱された時代的背景も関与しています。その後しばらく、政治的派閥などの影響によりヒューメイン・エデュケーションの発展は停滞しますが、1960年代になると、大恐慌や世界戦争の影響も薄れ、人々は再び他者や環境との
関係に疑問を抱き始めます。この頃から環境に対して関心が払われるようになり、それに応えるようにして、ヒューメイン・エデュケーションは環境的な視野を取り入れることとなります。
近年、家庭内暴力やその他の罪を犯した者が、幼少期に何らかの動物虐待を行っていたというケースが数多く報告され、その後の様々な研究結果により子供の動物虐待行為とあらゆる社会犯罪との強いつながりが明らかになりました。心理学の分野でも、動物虐待は幼児期から成人するまで継続して現れる精神障害のひとつであると確信されています。よりよい人格と人間関係を構築するために、動物との好意的な関わりを通じて子供に動物を尊重し思いやる態度を教え、暴力行為を防ぐことの重要性があちこちで主張され始め、ヒューメイン・エデュケーションはますます注目されるようになりました。
■教育カリキュラム
ヒューメイン・エデュケーションは今日、全国に存在する多数の人道協会や福祉団体により様々なカリキュラムと教育方法で行われており、その主な供給
源は引き続き地域のアニマルシェルター(動物保護施設)やSPCA(動物虐待防止協会)などの動物保護・管理を目的とする動物福祉団体です。多くの場合、地方自治体や地域社会との提携や米国人道協会(HSUS)などの全国的な組織からのサポートを受けて
実施されています。
動物保護施設の多くは、保護を必要とする犬、猫、小動物などが後を絶たず、収容されている動物への対応に追われ、教育を施す時間とスタッフがないというのが現状です。また、ヒューメイン・エデュケーションの理論は比較的単純ですが、その実践には現行の教育制度の枠組みの中での活動を強いられる複雑さと困難を要します。それにもかかわらず、ますます多くの動物保護団体が、止まない動物虐待や社会犯罪の実態とその対策への教育の有効性に気づき、市民が動物に対する敬意、責任感、思いやりの行動を学ぶことの必要性を強調するようになりました。そして、動物のことだけでなく社会を前向きに変化させていくための人材育成を目的とした革新的なプログラムを行う動物福祉団体も増えてきています。
最近では、リーダーや教育者(ヒューメイン・エデュケーター)などの指導者養成のためのオンライン教育やオンサイト研修を行う団体、教育プログラム作りやその設置を支援する団体、それに専門能力の再開発やネットワーク作りを目的とした組織なども、数多く存在するようになりました。中には、ウェブサイト上にカリキュラム、授業計画、授業用教材など役立つ資料を無料ダウンロード可能な形で掲載している団体もあります。
アニマルシェルター見学、サマーキャンプ、放課後や週末の活動、学校やコミュニティーにおける出前授業、ボランティアプログラム、授業計画や授業用教材の配布など、ヒューメイン・エデュケーションの形態はそれを行う団体や指導者の数だけあるといっても過言ではありません。良質で効果的なプログラムや教材に共通していえることは、知識と情報が最新かつ正確であること、わかりやすい例を取り入れた興味のわく授業であること、対話型の授業であること、教育を受ける側に適切なレベルと内容の授業であること、課題に対して追求可能な選択肢があることなどです。
自分とは異なる存在への理解と関心を高めて、動物や環境とより充実した関わり方を促進するために、扱う課題によっては文化的な相違を考慮することも大切です。
⇒(その2)に続く
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求
