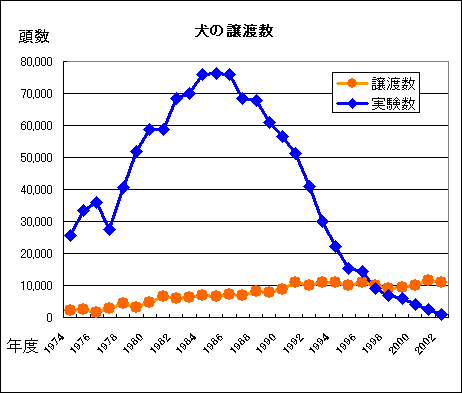犬猫の処分数の減少に向けて
ALIVE 2005.9.3
■犬猫の処分数の推移
この統計は、1974年から2003年度までの過去29年間の行政による犬猫の殺処分数を示しています。
行政による犬猫の処分の根拠には、次の2つの法律が関わっています。
・狂犬病予防法(1950年、昭和25年公布;厚生労働省所轄)
・動物の愛護及び管理に関する法律(1973年、昭和48年公布;環境省所轄)
動物愛護法(動物保護法)が施行された1974年度から、法で定められている「犬猫の引取」数と処分数について、全国統計が取られています(環境省)。
現在、動物行政を所轄している自治体は、都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市であわせて105自治体です。(平成15年)
一方、狂犬病予防法に基づく犬の「抑留(捕獲)」の統計は、厚生労働省が都道府県単位で取りまとめています。
犬の登録数は毎年増加していますが、それと反比例して殺処分数が減少しているのは、社会全体の意識の変化によるものであり、草の根の動物愛護、保護活動の成果であると思われます。
一方、残念ながら猫の処分数は、この10年以上、ほとんど変化がありません。
■行政による犬の捕獲
狂犬病予防法は、戦前から戦後にかけての狂犬病のまんえんという事態を受けて、公衆衛生の観点から定められ、犬の登録と予防注射の義務、犬のつなぎ飼いの推進、放浪犬の抑留(捕獲)、輸出入犬の検疫、狂犬病発生時の犬の拘留命令など、犬と飼い主に対する強い規制を設けています。
現在、多くの自治体で動物行政が衛生部局(保健所)におかれているのは、この時代の名残です。
放浪犬、迷い犬、のら犬などは、この法律に基づく自治体条例によって捕獲されています。捕獲されて施設に抑留された犬は2日間公示され(張り紙が出されるだけ)、飼い主が引取りに行かなければ、3日目には処分されることになっています。
全国(都道府県)における抑留犬の処分数は、毎年、所轄の厚生労働省が統計を出しています。
戦前、戦後における犬たちの状況は実に悲惨なものでした。放浪犬や迷い犬は片端から捕獲されて撲殺されたり、硝酸ストリキニーネによって無差別に薬殺されたり、あるいは大学の医学部や製薬会社などに実験用に払い下げられていきました。
日本の犬たちの運命があまりに悲惨であったため、海外メディアがこれを取り上げ、英国で反日キャンペーンが起こるなど、国際的にも外聞が悪い状態となっていました。
■行政による犬猫の引取り
ようやく1973年(昭和48年)に、飼育動物への虐待を禁止する法律として「動物の保護及び管理に関する法律」(総理府所轄)が制定されたのですが、保護よりは管理の側面の強い法律であったため、「動管法」と呼びならわされてきました。
この法律で、犬や猫をどうしても飼育できない場合は行政がこれを引き取らなければならないという犬猫の引取規定が定められました。
法律では、行政の施設に引き取られた犬や猫をどうするかという規定はありません。引取りの犬猫をどう取り扱うかは、法律の下にある施行令「犬猫の引取り等に関する措置要領」(昭和50年 内閣総理大臣決定)に定められています。この措置要領の中に、3つの選択肢が記されています。
1,できるだけ新しい飼い主に譲渡すること
2,動物実験用として払下げること
3,殺処分すること
■行政による犬猫の処分
本来であれば、1番にあげられている新しい飼い主を捜して譲渡することが最もなされなければならない筈でしたが、実際は、上の統計のように、殺処分が最も多く、次は実験払い下げ、そして一般家庭への譲渡は最もなおざりにされてきたのでした。
その理由の一つに、自治体では犬の捕獲と、犬猫の引き取りは、衛生業務の一部として行われており、動物の福祉や新たな飼い主への譲渡など、動物の生命を尊重する姿勢を甚だしく欠いてきたことがあります。
動物の収容施設(抑留所)も劣悪で、日の光も差し込まず通風もない施設が多く、パルボやジステンバーといった伝染病がまんえんし、とても一般家庭への譲渡はできなかいという事情もありました。
また、動物実験への払い下げは、大量の動物を処分しきれないため、実験施設に殺処分を委ねるという意味もあったのです。国立大学の実験施設の前で犬の引き取りをし、そのまま実験室に送っていた自治体もありました。
実験施設に感染症にかかった犬が持ち込まれていたために、実験施設でも感染症がひろがり、実験以前の段階でほとんどが殺処分されていたという証言もあります。
■苦痛に満ちた殺処分
犬猫を大量に殺処分するためい考案されたのが、二酸化炭素によるガス室です。動物を密閉式のボックスに入れ、空気を抜いて二酸化炭素を吹き込むことにより、窒息により死に至らしめるという方法です。窒息死は動物に大きな苦痛を与えるもので、「安楽死」にはあたりません。ちなみに欧米諸国では、麻酔薬による意識の喪失を獣医師が処置する方法がとられています。
当会では長らくこのような犬や猫たちの悲惨な状況を訴え、遺棄の防止、動物行政の改善、その根拠となる法律の改正を働きかけてきました。次第に、事実を知った人々の声があがるようになり、世論となって行政や議会を動かし、この状況は少しずつ改善されるようになってきています。
1999年には「動物の愛護及び管理に関する法律」として法改正が実現し、2000年12月に施行されました。この法改正により動物虐待は懲役1年以下、罰金100万円以下となりました(所轄は総理府から環境省に移管)
■動物実験への払い下げは激減
この統計は、1974年から過去26年間の、行政による犬猫の実験払い下げの数字を示しています。数字は、飼い主が保健所などに自分の手で処分を依頼して持ち込んだ数のうち、動物実験にまわされた数であり、このほかに、捕獲された犬のうち実験に提供された数も相当数ありました。
日本では、過去何十年となく、捕獲されたのら犬や迷い犬、それに飼い主が行政に持ち込んだ犬や猫を動物実験に無料で払い下げるという悪習が続いてきました。その数は、統計で見る限り、1986年(昭和61年)ころがピークで犬猫あわせて10万頭を超えていたと推定されます。
1986年は、動物実験廃止・全国ネットワーク(AVA-net)の前身が発足し、犬猫の実験払い下げ廃止活動に取り組み始めた年でもあります。
1991年はじめに同会が取り組んだ「シロの事件」を契機に、東京都が払い下げを廃止し、その後、各地の自治体が順次廃止に取り組み、10年で10分の1にまでその数が減少しました。
 詳しくは、「私たちが、行政や研究機関に、犬猫の実験払い下げの廃止を求める理由」をご覧下さい。 詳しくは、「私たちが、行政や研究機関に、犬猫の実験払い下げの廃止を求める理由」をご覧下さい。
全国の人々の行政に対する働きかけにより、とうとう平成18年(2006年)には、実験払い下げという長年の悪習は、ゼロになる見込みです。
■一般譲渡の促進へ
上のグラフで示したように、実験への払い下げは急速に減少してきましたが、それに比して、一般家庭への譲渡の数(オレンジ色の線)には大きな増加は見られません。
動物愛護法の本体の主旨である、新しい飼い主への譲渡を促進するためには、まず行政の施設の改善が必要です。殺処分の用途にしか設計されていない施設を、一般譲渡を主目的とした用途に改築しなければなりません。感染症の対策(検疫、隔離、治療)ができるようにすること、そのためにも明るくて日差しや風通しのよい清潔で快適な施設にする必要があります。
このような施設への改築は、そこで働く人々の労働条件の改善となりますし、新しい飼い主となる一般の人々が訪れて楽しい施設にもなるでしょう。
また、一般譲渡の仕事には、民間の動物愛護NPOの協力により、きめ細かく面接や追跡調査などによってフォローしていくことができるようになるでしょう。
■殺処分の減少へ
現在、犬については毎年2万匹前後で殺処分数が減少しています。このままの比率で減少していけば、あと10年以内で殺処分ゼロの日がくることも夢ではないかもしれません。
ALIVEの調査では、平成15年度の犬の殺処分数は164,200匹ですが、そのうち、子犬33%、成犬 67%となっています。
また猫の殺処分数は275,600匹で、そのうち子猫は81%、成猫は19%となっています。この子猫はまだ目も開かないような産まれたばかりのものが大多数と言われています。このことは、特に猫については、不妊去勢の周知徹底により、8割以上の殺処分をなくすることができることを意味します。
飼育できずに殺処分ということに至る前に、飼い主のモラルの向上が強く望まれます。
|




![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求