| サルの福祉-飼育ハンドブック |
サラ・ウォルフェンソン+ポールホーネス共著 |
昭和堂 |
2300円 |
| 動物への配慮の科学-アニマルウェルフェアをめざして- |
M.C.アップルビー&B.O.ヒューズ著 |
チクサン出版社発行
緑書房発売 |
5600円 |
迷惑な進化
-病気の遺伝子はどこから来たのか |
シャロン・モアレム著 |
NHK出版 |
1800円 |
| 共生という生き方 |
T・ウェィクフォード著 |
シュプリンガー・フェアラーク東京刊 |
1900円 |
| 動物たちの喜びの王国 |
J・バルコム著 |
インターシフト |
2300円 |
動物感覚
-アニマル・マインドを読み解く |
T・グランディン他著 |
日本放送出版協会 |
3200円 |
| 植物という不思議な生き方 |
蓮実香佑 |
PHP研究所 |
1300円 |
アニマルウェルフェア
-動物の幸せについての倫理と科学-
|
佐藤衆介著 |
東京大学出版会 |
1800円 |
| 豚は月夜に歌う-家畜の感情世界 |
J・M・マッソン著
村田綾子訳 |
バジリコ(株) |
1800円 |
| 人体常在菌のはなし |
青木 皐 著 |
集英社新書 |
680円 |
| ゴキブリ取扱説明書 |
青木皐著 |
ダイヤモンド社 |
* |
| 共生の生態学 |
栗原 康著 |
岩波新書 |
640円 |
都市動物奮戦記
-東京生き物マップ |
佐々木洋監修
東京アニマル研究会 |
彩流社 |
1200円 |
嫌われものほど美しい
-ゴキブリから寄生虫まで |
ナタリー・アンジェ著 |
草思社 |
1900円 |
| ゾウがすすり泣くとき |
J・M・マッソン/
S・マッカーシー著 |
河出書房新社刊 |
2000円 |
| 生命(いのち)のよろこび |
高田宏著 |
新潮選書 |
1000円 |
| 動物たちの心の世界 |
マリアン・S・ドーキンス著 |
青土社刊 |
2200円 |
|
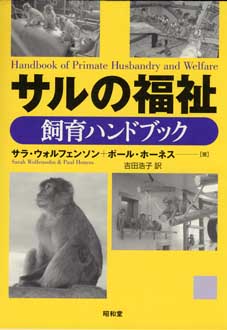 ALIVE No.88 2009.9-10 本の紹介 by 野上ふさ子
ALIVE No.88 2009.9-10 本の紹介 by 野上ふさ子
サルの福祉-飼育ハンドブック
サラ・ウォルフェンソン+ポールホーネス共著 吉田浩子訳
昭和堂 2300円(税別)
当会で調査しているニホンザルの飼育実態調査によって、飼育下にあるニホンザルの飼育環境は信じがたいほどに劣悪であることが明らかになりました。ニホンザルは「特定動物」で飼育が許可制であるため、飼育実態を情報開示請求によって知ることができるのは外部チェックの観点からは大きなメリットです。しかしまたニホンザルは「特定動物」であるがゆえに、逸走防止を主目的とする極めて小さく、頑丈な檻の中に閉じこめられ、苦痛にみちた飼育環境におかれています。
当会では、特定動物の飼養保管の基準が制定される際に、管理のみが強調されて動物の受ける苦痛が無視されないよう、福祉に関する項目を入れるように求めましたが、残念ながら実現できませんでした。この基準の改正も急務です。
日本ではサル類は実験動物として最も多く飼育されています。サル類は、マウス・ラットなどのげっ歯類より、長い寿命、複雑で高度な社会性、多様な認知能力、手先の器用さなどの側面で、はるかに人類に似ています。それにもかかわらず「動物というひと括りで、かれらが本来必要とする社会性(家族や仲間といっしょにいること)や行動特性(登る、隠れる、ぶらさがる、遊ぶなど行動の自由)は無視され、抑圧され、踏みにじられています。もし人間の子どもを、生まれてすぐに母親から引き放し、縦横高さが各1メートルにも満たない鉄の檻の中に一生の間閉じこめておくとしたら…身震いするような恐ろしい虐待行為と言えるでしょう。それなのに、相手がサルであれば、なぜ同じ事をしても誰も何も言わないのでしょう?まともに考えれば、とうてい容認できることではありません。
本書は「「現在のサル類の飼育状況を改善し、その福祉に役立つこと」を明確な目的として書かれています。サルの種ごとの行動特製、快適な飼育環境、健康を維持するための食べ物、感染症や病気のチェックと対策、心理的なケア、馴化、飼育者の訓練、輸送に際しての配慮、および関連法規などを網羅して記述し、その幅広い学問的見地に基く提言はたいへん説得力があります。日本のサルを飼育するすべての施設で本書を必読文献として備え付け、飼育関係者のすべての人々に読んでいただきたいと思います。
|
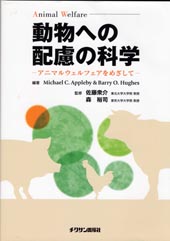 ALIVE
No.86 本の紹介 ALIVE
No.86 本の紹介
動物への配慮の科学
-アニマルウェルフェアをめざして-
M.C.アップルビー&B.O.ヒューズ著
監修:佐藤衆介/森 裕司 翻訳:加隈良枝 他
チクサン出版社発行 緑書房発売 5600円+税
アニマルウェルフェアは、動物福祉と訳されますが、本来は動物の幸福をはかるという意味でもあります。人が動物を飼育すること自体、かれらの幸福に反することかもしれませんが、それはさておくとして、人が動物を飼育する以上は、動物が幸せであるように配慮することは、人の責任であると言えるでしょう。
世の中にはしばしば畜産動物や実験動物に対して「どうせ殺す動物だから」、かれらの幸せを考えるなどバカげている、従ってどう取り扱おうが勝手だと言う人々がいます。そんなことを言うなら、あなたも「どうせいつか必ず死ぬのだから、それまでどんな苦しみに満ちた悲惨な人生であってもいいのですか」と問い返したいものです。
生きている限りは、健康で安心して幸せで生きたいということは、人も含めてすべての動物に共通する本質ではないでしょうか。
だからこそ、人間は飼育動物に対してその本質を理解し、それが実現するように行動するという倫理的責任があります。
それでは、動物の「幸せ」とは何なのでしょう。
それ知るためには、その動物が本来的に何を必要とし何を望んでいるのかを正しく理解する必要があります。その指標となるのが動物福祉の原則である「5つの自由」です。家畜に対して行われる、尾、羽、くちばしなど身体の一部の切断が動物にどれほどの苦痛を与えているか、また、ほとんど一生の間狭い空間に拘束されることからくる様々な慢性的ストレスが動物の心身にどのようなダメージを与えているか等は科学的な研究対象とすることが可能です。本書は、動物行動学の見地から見た福祉の問題点と対策を幅広くもうらしており、アニマルウェルフェアを学ぼうとする者には必読書となるでしょう。
動物福祉には合理的根拠があることが一般に広く理解されるようになり、市民の求める動物愛護の倫理、動物行動学者や獣医師による動物福祉の科学的知見の充実、政府・行政による法令の制定や執行があいまってさらに進んでいくことを期待したいと思います。
(野上ふさ子) |
 ALIVE No.82 本の紹介 ALIVE No.82 本の紹介
迷惑な進化
-病気の遺伝子はどこから来たのか
シャロン・モアレム著 矢野真千子訳
NHK出版 1800円+税
あらゆる生物は変動する地球環境の中で生き延びるために、自ら多種多様に進化してきました。進化論によると、現在の生物種は「適者生存」の原理によって、環境に
よりよく適合し、他種の生物との競争にうち勝ってきた個体の遺伝子を受け継いで生 き延びてきたとされています。ところが、この理論では生存に不利な病気の遺伝子が、
なぜ現在に至るまで生き延びてきているのか説明がつきません。
そこで、体に鉄分がたまるという疾患遺伝子を受け継いだ著者は、病気の遺伝子に も存在することの意味があるのではないかと考えたのです。この考察は、体内に鉄分
か過剰に蓄積される形質は、ヨーロッパ中世に人口の3分の1をも死亡させたペストを乗り越えるために獲得されたものではないか、という結論に導かれます。
糖尿病は、日本人にも大変多い病気ですが、本書で驚くのは、糖尿病は人類が氷河期を乗り越えるために獲得した形質だったかもしれない、ということです。人類の起源はアフリカにあるとされていますが、火を手中に納めたことから、徐々に北半球に広がり、北極圏にまで住み着くようになりました。
凍り付くような寒冷地で体温を一定に保つためには、体内の水分をできる限り少なくし、かつ血液中の糖分濃度を濃くする(血糖値を上げて)ように体内バランスが働くと考えられます。大規模な疫学調査でも、夏と冬の気温の差が大きい寒冷地に住んでいる人ほど、夏の血糖値は低く、冬の血糖値は高くなり、その差が大きいことが明らかになっています。寒い季節には血糖値をあげて寒さに適応してきた人々が、文明生活のせいで冬でも一日中暖かい暖房のある家屋に住むようになると、高い血糖値は糖尿病を引き起こし、健康には不利な要素となってしまいます。
本書には、このような人類の進化史と病気の関係を考察するたいへん興味深いエピソードが紹介されています。
(野上ふさ子) |
ALIVE No.81 本の紹介
人類が消えた世界
アラン・ワイズマン 著 鬼澤忍 訳
早川書房 2000円+税
20代の頃ですが、核戦争で破滅したと思われる世界の夢を見て、恐ろしさで目が覚めるということがありました。本当に、この地球から人類が消滅したら、そのあとの世界はどうなるのでしょうか?
この問いかけは、地球の生態系に対して、人類がどれほど好き勝手に破壊行為を行い、その破壊の傷跡から回復するのにはどれほどの時間がかかるかについて否応なく考えさせるものです。
人類の文明史は、火を手にして、森林を焼き払い、野生動物を絶滅させて、原野を畑にかえ、動物を家畜にして、大地を砂漠化させるという歴史です。すべての文明は滅びるという歴史観に立てば、このような破壊的な文明はまもなく限界を迎えて崩壊していくことが予想されます。文明は滅びても、地球上に誕生した「生命」は生き続け、新たな進化の歴史を作りだしていくことは間違いありません。ニューヨークのような大都市は、水や植物に覆われ、再び野生の王国がよみがえることが描き出されています。
しかし、人工的に製造されたプラスチック、無数の化学物質、放射性物質などは、場所によっては何万年も残存し、生物の遺伝子のかく乱を引き起こし、予期しない変異あるいは絶滅を引き起こすかもしれません。太平洋上で渦巻く、人間の生活圏から吐き出されたありとあらゆる分解しないゴミ捨て場は、アフリカ大陸ほどの大きさにふくれ上がっているとのことです。自然に還らない物質を生産することは犯罪とするような法律を作らない限り、人類の自滅の道は避けられないように思えます。
(野上ふさ子) |
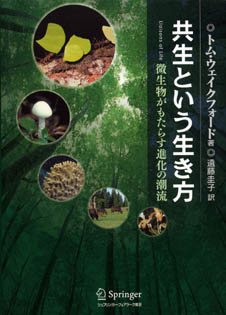 ALIVE No.77 本の紹介 ALIVE No.77 本の紹介
共生という生き方
トム・ウェィクフォード著 遠藤圭子訳
シュプリンガー・フェアラーク東京刊 1900円+税
地球環境や生態系の、あるいは生物のことを考えるとき、誰の目にも見えない微生物のことはしばしば見落とされてしまいます。しかし、微生物こそ、もしかしたらこの地球の本当の主人公なのかもしれません。
私たちは、自分の体は自分のものだと思っていますが、私たちの体のおよそ10分の1は、バクテリアのような微生物によって占拠されているのだそうです。もし大腸菌が腸の中に住んでいなければ、どんな食べ物を食べても消化されず栄養素を吸収することもできません。もし皮膚の上に常在菌がいなければさまざまな外的刺激の直撃を受けて、私たちの身体はあっという間にぼろぼろになってしまうでしょう。
私たちは彼らに身体という住まい(環境)を提供し、その見返りに彼ら(微生物)のサービスを受けています。異なる生物種が、お互いに互いを必要としている関係を相利共生と言います。これは、自然界に普遍的に見られる現象ですが、人間の体の中でもそのような関係が構築されているのは、驚きです。
私たちの身体が彼ら(共生微生物)の生息環境であるのですから、体重換算で言えば、1日のうち2時間くらいは彼らのためになるようなことを考える必要があるのかもしれません。
たとえば、ジャンクフードのような食分添加物や農薬まみれの食事は、彼らが分解吸収するのに難儀するだろうとか、抗生物質は彼らを善悪の見分けもなく無差別に殺してしまうので、腸内生態系をめちゃめちゃにしないように注意しなければ、などなど。
病気についても、病原体の立場に立って考えると、よりよい対処法ができそうです。
病原菌と呼ばれて悪者扱いにされている病原性微生物にも、生物としての存在の意味があるだろうし、生息地(環境)の快適性を選ぶ自由もあると考えられるからです。
もし病原菌が人間の体内で大いに暴れて宿主(人間)が死んでしまうようなことになると、自らの生息環境を消滅させることになり、自分で自分の首を締めることになってしまいます。それなので、病原菌は、急速な世代交代(変異)を重ねながら、人間に害のない常在菌に変貌していく傾向があるということが言えます。
これは、自然界でもよく見られることで、特定の外来生物が、未知の環境下に導入されたときにそこにニッチ(生態的空間)があると個体数が爆発的に増大するが、しかし、それは長くは続かないという現象です。すべての生物は、エネルギーを浪費する闘争を避け、領域を分け合って共存共生してきたのであり、これが地球の生物多様性の源泉ではないかと思われるのです。
(野上ふさ子) |
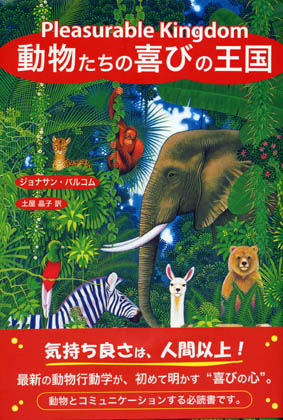 ALIVE No.76 本の紹介 ALIVE No.76 本の紹介
動物たちの喜びの王国
ジョナサン・バルコム著 土屋晶子訳 インターシフト 2300円+税
お天気の朝、小鳥のさえずりで目覚めたことはありませんか? そのさえずりは喜びにあふれているように聞こえないでしょうか。猫がひざの上でノドを鳴らしていれば、猫がリラックスしてよい心地でいるように思えます。散歩にでかけようとするとき、犬が飛び跳ねているのを見れば、彼(彼女)が期待でわくわくし大喜びしていることは間違いないようです。動物たちが楽しい気分でいると、私たちも何となく心がなごみます。
動物には痛みも苦しみの感覚もないなどという人は、今やほとんど存在しないと思いますが、動物には喜びや快感があるということについては、広く認知されているとは言えません。動物行動学者であるバルコムさんは、まさにその観点から動物たちの行動に光をあてました。私たち人間がそうであるように、動物たちは、仲間と楽しく遊んだり、おいしいものを食べたがったり、好みの恋の相手を選んだり、心地よさでうっとりしたり、していることを、さまざまな例をあげて示しています。
確かによく考えてみれば、人と動物は、地球上で生物進化の歴史を共にしてきた仲間であり、喜びの感覚を持つことは人間だけの特権ではないということは当然だと思われます。苦痛から逃れようとすることは、生きるために必要な不可欠な感覚です。
苦痛を感じなければ、身を守ることもできずにそのまま死んでしまうこともあり得るからです。
一方、喜びや心地よさを感じることもまた、それと同じくらいに生存にとって重要な感覚です。心地よいことはよりよい食事やよりよい環境を選ぶことをつながり、ひいては種の繁栄をもたらすでしょう。
かつて、ダーウィンの進化論が、「弱肉強食の生存競争」の観点のみが誇張され、ナチスなどに悪用されてきた歴史がありますが、同じころ、ロシアの生物学者、クロポトキンは「相互扶助論」の中で、生物の世界には互いに助け合い支えあう関係があることを強調し、平和的な社会の展望を示しました。人間と同じように、動物たちも楽しいことや心地よいことの感覚を広くわかちあっていることに気付けば、人間による動物に対するとめどない暴力や搾取もやむのではないでしょうか。そして、地球上で、さまざまな生き物たちが、生きることを楽しみ、幸福や喜びを感じていることを知れば、世の中はもっと平和になるのではないでしょうか。
(野上ふさ子) |
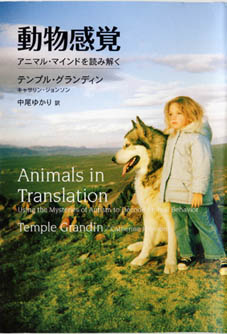 ALIVE No.73 本の紹介 ALIVE No.73 本の紹介
動物感覚 -アニマル・マインドを読み解く
テンプル・グランディン他著 中尾ゆかり訳 日本放送出版協会 3200円+税
全世界では何百億という動物が飼育されていますが、その動物たちは人間に飼われて幸せでしょうか?人間は動物を家族の一員として大切にしている一方で、食用にしたり、実験に使ったり、見せ物にしたりしています。どんな目的や用途があるにせよ、動物を飼育する以上はできる限り苦しみを与えないようにすることは人としての義務でしょう。
では、苦しみを与えないことに止まらず、動物ができるだけ快適に暮らせるようにするには、どうしたらいいのでしょう。そのためには何よりもその動物が本来何を必要としているか、そしてどのような行動をするのかといった動物に対する理解が必要です。
動物を理解するためには、自分自身が動物の立場に立って見ること、動物のような感覚をもつこと、がもっともよい方法でしょう。多くの人はこのような能力を欠いていますが、本書の著者はその分野では人並み優れた能力を持っています。著者はアスペルガー(自閉症の一種)であり、このような人はより動物に近い感覚や情動を持っているので、よりよく動物を理解できるし、またそれゆえに動物が受けている不当な苦しみを取り除くための仕事をするのに適していると言います。
本書では、「動物はこんなふうに世界を理解する/動物の気持ち/動物の攻撃性/痛みと苦しみ/動物はこんなふうに考える/動物の天才、驚異的な能力/動物の行動と訓練の仕方の問題点を解決する」について詳しく紹介され、中には動物についての理解で「目からうろこ」のような事柄がたくさん思いをすることもしばしばです。動物をよりよく理解し、虐待から救うためには、たいへん役立つ、お勧めの一冊です。
|
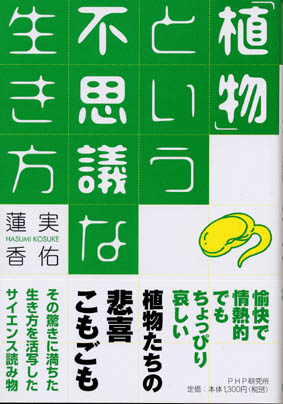 ALIVE No.68 本の紹介 ALIVE No.68 本の紹介
植物という不思議な生き方
蓮実香佑 PHP研究所 1300円+税
冷蔵庫の中にリンゴとキュウイと菜っぱをいっしょにしておくと、キュウイは早く熟し、菜っぱは早くしおれてしまうのにお気づきですか?なぜワサビは辛く、タマネギは目にしみるのでしょう?植物はなぜ色とりどりの美しい花を咲かせたり、美味しい果実を実らせたりするのでしょう?当たり前と思われていることも、よくよく考えれば不思議です。植物は、まさに生き物としてさまざまな活動をしています。自分を外敵から守る工夫もしていますし、危険信号を仲間に発信もしています。それというのも動物と植物ははるか昔をたどれば同じ起源に行き着くからで、だからこそ私たちは植物の生命活動を理解することができるのだと思います。植物達がどんなに一生懸命生きているかを知るには格好の入門書です。
(野上ふさ子)
|
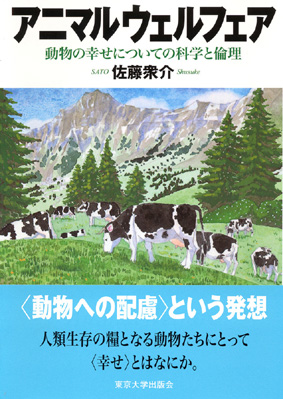 ALIVE No.64 本の紹介 ALIVE No.64 本の紹介
アニマルウェルフェア-動物の幸せについての倫理と科学-
佐藤衆介著 東京大学出版会 1800円(税別)
動物福祉とは、単に虐待を防止するにとどまらず、その動物にとってよりよい飼育環境や状態を提供することを意味します。例えばペットショップや動物園で、動物たちが日当たりも風通しもない場所の狭いケージや檻の中に入れられているのを見たとき、こんな状態が動物の心身の健康に悪影響を与えることはすぐにわかりますが、ではこのような劣悪な飼育状態を改善させるためにはどうしたらいいでしょうか。動物はそれぞれの種ごとに、本来その種の動物が必要としている生理的条件や行動特性に適う飼育環境が与えられなければなりません。その根拠となるのは、動物の生理、習性、生態等についての学問的知見に基づいて定められるべき飼育の基準です。
いま世界中で人間に飼育されている何百億匹という動物たちの飼育状況を改善するためには、動物福祉は必須の考えであると同時に、それが科学的根拠に基づく客観的な基準であることにより社会に受け入れられるものとなります。動物福祉は、倫理的にも科学的にも妥当な合意点としてその向上がはかられていくべきものなのです。
(野上ふさ子)
|
 ALIVE No.62 本の紹介 ALIVE No.62 本の紹介
豚は月夜に歌う-家畜の感情世界
ジェフリー・M・マッソン著 村田綾子訳 バジリコ(株)
動物たちの感情の世界を描き出して欧米でベストセラーとなった『ゾウがすすり泣くとき』の著者が、今度は豚や鶏、牛などの人間に食べられる動物たちの感情の世界を生き生きと描き出しました。ALIVEの畜産パネルは「食べる前に知って下さい」と呼びかけていますが、本書もまさにこの呼びかけにぴったりです。
人間という動物の心理や感情などについていは古今東西の文学や芸術などで表現されてきました。近年は、犬や猫などが家族の一員として同居するようになるにつれ、日々彼らの行動や心理、感情などがいかに多様で興味深いものであるかが多くの人々に知られることとなり、犬や猫に関する本は書店で一つのコーナーができるほどになっています。それに比べて、人間に食べられる動物である畜産動物の心理や感情について書かれた本はほとんどありません。人間と同じように社会性のある動物なのですから、牛や豚や鶏に喜怒哀楽の感情がないはずがありませんが、これに関してはこれまで誰一人関心を向けてきませんでした。おそらく、これは彼らが人間に食べられるためだけに生み出されているのだから、彼らがどのように苦しんでいるかなど考えたくもないし知る必要もない、と暗黙のうちに決めつけているからではないでしょうか。もし、彼らにも豊かな感情の世界があることを知ったら、私達は自分の考え方や生き方を変えなければならなくなるでしょう。それが嫌なので、皆が真実をあえて見ないようにしているのだということもできるでしょう。
しかし、いつまでも真実を知らないことは、自分自身の心の貧しさ、健康の喪失、自然環境の破壊や汚染といった現象となって、いつか自分自身に跳ね返ってくるように思います。毎日の食事の背後横たわる「隠された真実」を知ることは、近代的な工場畜産が極限にまで達し、様々な厄災が人々に襲いかかろうとしている今ほど、必要なときはないのです。
(野上ふさ子) |
 ALIVE No.59
本の紹介 ALIVE No.59
本の紹介
人体常在菌のはなし
青木 皐 著 集英社新書
人の腸には兆の単位で微生物が住んでいるらしい。そればかりか皮膚の上にもおびただしい菌が住み着いているとのこと。誰もがそんなことをまったく意識していないが、彼らが住んでいてくれるおかげで私たちは病原菌やウイルスから守られている。
抗生物質は腸内で休むことなく働いている善玉菌をも殺してしまい、過剰な洗顔は皮膚のバリアを壊して悪玉菌を呼び込んでしまう。健康と美のために微生物との共存を考える書。
(野上ふさ子)
|
|
ALIVE No.45
本の紹介
ゴキブリ取扱説明書
青木皐著、ダイヤモンド社
私は、「地球のすべての生き物が生存できる環境」の存続を心から願っています。すると、その生き物の中には、蚊やハエ、ゴキブリも含まれるのかと問われます。当たり前でしょう。地球上の生き物は何千万年という悠久の時を経て今日に至っているのだから、ひとつとして存在しなくてもいい種などはない、と思う。それにもかかわらず、人の社会は、自分勝手にある種の生き物を害虫とか害獣とかと名付け、これをとことん駆除(抹殺)しようとしています。
ゴキブリほど忌み嫌われる生き物はありません。しかし、相手を理解しようとする努力もなしにこの世から抹殺していいものでしょうか。本書の著者は、ゴキブリ3万匹を飼育しその生態を詳しく観察した結果、知れば知るほど面白くなり、いつか相手を尊敬し、愛おしいという気持ちにまでなったといいます。
ゴキブリのようにありふれた生き物について、私たちはいかに無知であるか。対策は、まず相手を知ることから始めること。駆除よりは防除(発生予防対策)の方に重点をおくというという視点は、人とのトラブルを抱える「有害鳥獣」対策にも役に立つように思えます。
(野上ふさ子)
|
|
ALIVE No.38 本の紹介
共生の生態学
栗原 康 著 岩波新書 640円+税
ライオンとシマウマの関係は「弱肉強食」だというのは、一面的な見方にすぎません。
肉食獣が草食獣を食べ尽くせば自分も飢えて絶滅してしまいます。一方、草食獣は草がある限り繁栄できますが、個体数が増え草を食べ尽くして大地を砂漠化すればやはり自滅するので、肉食獣に過剰繁殖のコントロールを委ねています。
このように互いに相手を必要とする相互依存的な共生関係は、動物・植物・微生物種の間で普遍的に存在し、その組み合わせはほとんど無限で多様な形態を作り出しています。
自然界がどれほど多種多様な生命の相互依存的なネットワークであるかを知ることは、私にとってはわくわくするような面白さです。
一方、またそれを知れば知るほど、自然界の中でヒトという一つの種だけが過剰繁殖し、かつ自然の完全管理という欲望を持つことは、必ずどこかで破綻してしまうということに、はっきりと気付いてもしまうのです。
(野上ふさ子)
|
ALIVE No.22
本の紹介
嫌われものほど美しい-ゴキブリから寄生虫まで
ナタリー・アンジェ著 相原真理子訳 草思社 1900円
大きな書店に行って棚の隅から隅まで見て回ると、書棚の大部分が人類に関する書物で占められていることがわかる。隅のわずかな一角を、犬や猫、それにイルカなどの本が占めている。目を皿にしてもゴキブリの子育てやマムシの恋のかけひき、寄生虫の一生についての本は見つからない。しかし、世の中にはこういう嫌われものを熱心に研究する人々もいるらしい。この人たちが、予断と偏見を持たずに、むしろ愛情を持って彼らを観察してくれるおかげで、彼らの世にも稀な能力や叡知が発見されつつあることに、感謝したいと思う。
といっても、本書は嫌われものばかりを好んで書いているわけではない。私たちと同じ地球に生きる様々な生き物たちへの深い関心と共感が、最大のテーマだ。毎日、せせこましい暮らしに明け暮れ、目先のことで精一杯の私たちの視野が広がって、生き物たちの魅力的な世界が少しでも理解できるようになれば、いいと思う。
( 野上ふさ子)
|
ALIVE
No.9 本の紹介
ゾウがすすり泣くとき -動物たちの豊かな感情世界
ジェフリー・M・マッソン/スーザン・マッカーシー共著 河出書房新社刊
西欧社会には長い間、心や魂があるのは人間のみであり、動物は肉体だけの存在で、しかも痛みも苦しみも感じない単なる自動機械のようなものであるという極論がありました。そのように自分勝手な解釈の上に、18世紀から19世紀における西欧諸国での野生動物に対する大量殺戮、家畜への虐待や酷使、残酷な動物実験が、正当化されてきたわけです。
しかし、20世紀の後半に至って、西洋における動物観は大きく変貌しました。人権・民族解放運動の延長上に生まれた「動物の権利」「動物の解放」の思想は、動物は人間と同じように痛みや苦しみを感じる存在であり、だからこそ不当な痛苦から解放されるべき権利があるという認識の上に成立しています。
本書では、動物に対する理解をさらに進めて、動物には痛苦の感覚ばかりではなく、喜びや幸せの感情つまり心もあるのだということを、様々な例証をもって主張しています。とすれば、動物は人間とは、ほとんど基本的に同等の存在であるということになります。著者の動物に対する共感と深い理解が感じられるとてもいい本です。当然のことながら、著者はベジタリアンであり、動物実験反対論者です。
(野上ふさ子)
|
ALIVE
No.9 本の紹介
生命(いのち)のよろこび -ドリトル先生に学ぶ-
高田 宏 著 新潮選書 1000円
たぶん今でも多くの子供たちが「ドリトル先生」シリーズを読んでいるでしょう。動物とともに暮らし、動物の言葉がわかり、いつも動物のために活躍するドリトル先生の冒険物語です。
もう半世紀以上も前に書かれた物語ですが、その中には、キツネ狩りや闘牛、動物園という牢獄、サーカスなどに対する批判、あるいは生き物をも皆殺しにする戦争や、病人を作り出すことによって利益を得る医療、生命の輝きを押しつぶしてしまう科学などなど、たいへん現代的なテーマがやさしく描かれていることを、著者は改めて発見させてくれます。
(野上ふさ子)
|
ALIVE
No.5 本の紹介
動物たちの心の世界
マリアン・S・ドーキンズ著 長野敬訳 青土社刊 2200円
実験用のラットのコロニーに、ふつうの餌Yと、食べるとしばらく具合が悪くなる餌Xとの2種類を与える。するとすべてのラットが餌Xを食べたわけでもないのに、全群が一斉にXを食べなくなり、それは世代を重ねても間続いた…その理由は、ラットが個々に学習したことを群れ全体に教え、そして子孫にまで伝えることのできる能力をもっていたから。人間であればこれを「文化的伝統」という…。
実験室という閉鎖された単純な条件下でさえラットはこれほど「賢い」。とすれば、複雑多様な環境で生活をしている野生のネズミは、もっとさまざまな影響に対して、自分で判断し、学び、それを仲間や子孫に伝えていくという行動をしているでしょう。
これまで、人々は動物の行動について、野生動物は「本能のまま」、家畜は「愚か」、実験動物は「単なる条件反射」というレッテルの下でしか見ようとしませんでした。けれども、このような人間中心の自分勝手な思いこみは、今大きく覆されつつあります。この30年くらいの間に、動物の行動をその社会や環境の中でとらえることによって、動物の心理や意識、さらには文化に関するさまざまな発見がなされるようになってきたからです。本書は、動物たちも多様な世界でそれぞれが意志決定し、自ら学習し、他者を理解し、相互扶助を行い…と、人間と同様に生きていることを、豊富な事例で紹介しています。
(野上ふさ子)
|




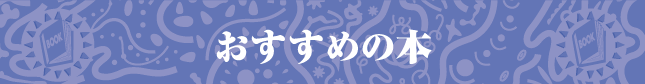
![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求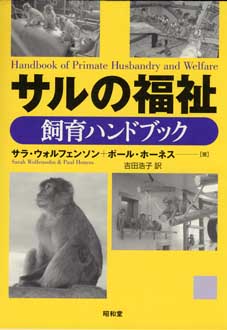 ALIVE No.88 2009.9-10 本の紹介 by 野上ふさ子
ALIVE No.88 2009.9-10 本の紹介 by 野上ふさ子
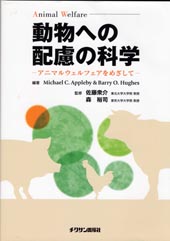 ALIVE
No.86 本の紹介
ALIVE
No.86 本の紹介