¡úF2004NRVúiújßãP¼`S¼
¡êF¶VrbNZ^[TK¤Cº
@s¶ætú1-16-21@
@ccnºSEãywPªiÛÌàüAìküAå]Ëüj
@scnºSEtúwRªiOcüj
¡åÃFn
¶¨ïciALIVEj
¡¿ãF500~
i»ÌðjÅqgÉÅàߢíASâ`pW[ÍA¡Ü³ÉâÅ¡OÅ·B
AtJÌnÅN±ÁÄ¢éßÍA½¿Æ³ÖWÌÅ«²ÆÅÍ èܹñB
½ÌS élX̺ÌݪAÞçðâ]Ì£©ç¯o·BêÌó]Å·B
»ê©ç̶ÌñÉǤ©¨ðX¯Ä¾³¢B
ñ@
J[EA}i춶¨Ê^ÆA춶¨Ûì®Æj
@XCXogBAJÌR[låwåw@ÅzeocwðêUB²ÆãAAtJÉnèAC^[R`l^EzeA}EgEPjAETt@ENuÈÇÉαµAAtJðKêéB1980Nãã¼AÇêÙǽÌå^ÞlªubV
~[gæøÌ]µÉÈÁÄ¢é©CâÄÈAÐàJðèú³¸A`pW[âSª¿ÈubV
~[gpÉE³êÄ¢»êðBeµÄ«½B
@A}ÌÊ^Æ|[gÉÕð󯽢BcïÆAtJ20ÍAì·ÞÌjEɽη麾ɼAJ[{Íá@ubV
~[gæøÉÖ·éïcðJõ½BubV
~[gæøÉ¢ĢEIÉmçêéæ¤ÉÈÁ½wiÉÍA}Ì·NÉn鮪 èA»Ì÷ÑÉεÄA±êÜÅXÌ®¨ÛìE춶¨ÛSÖAÌܪçêÄ¢éB
@@ú{ÅÍßÄÌêÊü¯WïBXChðp¢»nÌóµðAÉñ³êé\èB
Re[^[
¬´GYiqh{åw¼_³öj
@®¨wAlÔwA«ÈwÌêåÆB춮¨âÛì®ÉÖ·éì½B
JÃÌï|
¡qgÌ×lÆ¢íêéå^ÞliAtJÌ`pW[A{m{ASAAWAÌIE[^jÍAß\NÉn鶧nÌÁÅAubV
~[g̤ÆæøAybgpÂÌ̽ßÉÂ̪¸µA±ÌÜÜÅÍA Æ\NÅâÅ·é¨»êª èÜ·B
¡±Ìæ¤Èë@IóµÉ¨¢ÄA2000NTAUNEPiA«vOjÍGRASPiå^Þl¶¶væjð§¿ã°AWF[EOh[mAbZE~b^[}C[miConservation
International ï·jAsåw̼cå³öªAå^ÞlÁgƵÄA`[hE[L[mªÁÊÚâƵÄC½³êܵ½B»ÝAGRASPÍUNEPÆUNESCOiÛA³ç¶»Èw@Öj̤¯vWFNgƵÄeûÊ©çÌxðó¯AðN11ApÌUNESCO{ÅAåÃÌå^ÞlÉÖ·éÙ}ïcðJõܵ½B±±ÉÍå^Þlª¶§µÄ¢éAtJ23PÆAWA2PÌã\ªQÁµÄ¢Ü·B
¡Ûì·ÞwïàA¸·éå^ÞlÌóµÉë´ðø«A2001NPAå^ÞlðUNESCOÌ¢EâYíƵÄo^·é±ÆðÚWÉÁÊÏõïðݧµÜµ½B
¡AWAEAtJÌå^ÞlÍ]EÈÇƯlA¶ÔnÌvÆÈéíiumbrella
speciesjA»µÄÛ¥Iȶ¨iflag species jÌÐÆÂÅ èA±êçÌí̶§ÉKµ½©Rðçé±ÆÍA¯É»n̶ÔnÆ»±Ééç··×ÄÌ®¨ðçé±ÆÉàÈèÜ·BAtJâAWAšܳÉpðÁ»¤ÆµÄ¢éu×lvð~¤×ÉÍÛI¦Íªs¾ƢíêĢܷB
¡B̶Íå^Þl̶§Æê©A½ÌÖAàÈ¢æ¤Å·ªAÀÍå«Èe¿ÍðÁĢܷB[bpâAWAÌéÆÉæéXÑ̳ßȰ̪Þl̶§nðªfµAѹͧÂÒªXÑÌ[ÜÅüé½ßÌÖÈÊHÆÈÁĢܷBܽARs
[^[âgÑdbÉgp³êéR^Æ¢¤z¨ðÌ@·é½ßÉSÈÇ̶§·éÛìææÉlÔªüèA»nŲBÅ«éHÆƵÄÞç̽ðDÁĢܷB
¡»ÝAubV
~[g̤ÆæøÍAAtJɨ¢ÄͶ§nÌÁÅðz¦éºÐÆÈèAå^Þl̶§ðº©µÄ¢Ü·B±Ìâ誢EÌfBAÉæèã°çêAEUâAªæèoµ½wiÉÍÐÆèÌÊ^Æ̶ݪ èܵ½B±ÌlAJ[EA}ͳubV
~[gEn^[̦ÍÅA»nÌÀÔ𲸵A»Ì|[gâfð¢EÉMµACNN,
BBC, j
[[NE^CYADiscoveryÈÇA±ÌâèÉÖSðÁ½fBAÖWÒð»nÖÄàµA¢EÉå^ÞlÌë@ðmçµßܵ½B
¡¡ñAJ[EA}𨵫·é@ïð¾Aå^ÞlÌu©êÄ¢é«öAubV
~[gæøâá@°ÌÌ»óAâÅÌë@©çÞçð~¤×ɽ¿ÉÅ«é±ÆÉ¢Ĩb𨷫µA²¢ÁµåÉl¦½¢Æv¢Ü·B




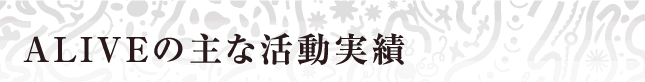
![]() @ALIVEÌÐî@
@ALIVEÌÐî@![]() @춮¨@
@춮¨@![]() @Y[¥`FbN@
@Y[¥`FbN@![]() @Æ뮨@
@Æ뮨@![]() @{Y®¨
@{Y®¨
![]() ®¨À±
®¨À±
![]() ¶½Ï
¶½Ï
![]() CtX^C
CtX^C
![]() ®¨Ûì@
®¨Ûì@![]()
![]() @¿W@
@¿W@ ![]() @rfI@
@rfI@ ![]() @ïñuALIVEv@
@ïñuALIVEv@![]() @æèµ¢}@
@æèµ¢}@![]() @Ql}Ðî@
@Ql}Ðî@![]() @N@
@N@![]() @¨â¢í¹@
@¨â¢í¹@![]() @¿¿
@¿¿