この地球に生きているのは人間だけではなく、数え切れないほど多種多様な生き物たちが共に、支えあってくらしています。
その生き物たちがもし集まって会議をしたら、何が一番のテーマになるでしょうか?
もし動物たちに発言権があるとしたら、人間に一番訴えたいことはなんでしょうか?
このアイディアから生まれた地球生物会議ALIVEは、今年(2006年)で満10年を迎えました。 |
 |
| |
会員の方がALIVE10周年を記念して
焼いて下さったケーキ |
ALIVEではこの10年間、常に現場の現実に立ちながら、なぜこうなのか、これを変えるにはどうしたらいいかを考えて活動を展開してきました。1年単位でみれば遅々たる歩みのようでも、10年経って振り返ってみれば、それなりの成果をあげることができたと思います。
動物たちにかかわる問題は、それが起こっている現場では個々の動物の犠牲という形で現れていますが、その背後には人の無関心、あるいは社会の制度や法律の不備といったものがあって引き起こされていることがほとんどです。であれば、動物の保護活動は社会に働きかける活動ということもできるでしょう。そのとき、変えたいと思う相手を知らずして働きかけることはできないので、否応なく、さまざまなことについて学んだり調査したり、情報収集をしてそれを分析するといった作業が必要になってきます。まさにこのような活動を通して、私たちは社会の一員であり、社会の仕組みに参加していくことの重要性を感じるようになります。
社会に向けての当会のこのような活動が継続できたのは、ひとえに多くの皆様のご支援とご協力に支えられていたからに他なりません。心から御礼と感謝申し上げます。そして、次の時代が地球の生きものたちにとって、よりよいものとなるように、今後とも皆で力をあわせてまいりましょう。
2006年4月
地球生物会議 ALIVE 代表 野上ふさ子
この10年間の主な活動とその成果をご紹介します。
・犬猫の処分実態の調査を行い、啓発普及ビデオ作成、大きな反響(1997年)
・第1回動物愛護法の改正、動物虐待への罰則強化等実現(1999年)
・毎年、全国の動物行政アンケート調査。動物行政の改善へ(1999~2005年)
・行政による犬猫の動物実験払い下げの全面廃止を実現(2005年)
・ペットショップ、ブリーダーなどの実態調査を行い、ビデオ作品作成(2003年)
・第2回動物愛護法の改正、動物取扱業者の規制強化等実現(2006年)
・動愛法改正を求める請願署名15万名提出。国会議員、各界著名人の賛同多数(2005年)
・英国の動物園査察官を招き日本初のズーチェックを実施、大きな反響(1996年)
・『動物園を問う』『イギリス動物園免許法』『EU動物園法』等、世界の情勢を紹介
・全国各地の動物園の実態調査を行い、ビデオ作品作成(2001年)
・劣悪な動物園に対する改善要望活動、環境エンリッチメント概念の普及
・世界動物保護協会との連携で日本のクマ牧場を調査、国際世論喚起、劣悪クマ牧場閉園へ
・ワシントン条約の輸入実態調査により経済産業省の施行方針の改善を実現(2004年)
・野生ニホンザルの有害駆除実態調査、違法捕獲の実態判明、実験捕獲の禁止実現(2002年)
・有害駆除動物に対する「安楽死」方針実現(2003年)
・署名活動、国会意見陳述等によりトラバサミの規制強化へ(1996年~2006年)
・特定外来生物法成立、外来動物の輸入規制強化へ(2004年)
・鳥獣保護法改正でNGO活動の成果(1999年、2002年、2006年)
・動物愛護法で動物福祉の原則3Rの明記(2005年)
・環境省の実験動物基準の改正、文部科学省・厚生労働省の動物実験指針制定へ(2006)
(動物実験分野では主にAVA-netの活動を中心として実施)
・酪農家、農業経済研究者、企業等と連携し家畜福祉の普及シンポジウムを開催
・畜産動物の飼育実態調査を行い、ビデオ作品作成(2006年)
・定期刊行物『ALIVE』誌の発行(68号まで)
・各国の動物保護法シリーズの翻訳発行
・動物園調査シリーズ等、資料集多数を刊行
・全国動物行政アンケート調査報告集刊行(1999~2005年度版)
・家庭動物、動物園、野生動物、実験動物、畜産動物等写真パネル100枚制作
・各種リーフレットの作製と配布
・各種ビデオ制作、ホームページでの情報提供
・パネル展、勉強会、シンポジウム等各種集会を各地で開催
・NHK、BS、CS、テレビ朝日、TBS、日本テレビ、フジテレビ、テレビ東京、東京MXテレビ、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、東京新聞、産経新聞、日本経済新聞、地方新聞、業界新聞、ネイチャー等専門誌、各種雑誌、フリーペーパー等、多数のメディアが取材報道
・世界動物保護協会WSPAに加盟
・WSPAに協力しクマ牧場キャンペーン、一部改善、廃園へ
・国際協力により国際希少動物(ラッコ、アジアゾウなど)の輸入停止の実現
・各国動物保護団体や活動家との情報交換、協力活動
・全国各地で動物行政の改善および行政の動物施設の改善活動
・パネル展を全国各地で開催(北海道、宮城、福島、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川、群馬、新潟、富山、長野、福井、愛知、岐阜、京都、大阪、三重、奈良、和歌山、兵庫、広島、岡山、福岡、沖縄)
・各種イベントに参加し啓発普及活動を展開




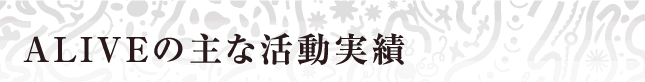
![]() ALIVEの紹介
ALIVEの紹介 ![]() 野生動物
野生動物 ![]() ズー・チェック
ズー・チェック ![]() 家庭動物
家庭動物 ![]() 畜産動物
畜産動物
![]() 動物実験
動物実験
![]() 生命倫理
生命倫理
![]() ライフスタイル
ライフスタイル
![]() 動物保護法
動物保護法![]()
![]() 資料集
資料集 ![]() ビデオ
ビデオ ![]() 会報「ALIVE」
会報「ALIVE」 ![]() 取り扱い図書
取り扱い図書 ![]() 参考図書紹介
参考図書紹介 ![]() リンク
リンク ![]() お問い合わせ
お問い合わせ ![]() 資料請求
資料請求